インタビュー
[インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/028.jpg) |
本作では,平和に暮らしていた学生たちが「最終防衛学園」に転校させられ,人類存亡をかけて謎の敵「侵校生」と戦うよう強要されるといった物語が展開される。
シミュレーションパートでは,学生たちが心臓に短刀を突き刺すことで,噴き出す血しぶきとともに「我駆力(がくりょく)」が発動,鎌や日本刀やバイクなどの形をした「学生兵器(クラスウェポン)」を駆使して戦いを繰り広げる。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/029.jpg) |
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/030.jpg) |
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/031.jpg) |
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/032.jpg) |
戦闘中は,死を伴う「決死必殺」を発動することで圧倒的な力を手に入れられる。しかも学園にある装置を使えば,死んだ者も何食わぬ顔で次の戦いに参加できる。
衝撃的な物語やアドベンチャーとシミュレーションRPGが両輪となったゲームならではの感情移入,100種のエンディング……と話題に事欠かない本作について,小高氏と打越氏に話を聞いた。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/027.jpg) 小高和剛氏(右),打越鋼太郎氏(左) |
[プレイレポ]エンディングは100種類!「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は,予測不可能な展開と尖ったシミュレーションパートが魅力
![[プレイレポ]エンディングは100種類!「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は,予測不可能な展開と尖ったシミュレーションパートが魅力](/games/811/G081143/20250415059/TN/065.jpg)
TooKyo Gamesとメディア・ビジョンが開発する「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」が,2025年4月24日にアニプレックスから発売される。「ダンガンロンパ」と「極限脱出」のスタッフが手掛けたシナリオと,尖ったシミュレーションパートが楽しめる本作のプレイレポートをお届けする。
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」公式サイト
※本稿(インタビュー内)にはゲーム内のネタバレを含みます
15人が共同生活を送り,謎の敵と戦う物語は,どのようにして作られたのか
4Gamer:
本日は,よろしくお願いします。まずは簡単な自己紹介をお願いします。
小高和剛氏(以下,小高氏):
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」の開発を担当している,トゥーキョーゲームスの小高です。シナリオとディレクションを務めました。
打越鋼太郎氏(以下,打越氏):
トゥーキョーゲームスの打越です。同じく,シナリオとディレクションを担当しています。
4Gamer:
2025年2月19日には「プロローグ体験版」が配信されましたが,プレイヤーの反応はいかがでしたか。
小高氏:
「ダンガンロンパ」や打越さんのファンから注目していただけています。
本作は,これまで僕らが手掛けたことのないシミュレーションRPGの要素を持つ作品です。その部分の反応を心配していたのですが,ストーリーと同じようにこのパートも作り込んでいることをご理解いただけたようです。
4Gamer:
プレイレポートのため,先行して製品版相当のバージョンをプレイさせてもらいましたが,シミュレーションパートもかなりしっかり作られていると感じました。
小高氏:
ほかのシミュレーションRPG作品とは少し違うゲーム性になっていますし,バランスも時間と人数をかけて突き詰めています。自信がありましたが,同時に不安もあったので体験版を出してよかったですね。
打越氏:
体験版には,小高さんが書かれたシナリオしか入っていないんです。ですので,製品版で私が書いた部分をプレイしてもらうのが楽しみです。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/021.jpg) |
4Gamer:
シミュレーションパートを導入しようと考えたきっかけを聞かせてください。
小高氏:
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」の企画は,僕と打越さんがシナリオを書くゲームというところからスタートしました。
“15人の学生たちが共同生活しつつ,襲ってくる敵と戦う”という「ダンガンロンパ」と「進撃の巨人」を掛け合わせたような設定を考えつき,それなら全員が同時に動いて欲しい……ということでシミュレーションRPGの要素も入れ込むことになったんです。
4Gamer:
設定からゲームシステムが決まったわけですね。
小高氏:
また,この2人で組むならウリにすべきは膨大なシナリオ量だろうということで,100種のエンディングを用意することになりました。
それぞれのルートで,フォーカスされるキャラクターやその扱いが違います。ゲーム中では,15人全員が活躍しますが,ルートによっては推しの扱いに絶望するようなこともあるかも知れません。
すべてをクリアするか,ご自身の推しが出てくるルートで満足されるかはプレイヤー次第というところでしょうか。
4Gamer:
エンディングを100種も用意しようと思ったのはなぜでしょうか。
小高氏:
(打越氏の方を向いて)これ,本当に僕が言ったんでしたっけ。
打越氏:
絶対に君が言ったよ(笑)。
小高氏:
なんとなく区切りがいいので,100日・100ルート・100エンディングという感じで決めたんだと思います。当初,打越さんは「無理でしょう」って反対していましたね。
全エンディングを見ていただくには,普通にプレイして130時間,自由行動を全部飛ばしても100時間くらいかかるんじゃないでしょうか。
ただし,コンプリートしないと見られない真のエンディング的なものは用意していませんので,納得いただけるエンディングが出たところで終わっていただいて大丈夫かなと。
4Gamer:
実際にプレイをしてみて,読者の興味を引くフックを仕掛けるタイミングが絶妙であると感じられました。大は読者を飽きさせないようなところで事件が起こり,小はセリフの中にちょっと過激な一言やパロディといった目を惹く要素が入っている。止め時が見つからなかったです。
小高氏:
「止め時が見つからない」という状態は「ダンガンロンパ」から意識しているところですが,本作では物語の組み立て方が違っているんです。
「ダンガンロンパ」の場合,ひとつの事件を物語の1章で描きます。ここで伏線を張り,ここで事件を起こし,その後のエピソードを描き……とやるべきことが決まっているわけです。
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は章立てではないので,100日という日数でシナリオを組み立てなければなりません。途中で話が終わってしまうようではダメなので,小事件を起こしてフックにするという仕掛けを散りばめています。
4Gamer:
フックのタイミングは,どのように調整したのでしょうか。
小高氏:
プレイヤーの視点に立って,シナリオを読み返すことにすごく時間を使いました。そのうえで,退屈になりそうなところがあれば事件のタイミングを前倒しにしたり,二転三転させたりという直しをしています。
最近のゲーマーは,ゲームを遊ぶだけでなく,映画やドラマもよく視聴するので,物語を飽きさせず,しっかりと読ませるための修正は非常に大事なんですよ。
今回のライターたちには,自身が担当したルートのスクリプトも打ってもらっていますから,最後の最後までいいバランス調整ができました。
4Gamer:
スクリプターに任せるのではなく,ライター自身がスクリプトを打つメリットはどこにあると考えていますか。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/018.jpg) |
スクリプターに預けてしまうと,思っていたものと違う演出になる“解釈違い”が起こりますが,ライター自身がスクリプトを打てばそうした事態は避けられます。
解釈違いの発生は,スクリプターが悪いわけではありません。ゲームのシナリオには情景描写などの地の文がないため,スクリプトを打つ際の手掛かりがないからです。しかし,ライターとしては思っていたのと違った表情やボイスを付けられてしまうことになるんですよ。
僕が「ダンガンロンパ」を開発していたときも,こうした解釈違いが多々あり,最終的に自分で直していました。そこで「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」では,スクリプト作業もライター自身に任せることにしました。
打越氏:
これまではライターがベースのスクリプトを打ち,これを別の人が直し,さらにライターが直しと何度も修正していたので,クオリティは上がっていると思います。
小高氏:
ただ分量が多いため,さらなる地獄の始まりでした(笑)。セリフの一つひとつに表情を選び,ボイスを鳴らし,画面を揺らし,音楽を鳴らして……ということをしているので,すごく大変なんです。
4Gamer:
シナリオも書いたうえで,細かな演出も自分で付けるわけですからね。
小高氏:
演出のために新たな表情や声が欲しいという話も出てきまして,特に表情はかなり追加しています。数が増えすぎてしまったので一旦は減らしましたが,結局足りないということでさらに追加しました。
最終的には,1キャラクターが100〜200の表情差分を持つことになり,指定するだけでも一苦労でしたね。丸一日を演出の作業に充てても,ゲームの中の100日のうち,5日分くらいしか進められないんですよ。
4Gamer:
15人という学生たちの数には,何か理由があるのですか。
小高氏:
学園ものなので,キャラクターが少ないとクラスメイト感がなくなってしまうんですよ。シミュレーションパートでも,使用できるユニットが1桁台になると寂しいですからね。15人もいれば個性が出せますし,これ以上だと書き分けが苦しいので,ちょうどいいかなと思っています。
また,キャラクターには戦いの中でどんどん死んでいってほしい……ということで,気持ち多めにしてあります。15人以下だと「ダンガンロンパ」と比べられてしまうというところもありますね(笑)。
4Gamer:
15人が一堂に会して会話をするシーンも多く,書き分けも大変ではないでしょうか?
小高氏:
もともとは「ペルソナ」シリーズのように,あまり誇張のない等身大のキャラクターを何人か入れたいと思っていたんですが,さすがに15人を書き分けるのは辛いものがありました。
そういう事情もあり,制作を進めると皆の個性がどんどん極端になっていきましたね。会話中のちょっとした一言でも誰が喋っているか分かるように,打越さんを含めたライターが個性の表現をある程度テンプレ化してくれました。
4Gamer:
最初に作ったキャラクターは誰ですか。
小高氏:
主人公の澄野拓海ですね。これまでの僕の作品にはいなかった,普通の少年っぽさがあるキャラクターです。そこから澄野との距離感ということで,ドSな雫原比留子や,「キャプテン翼」での名相棒である岬 太郎をイメージした蒼月衛人を作っていきました。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/001.jpg) |
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/002.jpg) |
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/003.jpg) |
4Gamer:
シナリオを書くうえで,最も苦労したキャラクターは誰ですか。
打越氏:
面影 歪です。基本的に小高さんが考えるキャラクターは特徴的で書きやすいんですが,面影は家業が殺し屋で,相思相愛の「殺し愛」をしたがっている……という過去設定がどこまで本当か分からないんですよ(笑)。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/004.jpg) |
小高氏:
根っこの部分でいい人なのか,そうでないのかが分かりにくいキャラクターですよね(笑)。
4Gamer:
お二人が気に入っているキャラクターを教えてください。
小高氏:
一番長く関わったキャラクターに思い入れがあるので,僕の場合は蒼月でしょうか。……まあ,インタビューごとに答えは変えているんですけれどね(笑)。
打越氏:
僕は雫原です。とあるルートではメインキャラクターのような扱いになっていますし,体験版以降に大きな展開がありますから。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/025.jpg) |
4Gamer:
キャラクターのシナリオですが,それぞれ担当するライターが決まっているのでしょうか。
小高氏:
そういうわけではないですね。まず僕がキャラクターの設定を作り,ベースになるルートを書いたうえで,打越さんやスタッフに渡しているという感じです。そこから皆の手で深掘りされたり,意外な一面が付け加えられたりしています。
4Gamer:
キャラクターデザインについて聞かせてください。特に難航したキャラクターはいますか。
小高氏:
キャラクターは,1体ずつデザインしていくというより,全員を並べてバランスを見ていくという感じで,難航した記憶はないですね。
例えば澄野の場合,主人公だから髪の毛は赤と決めており,頭身が変わったりはしましたが,ずっと今の感じでした。逆に喪白もこは,ギリギリまでいじり続けましたね。お母さんっぽさを出したいので,可愛過ぎてもエロ過ぎてもいけないし,色物過ぎてもいけない。
あとSIREIとNIGOUは,小松崎(類)さんに設定だけ渡してお願いしたのですが,出てきたものがイメージ通りだったので,一発OKを出しました。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/006.jpg) |
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/007.jpg) |
4Gamer:
プレイしていて印象的だったのが,15人全員がいずれも好感を持てる人物だったところです。特にあとから合流するキャラクターたちは,性格やシナリオ作りに巧みさを感じました。
小高氏:
作った自分としては,あとから合流する連中だけに,好感度は捨てて個性を取ったキワモノで揃えたという意識でした。
打越氏:
リアルだったら,絶対に友達にはなりたくない連中ではありますよね(笑)
小高氏:
新キャラクターが合流すると,もともといたメンバーは「あの人たちは急にやってきて何なんだ」という感情を覚えます。
新キャラクターたちが体育館にズラッと並び,澄野がひとり気圧されている気持ちをプレイヤーにも感じてもらいたかったんです。
4Gamer:
魅力的なキャラクターを作るうえで,注意している点はありますか。
小高氏:
本作の場合だと,自己紹介がすべてかなと思います。初期メンバーにしろ新キャラクターにしろ,自己紹介で心を掴んで好きになってもらおうということは心掛けていました。
ですから,皆の自己紹介のシーンは結構直しています。例えば新キャラクターが合流するシーンでは,かなりストレートな下ネタを入れていたんですが,弊社の女性ライターから「あれはキツ過ぎないですか?」という声が出たので減らしたりもしています。もしもあの下ネタをそのままにしておいたら,嫌がられてしまったかも知れませんね。
4Gamer:
多くのキャラクターを表現するうえで,大事にしていることがあれば教えてください。
小高氏:
「ダンガンロンパ」のときも今回も,“全員が主人公である”ということを意識していますね。そのために,自分が好きな漫画やアニメ,映画にゲームのキャラクターを2〜3体足してベースを作るようにしています。
例えばクールな女性キャラクターを作りたい場合,「『攻殻機動隊』の草薙素子のようなキャラクターが,どう言ってくれれば自分はグッとくるんだろう」といったところを積み重ねていく感じです。
逆にプレイヤーの動向を見て,どういうものが好かれているかという視点では,ものを作ってはいません。自分が好きなものを入れているだけなんですよ。
そのため,自分自身の知識や考えをアップデートするように心掛けています。自分の青春時代に直撃した作品だけを持ってくるのではなく,現在だと「ダンダダン」のような新しいものを意識したりもしています。
4Gamer:
ご自身の“好き”を詰め込んでキャラクターを作っているわけですね。本作に登場するキャラクターは,その性格の違いがシミュレーションパートにも生かされているような気がしました。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/009.jpg) |
小高氏:
確かに,シミュレーションパートでの性能込みでキャラクター像を作っていったところはありますね。
例えば銀崎は,敵の攻撃を反射できるのですごく使い勝手がいい。そして「必殺」や「決死必殺」もカッコいいからこそ,アドベンチャーパートでは極端に自己卑下するキャラクターにしようとなったんです。
4Gamer:
銀崎は,自己卑下するときに使うボキャブラリーが多いのも面白いですね。
小高氏:
定型句として同じことばっかりいうのも面白くないので,神谷英樹さんがXでしているポストも参考にさせていただきました。神谷さんは,悪口のボキャブラリーがすごく豊かですからね(笑)。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/010.jpg) |
4Gamer:
丸子は「こんなところに連れてこられていきなり戦えるわけがない」と怯える小人物ですが,そこに共感しました。
小高氏:
丸子は「ゲゲゲの鬼太郎」のねずみ男をアレンジし,かわいいねずみ男的なキャラクターを作ろうというのがスタート地点でした。
顔もいいわけではないし,小人物的だしと不安があったキャラクターだったので,気に入っていただけて幸いです。最終的には,表情も豊富な人間臭さを出せたかなと。バトルでも役に立ちますし。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/012.jpg) |
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/013.jpg) |
4Gamer:
キャラクターへ感情移入するうえで,アドベンチャーパートとシミュレーションパートが相乗効果を発揮する両輪になっていたような気がします。
1ポイント単位の数字をやり取りし,誰かが倒れるごとに有利になる尖ったシミュレーションパート
4Gamer:
シミュレーションパートはかなり遊びごたえがありました。1ポイント単位の数字のやり取りがシビアで,かつ命中率や回避率といった乱数がないので,純粋に戦術を問われる感があります。
小高氏:
本作の企画が始まったときに,シミュレーションパートのモデルとして参考にしたのが「Into the Breach」でした。こちらは詰め将棋としての方向性に振り切っていて,キャラクターの立ち方も我々が望む方向性のものではなかったため,いろいろと変えてはいますけどね。
要件は,「15人が同時に戦場に出ること」「たとえ死んでも蘇生装置で復活させられる設定があるので,キャラクターたちがたくさん死ぬこと」「たくさんの敵が出てきて『真・三國無双』のような派手な活躍を見せられること」です。
あとはレベルの概念を取っ払うことで,レベルが上がりすぎて戦いが退屈になることや,逆にレベルを上げないと敵に勝てないということをなくしたいと考えました。
4Gamer:
ふつうのシミュレーションRPG,といった感じではないですね。
小高氏:
「ダンガンロンパ」を遊んでくれた人たちはアドベンチャーゲーム好きだと思うので,シミュレーションRPGとしてこまごまとした要素を廃し,感覚的に分かりやすいよう1ポイント単位でのやりとりにしたんです。また,ゲームオーバーになったときの救済措置を設けています。
「1回負けたら防衛対象と全員のHPを全回復」「2回負けたらさらに難度が下がってイージーになる」という仕組みを思いついた瞬間,歯ごたえのある難しさでゲームとしてより面白くする,詰め将棋的な方向へ舵を切ることができました。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/014.jpg) |
4Gamer:
アドベンチャーパートでのキャラクター性と,シミュレーションパートでの性能はどのようにして決めていったのでしょう。
小高氏:
初期設定の段階で,キャラクター性とユニットとしての大まかな性能が決まっていました。
厄師寺はヤンキーなので近距離タイプに,丸子は情けないので武器はすごくカッコいいものにしたいのでガトリング砲に……というように,シナリオを面白くするための制限から大まかな性能を決め,メディア・ビジョンさんにお願いしたんです。
厄師寺は,移動距離に応じてアーマー値が付与されますが,そのような細かな点はゲームバランスやシミュレーションパートの面白さを加味して,メディア・ビジョンさんが設定してくれました。
4Gamer:
「必殺我駆力」と「決死必殺」に関してもゲームならではの感情移入があったと思います。
必殺我駆力を使うと一次的に行動不能になるので危険ですし,決死必殺は使うと死んでしまいます。蘇生装置で復活できるとはいえ,決死必殺を命じて死なせるのはプレイヤー自身です。
当初こそ抵抗があるものの,プレイ時間が長くなってくると「こいつはもう次のターンで確実にやられてしまうから,それよりは決死必殺で有効に散ってもらったほうがいい」などと考えている自分にゾッとしました。
小高氏:
決死必殺のシステム自体は最初の段階からありました。開発中は「決死必殺を使っても死なないで,HPが1ポイントだけ残る」「必殺我駆力がなく,決死必殺だけしか使えない」など紆余曲折しています。ただ,全体を見ていくとバランスがいいところに落ち着けたと思います。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/015.jpg) |
4Gamer:
キャラクターが繰り返し死ぬというコンセプトは,企画のどのあたりから存在していたのでしょう。
打越氏:
僕の記憶だと最初期からですね。
小高氏:
「防衛戦の中でもシナリオを展開させたい」というコンセプトがあったんですが,「死亡したキャラクターが次の会話で復活しているのはおかしいんじゃないか?」というところから設定を考えていくことになりました。
だからといって死亡させたままだと,ケースに応じた分岐を大量に作らなければならないことになります。また行動不能という扱いにしても,急いで治療してきたなんてことは不可能です。
それなら一周回って「死んだ人もすぐに復活する蘇生装置」というブラックジョーク的な扱いにしてしまったほうが,信ぴょう性があるんじゃないかと考えたわけです。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/016.jpg) |
4Gamer:
プレイ中,死なせたことで良心が痛むようなゲームにしようというコンセプトではなかったということでしょうか。
小高氏:
そうした部分もどこかにあります。ただ,戦場の現実を突きつけることは意識したかも知れませんし,命の軽さや重さを感じてもらうためにプレイヤーさんに介入してもらうようにはしましたが,ここから本作の企画がスタートしたわけではありません。
また,露悪的に生死を扱うようなものでもありません。戦争の絶望感や悲壮なところを描きたかったので,皆も後退しつつ戦っていくような話ですし,シミュレーションパートもこうしたイメージを表現するものになっています。
4Gamer:
決死必殺は使うと血しぶきが飛び散るなど,描写的にも容赦がありません。「探索」モードで決死必殺を使うとセリフが変わって「撤退する」という扱いになりますが,こちらに統一するという選択肢もあったと思います。
小高氏:
設定として,死が軽くなっているのは確かです。しかし,「ロスト」や「行動不能」では軽いですし,命の重みを出したいのでそれらの表現にはしていません。
死の軽さと少年たちに残酷なことをさせているという2点は同居させたかったんです。だから「どうしても血だまりがほしい」ともお願いしました。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/017.jpg) |
4Gamer:
物語として,見ているこちらの無責任さと,必死に生きようとしているキャラクターたちのギャップのようなものを体感させられました。
小高氏:
重さと軽さというのは意識した部分があります。現時点で詳しくお話するわけにはいきませんが,僕が書いたルートではゲームシステムを見てシナリオを変えた部分もあったりします。
4Gamer:
1回も決死必殺を使わずに100日をクリアすることは可能なのでしょうか。
小高氏:
フル強化しても難しいんじゃないですかね。
打越氏:
定石がないゲームでもありますから。実際,プロローグ体験版では弊社の担当者が思ってもみなかった方法でクリアしていました。
4Gamer:
シミュレーションパートではギリギリ勝てたという局面も多く,最後の最後までハラハラしっぱなしのプレイでした。
小高氏:
こちらも重さと軽さというキーワードに関連するところで,キャラクターが死ぬと,味方が有利になっていくというシステムで逆転を起こりやすくしています。
一般的なシミュレーションRPGだと,ステージの最後は一方的な殲滅戦になりますし,逆に相手の数が多すぎると勝てなくなってプレイヤーさんが諦めてしまいます。
言い換えれば “詰みが早い”のがシミュレーションRPGのシステムなので,そうならないようなシステムにしているわけです。
4Gamer:
シミュレーションパートのゲームバランスは,そのように調整したのでしょう。
小高氏:
弊社とメディア・ビジョンさんの両方でだいぶ時間をかけてバランスを詰めていきました。シミュレーションRPGが得意な人でも苦労するくらいの難度を目指していて,僕自身がプレイしてもときどきゲームオーバーになるくらいです。
得意な方と苦手な方がおられるジャンルであるのは確かですが,じっくり考えていただければなんとかなると思います。
4Gamer:
1回行動すると「疲労」状態になってろくに移動できなくなるので,一手一手が重くなるというシステムも面白かったです。ゲームの後半になると「戦略物資」のお薬で疲労を強制回復できるのも,戦時中っぽいブラックさがありますし。
小高氏:
疲労システムはメディア・ビジョンさんの発案ですね。たくさんのキャラクターを使ってもらいたいが,従来のシミュレーションRPGのようにひとりにつき1回の行動権があるというのはやめたいというお話がありました。
そこで全員まとめて行動回数を管理するAPのシステムを取り入れつつも,使うのがひとりに偏らないように疲労の仕組みが用意されたのです。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/020.jpg) |
自分たちが作る作品の力を信じ,がむしゃらに作り続ける
4Gamer:
先ほど,今のエンターテインメントもインプットされているというお話がありました。それらの作品は意識してインプットされているのか,それとも気づいたらチェックしていたのかどちらでしょう。
小高氏:
基本的には新旧問わず,見たことのない映画やドラマ,プレイしたことのないゲームを意識的に見たり遊んだりしますね。
ただ音楽は,常に新しいものを聞くようにしています。年を取ってくると,昔の音楽しか聞かなくなってくるじゃないですか。聞くだけで青春やらなにやらがフラッシュバックして楽しいですからね(笑)。
打越氏:
小高さんは本当にいろいろなジャンルをインプットしていますが,僕の場合は逆で,昔の曲とか聞いちゃいます(笑)。
今のエンターテインメントでインプットしているのは,映画やNetflixのドラマくらいですね。時間がないというのもありますし,今のアニメを見ても3話くらいで続かなくなるんです。
4Gamer:
お二人が注目している作品はありますか。
小高氏:
少し答えるのが怖いですね。
「週刊少年ジャンプ」などを読んでいても,僕が面白いと思う作品は大体打ち切りになるんですよ(笑)。第1話だけ面白くて,その後に失速してしまうというパターンも多いと思いますけど。
映像作品だと,「カウボーイビバップ」の渡辺信一郎さんが原作と監督をされている「LAZARUS ラザロ」や,ディズニープラスで配信されている「デアデビル:ボーン・アゲイン」でしょうか。
特に「デアデビル:ボーン・アゲイン」は,マーベル史上一番面白いんじゃないかと思います。ヒーローのデアデビルが出てこなくて,トランプvs弁護士みたいな法廷バトルが続いてるし,悪役のキングピンも市長になってるんですよ(笑)。
打越氏:
僕は,映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」ですね。九龍城砦が大好きなので,映画の中でものすごく丁寧に作り込まれているのが嬉しいです。日本では作れない作品だと思います。
4Gamer:
小高さんが言われた「第1話だけ面白い」というのは,結構重要なテーマだと思います。
小高氏:
問題の根底には,いろいろなものがインスタント化しているという昨今の事情があるんじゃないでしょうか。第1話はインスタント化したユーザーさん向けに,編集者も含めて時世やほかの作品をすごく計算したうえで作っていくけれど,その後でそうした手間を掛けられなくなって失速するということかも知れません。
4Gamer:
創作のうえでマーケティングや分析の比重が大きくなり,さまざまな分析を行ったうえでIPを立ち上げることが多くなっているというわけですね。お二人がものを作られる際は分析をされるのでしょうか。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/024.jpg) |
小高氏:
僕らの場合は,そこまで受ける受けないを計算しているわけではないです。だから「第1話だけ面白い」といったことになる心配もしていません。
打越氏:
漫画とゲームの性質の違いもありますね。買い切り型のゲームであればエンディングまでの内容が入っていますから,購入した人は多少面白くなくても,もったいないので最後までプレイすると思うんですよ。
連載ものの漫画だと,面白くなかったら打ち切りになるわけですからね。まあ出版社としては,たくさんの作品が打ち切られても1本が大ヒットすればいいわけで,ある意味残酷ですよね。
小高氏:
連載ものだと,逆算で物語を作れないのも大きいかもしれません。
4Gamer:
「ダンガンロンパ」や「極限脱出」シリーズには多くのファンがいますが,そこから新たなIPを立ち上げる際に苦労したことはありますか。
小高氏:
僕の場合は「ダンガンロンパ」というヒット作があるので企画が通りやすく,この状況を使って自分の好きなものを作っている気持ちです。過去作のファンは,それと同じようなものを求めているかもしれないのですが,自分としてはそこまで意識しないようにしています。
今回も「ダンガンロンパ」との被りはまったく考えず,気にしないでやっていこうというところからのスタートです。ただ新しいIPを作るときは,「ダンガンロンパ」と差別化していかないといけないとは考えていますね。
4Gamer:
ご自身のファンを徹底分析するような,マーケティング的な手法は使われていないということでしょうか。
小高氏:
そうした手法は小賢しいですし,滅びるべきだと思います。今回の企画はそんなことをしていたら通らなかったと思います。
プレイヤーが最後まで遊んでくれると限らないのに,100日・100エンディングというものすごいボリュームを作らないといけないし,我々がやったことのないシミュレーションRPGというジャンルに初挑戦するわけですから。
だから,今回はまず自分たちでお金を出して制作をスタートし,コンセプトに賛同してくださるパブリッシャさんを探していくことになりました。アニプレックスさんも,2回目の会合以降に企画を成立させる方向で動いてくださいましたし。
4Gamer:
パブリッシャを探す前から制作がスタートしていたんですね。
小高氏:
そうです。僕らだけで1年ほど制作を続け,その後にメディア・ビジョンさんが合流して……という感じでした。
目に見えて資金が減っていき,じきに枯渇することは分かっていたんです。パブリッシャが見つかるのがあと3か月遅れていたら危なかったですし,正に綱渡りでした。よくよく考えると,正気ではない作り方だとは思います(笑)。
打越氏:
小高さんは,パブリッシャが見つかってもいないのに「なんとかなるでしょ」という感じでしたね。
小高氏:
その頃の記憶って,あまり残っていないんですよ。あまりに辛過ぎて忘れちゃったのかなと(笑)。気にしすぎるとノイローゼになるので,なんとかなると言い聞かせるしかないですし。
4Gamer:
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」ですが,今後はどういった展開を予定していますか。
小高氏:
アニメや舞台といったメディアミックスもやりたいですね。エンディングが100種あるので,舞台なら見に行くたびに話やキャストさんが変わっているとか,本作ならではの要素があると面白いと思います。
4Gamer:
最後に,ファンや読者へのメッセージをお願いします。
打越氏:
このゲームは,自分たちが今までにない物量かつすべてを人力で作った,ゲーム史に残るものになっています。お手軽じゃないという意味では最近あまりないタイプの作品ですし,日本ならではのゲームになっていますので,ぜひ若い方にもプレイしていただきたいです。
小高氏:
「ダンガンロンパ」や「極限脱出」のファンの方には,「シナリオ面については相当面白いものができているので安心してほしい」とお伝えしたいです。
また,今までのシミュレーションRPGとはちょっと違った,ひりひりするバトルを楽しめるので,これまで僕らが作ったアドベンチャーゲームというジャンルに興味がない方もプレイしていただければと思います。
4Gamer:
本日は,ありがとうございました。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / [インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/026.jpg) |
尖った物語と尖ったシミュレーションRPGが両輪となり,ゲームならではの感情移入を作り出す「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は,その制作の過程もまた尖ったものだった。
小高氏と打越氏のファンはもちろんのこと,シミュレーションRPG好きにも楽しめる本作,プレイ後にこのインタビューを改めて読み返していただければ幸いだ。
「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」公式サイト
- 関連タイトル:
 HUNDRED LINE -最終防衛学園-
HUNDRED LINE -最終防衛学園-
- 関連タイトル:
 HUNDRED LINE -最終防衛学園-
HUNDRED LINE -最終防衛学園- 
- この記事のURL:
キーワード
- Nintendo Switch:HUNDRED LINE -最終防衛学園-
- Nintendo Switch
- アドベンチャー
- CERO D:17歳以上対象
- TooKyo Games
- アニプレックス
- クライム
- サバイバル
- プレイ人数:1人
- メディア・ビジョン
- PC:HUNDRED LINE -最終防衛学園-
- PC
- インタビュー
- ライター:箭本進一
- カメラマン:永山 亘
(C)Aniplex, TooKyo Games
(C)Aniplex, TooKyo Games
- HUNDRED LINE -最終防衛学園- 【メーカー早期購入特典】 小高和剛監修オリジナル書き下ろし小説 付

- ビデオゲーム
- 発売日:2025/04/24
- 価格:¥4,850円(Amazon) / 5432円(Yahoo)



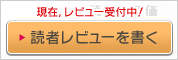






![[インタビュー]極限と絶望のADV「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」。その尖った作品の成り立ちを小高和剛氏と打越鋼太郎氏に聞いた](/games/811/G081125/20250422010/TN/033.jpg)










