インタビュー
[インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/001.jpg) |
「キセキのなべ」が壊れたことからミームたちが希望を失い,滅亡の危機に瀕する”という内容の絵本に出会ったプレイヤーは,絵本の結末を変えるべく,ミームたちをお手伝いすることになる。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/002.jpg) |
ミームたちは,ゲームにAIを生かした「がんばれ森川君2号」「アストロノーカ」といった作品で知られる森川氏がAIを手掛けており,なんとも不思議な生き物のような動きをする。
プレイヤーは個々のミームに直接指示を出すことはできず,ミームはプレイヤーが期待したのとは別の行動を取ることもある。オヤツを出しても目もくれずにさまよい歩いたり,ほかのミームがオヤツを奪ったりするのだ。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/006.jpg) |
今回4Gamerは,7月18日から7月20日まで開催されていたゲームイベント「BitSummit the 13th Summer of Yokai」の会場で,ドリコムのゲームカンパニー 開発統括本部 第3開発部 部長の人見 楽氏,E-ONE代表取締役である江藤桂大氏,モリカトロンの代表取締役 森川幸人氏にインタビューの機会を得た。
そんな「はらぺこミーム」は,当初まったく違ったゲームデザインが想定されており,AIのチューニングにも苦労があったという。ユニークな内容を志向したがゆえの苦闘と,AIの不思議さについて話を聞いた。
「はらぺこミーム」公式サイト
4Gamer:
本日はよろしくお願いします。まず「はらぺこミーム」の企画がどのようにして立ち上がったかを教えてください。
人見 楽氏(以下,人見氏):
まず「moon」「ちびロボ!」を手がけた西 健一さんから「遺伝的なシステムを持つシミュレーションを作りたい」と企画の持ち込みをいただいたのが,始まりです。
最初はユーザー数を見込めるF2Pでゲームを作りたいという動きがあり,「Sky 星を紡ぐ子どもたち」的な雰囲気のものを想定していたんですが,制作を進めるうちに,F2P市場自体が新規のオリジナルタイトルでは厳しいという結論に至ったんです。
4Gamer:
開発中止の危機になったと。
人見氏:
ただ世界設定もしっかり作り,いろいろ実験するなどして制作を進めていましたから,座組を変えたり,外部の方に協力していただいたりと可能性を探り続けていました。
最終的には江藤さんたちとゲームデザインを大きく変更したうえで,販売形態も買い切り型にシフトし,現在の「はらぺこミーム」の形になったんです。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/003.jpg) |
4Gamer:
紆余曲折があったわけですね。開発当初はどんなゲームだったのでしょう。
人見氏:
もっとコンパクトなゲームでした。AIで動き,遺伝の概念を持つキャラクターはそんざいしましたが,絵本のようなアートスタイル,村やごちそうや鍋,広がっていく世界といった,現在の「はらぺこミーム」にある特徴的なフィーチャーは存在しなかったんです。
「がんばれ森川君2号」的なステージクリア型ゲームを「リヴリーアイランド」的な世界で楽しめるゲームをテスト制作していた状態でした。
4Gamer:
まったく雰囲気が違っていたんですね。
人見氏:
まず西さんが作られた原案にあたる世界設定のアイデアと,現状とは違うシンプルなゲームデザインがありました。その後に私がディレクターになり,世界設定をあらためて膨らませつつ,ゲームデザインをまっさらにして作り直そうということになりました。こうして現在の「はらぺこミーム」の形になったんです。
森川幸人氏(以下,森川氏):
なので,原案,コンセプトについては西さんが作ったんです。キャラクターを動かし,ブリーディングによる遺伝を表現するのであれば,AIがあったほうがより生き物らしく見えるだろうことで私がサポートとAI担当として合流しました。
4Gamer:
F2Pと買い切り型,どちらのほうが制作を進めやすかったなどの違いはありましたか。
人見氏:
買い切り型のほうがやりやすかったですね。F2Pはマネタイズ(アプリ内課金による収益化)などゲームデザインへの制約が強すぎるし,運営し続けるリソースも考えなければなりません。
遺伝するAIキャラクターが登場するという斬新なゲームでF2Pの運営をやっていくのは難しく,誰も解決できなかったというのが正しい表現でしょう。
もちろん買い切り型も難しいんですが,F2Pほどのマネタイズは考えなくていいし,アイデアも「面白ければOK」という基準で追加していける強みがありました。
我々はベテランぞろいの15〜20人くらいの小規模チームです。それならすごく濃いゲームを作っていこうということになりました。
森川氏:
人見さんが苦しまれているのを横で応援していましたね(笑)。
4Gamer:
買い切り型になってから苦労したところはありますか。
江藤桂大氏(以下,江藤氏):
AIが思い通りに動いてくれないという部分ですね。
4Gamer:
AIキャラクターのゲームは思い通りに動かないところを楽しむ側面もあるので,思い通りにならないほど良いようにも感じられますが。
江藤氏:
目的なくキャラクターとじゃれ合うようなものなら,それでも良いのですが,「はらぺこミーム」は,クリアを目指すゲームです。クリアするためにはプレイヤーの狙い通りに動いてくれないといけない。ただ,AIは思い通りに動かないから先に進めないんです。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/004.jpg) |
4Gamer:
確かに,クリア型とAIらしさは相反する概念ですね。どのように解決したのでしょうか。
江藤氏:
森川さんの会社であるモリカトロンに「AIだけどコントロールしやすくしてほしい。それでいてミームは生き物らしく生き生きと動いてほしい」という感じでいろいろなお願いをすることになりました。
人見氏:
“自分ではなくAIが課題をクリアしていくのをどう楽しませるか”というゲームデザイン的な課題でもありました。
本当の意味でAIゲームを作られているのは日本で森川さんだけですから,森川さんにお願いすればなんとかなるだろうと。
江藤氏:
普通のゲームだと,プレイヤーが操作して進めますから,体験を設計できます。一方でAIはどう動く分からないし,型にはめられませんので,こうした不確実性をレベルデザインで封じ込めつつの制作となりました。
4Gamer:
ミームがどう動くか分からないからこその面白みはありますよね。同じような状況で同じように指示を出しても,振れ幅があるから魅力に感じることもあると思います。
森川氏:
内部パラメータを表示させずにデバッグを行っていますから,どこまでがAIの働きなのか分からないところはありますね。こちらとしては「バグに見えなければいいや」という感じではあります。
江藤氏:
その分からなさが逆に面白いところでもあるんですよね。
森川氏:
ミームを初めて世界樹に連れていく際,中身はまっさらであるはずなんです。ただ,“なぜかこちらの指示通りアイテムを回収してくれない”“クリアに必要な仕掛けを動かしてくれない”などの個性が出てきます。
プレイヤーからすると,ミームのキャラ付けとして意図的な演出であるように感じられるかもしれません。制作側としては「そんな設計はしていないはずなんだけどな……」と思いながらデバッグをしていたんですよ(笑)。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/012.jpg) |
江藤氏:
森川さんには「もう少しミームの行動をコントロールさせてほしい」とお願いすることが多かったですね。
4Gamer:
AIがウリのゲームである以上,あまりにコントロールされた行動が頻出するようではまずいとも思うのですが。
森川氏:
なので,ザックリとした調整にしていますね(笑)。
人見氏:
モリカトロンのスタッフさんたちは,ゲームへの理解が非常に深いうえにAIも扱えますから,心強かったです。
森川氏:
AIは完全にコントロールできません。予測不可能の行動をして予定調和に収まらないというのはAIをゲームに使う際は必ず出てくる課題です。
ゲームごとに異なる帳尻合わせというか落としどころを探していくので,多くのゲームでAIは隅っこに置かれることになります。
でも,モリカトロンにはベテランがいるので,ルールベース(人が決めたルールに従って動く)とニューラルネットワーク(脳の学習メカニズムを模倣し,AI自身が行動のルールを作る)のすり合わせには慣れています。
なので「ここはルールベースにしないと,プレイヤー主導の遊びとしては破綻する」といった部分は見極められます。逆に,若手にやらせるとすべてを機械学習で処理したがるんですよね(笑)。
人見氏:
ゲーム内の振る舞いすべてを機械学習でやろうとすると,事前の学習も手間がかかりそうですし,それこそゲームにふさわしい行動を取ってくれないという問題も出るでしょうね。
森川氏:
だから1人のエンジニアがプランニングとAI関連を同時にやらないといけないんです。そして,機械学習だけに頼ってしまうと「はらぺこミーム」というゲームが本当に面白くなったか分からなくなるという問題も出てきます。
人見氏:
3体のミームを同時に動かすのも難しかったですね。どの程度までAIを抑え込み,どの程度AIに任せるかはモリカトロンさんの経験が豊富なので助かりました。
ただ,デバッグの際には「(AIがゲームに合った動きをせず)チュートリアルが終わりません」という報告がテスターから上がってくることもありました。
4Gamer:
「はらぺこミーム」のAIはどういう仕組みになっているのでしょう。
森川氏:
ニューラルネットワークをバックプロパゲーションで学習させています。今話題のディープラーニングの一つ前の世代である,少しシンプルなモデルですね。まっさらの状態でも個性が出るようになっていて,初期ミームの時点でプレイヤーごとに違った体験ができます。ここにフレーバーとしての個性を加えたのが「はらぺこミーム」のAIです。
人見氏:
ミームのAIの育ち方は初期体験で変わってくるんですよ。早い段階で何か失敗すると,その行動をしなくなる。失敗が“心の傷”になり,避けるようになるんです。
森川氏:
ニューラルネットワークの学習は人間と同じなので,「三つ子の魂百まで」的な初期の経験が最も強く残る現象が起こります。プレイヤーが無責任なことをすると記憶に刻まれるわけです。
4Gamer:
では“心の傷”を負ったミームは特定の行動を取れなくなるのでしょうか。
森川氏:
ほかの場所で同じようなシチュエーションに立ちあわせ,正しい行動をさせればいいんです。そうすればミームは推論を行い,問題のシチュエーションでも行動できるようになります。
4Gamer:
まるで生き物のようですね。プレイヤーごとに異なる性格のミームになるということですか。
森川氏:
そうです。生き物と同じように学習するのがAIですから。逆に言えば,まったく同じミームになるということがあり得ません……まあ,そのおかげでテストプレイもドキドキものなんですけれどね(笑)。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/011.jpg) |
4Gamer:
デバッグの際,AIの中身を見えるようにしなかったというお話がありました。AIの中身が見えると便利そうですが,そうしなかったのはなぜでしょう。
森川氏:
AIはある種のブラックボックスだからです。パラメータを表示したところで誰も解析できないんですよ。これはディープラーニングでもLLM(大規模言語モデル)でも同様です。
「はらぺこミーム」でも学習の程度を示すエラー率という数字は拾えますが,なぜこうした結論に至ったのか,どうすれば望む方向に誘導できるかは分からない。このあたりは人間の脳も同じです。脳細胞ひとつひとつはシンプルなことしかできないのに,数が集まると非常に複雑なことができるわけですね。
江藤氏:
あまりに的外れな行動をしないよう,「はらぺこミーム」では“限られた環境の中でできることが増えていく”仕組みにしました。
例えるなら,赤ちゃんを囲い付きのベビーベッドで育てるのと同じようなものですね。ミーム自身は幅広い判断ができますが,ゲームデザインで封じ込めるというか,環境側でやれることを制限したんです。
人見氏:
プレイヤーはミームを介してゲームを攻略していると感じますが,実はミームを攻略しているんです。「ミームを何とかするゲーム」というアイデアを思いつき,これがブレイクスルーになった感があります。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/010.jpg) |
江藤氏:
当初は,木の実1つとっても,拾えるだけでなく壊せもするという,自由度の高いつくりでした。でも,途中からこうした自由度をなくし,ミームが取りうる行動を絞り込んでいくことになりました。
4Gamer:
自由度が高いほうがリアルに見えますが,なくしたのはなぜでしょう。
江藤氏:
ゲームとしての面白さに発展しないからです。面白くならないのであれば,カットしたほうがシンプルになるし,プレイヤーもミームをコントロールしやすくなります。
何の意味もない行動9割,意味のある行動1割より,半々くらいのほうがゲームとしては進めやすくなるんです。
人見氏:
何の意味もない行動は,ミームの立場からすると決断した意味があるものですが,プレイヤーの視点では意味がない。
4Gamer:
ただ,あまりに的確な行動ばかりするようでも,AIのゲームとしては良くなさそうに思います。
人見氏:
そうです。なので,こうした行動をどこまで許容するかのバランスは難しいです。
ミームがゲーム的に意味のない行動を取ったとしても,プレイヤーごとに好みが違いますから,その受け取り方はさまざまです。試行錯誤が生き物っぽいと感じる人がいれば,そうでない人までいるわけですね。
「はらぺこミーム」ではミームに直接指示を出せません。例えば,オヤツを与えるにしてもミームの近くに落として気付くのを待つことになります。時にはオヤツを与えたいミームが食べず,周囲のミーム同士で取り合いをしたりすることも起こりますが,これはさまざまな好みのプレイヤーに応えられるように配慮した結果です。
4Gamer:
無意味ではあるけどちょっと面白い挙動を許容できる人と,ゲームとしてサクサク進めたい人がいる。AIのチューニングだけでなく,仕様も工夫して,両者が満足できるようにしているというわけですか。
人見氏:
森川さんは,ミームをあまり賢い生き物として設定していません。これはAIの挙動とビジュアルを合わせての雰囲気作りです。事実,テストプレイヤーの中にはミームへの保護欲がかき立てられた方がいて,概してプレイへのモチベーションが高いという傾向がありました。
江藤氏:
プレイヤーが集まると,なぜかミームのダメなところを楽し気に語り合うんですよ。ちょっとおバカなところが可愛い。
人見氏:
最初は必要だったけれど,今はもう要らなくなったアイテムをせっせと集めるミームや,もう岩を壊さなくてもいいのにガンガン岩を砕いたりするミームを見たことがあります。まるで「自分はこれができるんだ!」とアピールしているかのように感じられました。
4Gamer:
なるほど。「三つ子の魂百まで」という初期の成功体験が残っているわけですね。
森川氏:
大体困ったことしかやらない。ミームは“いい感じにバカ”で,こっちがツッコミたくなる気持ちを引き出してくれるんです(笑)。
人見氏:
森川さんが作られるゲームでよくある光景ですよね。プレイしていて,飼っていた犬のほうが賢いと思いました(笑)。
森川氏:
ビデオゲームはキャラクターをコントロールするものが多いですから,「はらぺこミーム」は異質に見えるかも知れません。でも,ペットとの暮らしってこんな感じなんですよね。
AIというものは,従来型のシミュレーションゲームに押し込もうとすると枠にはまり切らないところがあるのは確かです。でも,ゲームというよりエンターテイメントとして考えるとシックリくる。そうした意味でも,今回の「はらぺこミーム」は冒険だったと思いますね。
人見氏:
「はじめてのおつかい」的にはしたいとはずっと話していましたね。
森川氏:
キッチリとお使いするよりは,見ている人がツッコミたくなるくらいのほうが面白いですから。
江藤氏:
プレイヤーとしては嬉しくない挙動を敢えて残していることもあります。その例が“ミームが何でも食べてしまう”という習性です。
1日には時間制限があり,特定のアイテムを持って帰らなければならないこともあります。プレイヤーとしてはすぐにアイテムを袋に入れてもらいたいけれど,その時ミームが空腹だったり,初めて見たアイテムだったりすると,とりあえず食べてみようとする。攻略には不利かも知れませんが,タイトルも「はらぺこミーム」ですから。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/013.jpg) |
森川氏:
本当は,本能を与えるべきだとは思います。呼吸など生きるための行動は教えられずにできて,目の前の物体が食べられるか否かも口に入れる前に判断できる。これをAIでやろうとすると,また作業量が増えるんですけどね(笑)。
4Gamer:
プレイヤーがコントロールでき過ぎてもダメ,予想外の行動を取るばかりでもダメ,程よく生き物っぽい動きをしなければならないわけですね。
ミームをブリーディングさせると,いろいろな姿のミームが生まれるフィーチャーも面白かったです。
人見氏:
ミームに多様性が出てくる様子を描きたかったんです。なので,ゲームが進んでいくと初期状態のような見た目をしたミームは生まれてこなくなります。残念に思う人もいるかもしれませんが,それは環境に適応してミームという種が変化していったということなんです。
ブリーディングの際には親の身体的特徴を受け継いだり,色や模様が変わったりといった現象が起こります。BitSummitの会場でも,我々が見たことがないようなミームが生まれていて驚きましたね。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/015.jpg) |
4Gamer:
進化や変化も体験できるわけですね。
森川氏:
ブリーディングの概念があると,あまり凝ったデザインにできないんですよ。子世代に姿を受け継がせられるよう,どうにでも変形できるようなデザインにしておかないといけないですから。
4Gamer:
今後アップデートは予定しているのでしょうか。
人見氏:
操作性をはじめとしたアップデートを行います。特に操作性についてはご指摘をいただいており,我々も真摯に受け止めていますので,なるべく早く配信できればと思います。
4Gamer:
最後にこのゲームはどんな人におススメかお聞かせください。
人見氏:
森川さんが描かれたキャラクターや世界の雰囲気に惹かれる人,ミームたちを見ていると,面倒を見てあげたくなる人ですね。
何をやるか分からないところが可愛い生き物っているじゃないですか。例えばウサギなんかは,いくら飼いならしても絶対に言うことを聞かない個体が出てくるものなんですが,そうした生き物が好きな人にはおススメだと思います。
また,常に使える最適解があるゲームではないですから,皆さんにタイムアタックしていただくのが楽しみですね。
江藤氏:
おバカなミームたちが出てきて,しかもいうことを聞いてくれない。森川さんが描かれた世界やミームたちに惹かれた方であれば,間違いなく楽しめるゲームだと思います。犬に指示を出しつつ障害物を乗り越えていく,アジリティ競技をされている方には向いているんじゃないでしょうか。
今までいろいろなゲームを作ってテストプレイもしてきましたが,2回目以降のテストプレイを面白く感じられることはまずなかったんです。ただ「はらぺこミーム」は,ミームの種類や村の状況が毎回変わりますから,面白くテストプレイを繰り返すことができました。
森川氏:
ユルくゲームをできる人だと思います。自分ですべてを制御し,最適解に近づけていく遊び方をするようなゲームではないので。昨今のゲームは続編が多く,ジャンルも固定化している気がします。その中で「はらぺこミーム」は幅を広げたというか,一石を投じたゲームになっていると思いますので,ぜひ体験してみてください。
4Gamer:
ありがとうございました。
「はらぺこミーム」公式サイト
キーワード
- PC:はらぺこミーム
- PC
- シミュレーション
- e-one
- ドリコム
- ドリコム
- Nintendo Switch:はらぺこミーム
- Nintendo Switch
- CERO A:全年齢対象
- プレイ人数:1人
- クラウディッドレパードエンタテインメント
- インタビュー
- BitSummit2025
- ライター:箭本進一
(C)Drecom Co., Ltd.
(C)2025 Drecom Co., Ltd. Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.



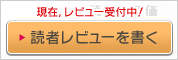







![[インタビュー]「はらぺこミーム」の魅力はおバカで可愛いミームたち。それを生んだのは,キャラをコントロールする遊びと思い通りに動かないAIのバランス](/games/872/G087244/20250730025/TN/016.jpg)










