プレイレポート
[プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/001.jpg) |
突如として発表され,多くのファンを驚かせた本作。なんだか具体的な内容もよく分からないまま発売日が近付いてきてしまった,という人も少なくないだろう。
そんな本作を,発売直前にじっくりと遊ぶ機会が得られたので,今回はそれをもとにしたプレイレポートをお届けする。ネタバレには最大限配慮し,重要なボスの名前などは可能な限り出していないが,気になる人は注意してほしい。
「ELDEN RING NIGHTREIGN」公式サイト
これまでに発表された情報をおさらい
主人公のスペックは本編より遥かに高い
遊んでみるまえに,基本情報をおさらいしつつ,「ELDEN RING」本編(以下,本編)とNIGHTREIGNの違いを確認しておこう。
まず,ジャンルが違う。NIGHTREIGNは協力プレイを前提に作られた作品であり,プレイヤーは3人チームを組んでボス討伐に挑むことになる。あえてソロで出撃すること自体は可能だが,ゲームデザインはあくまでマルチプレイ用。今回のプレイも,3人で行っている。
広大なフィールド「リムベルド」に降り立ち,2つの夜を乗り越え,3日目に出現する「夜の王」(ボス)を討伐すればプレイヤーの勝利だ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/002.jpg) |
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/003.jpg) |
戦いは毎回レベル1から始まり,初期装備以外は持ち込めないので,ボスと出会う前に育成を済ませる必要がある。リムベルドに出現する装備やアイテム,エネミーは挑戦するたびに変わるので,同じ攻略法は通用しない。
そのかわり,本作のプレイヤーキャラクターは「夜渡り」と呼ばれ,それぞれが一定の個性を持っている。初期装備やステータスが異なるだけでなく,汎用性の高いスキルと,必殺技にあたるアーツを活用することで,まったく異なる立ち回りができるのだ。つまり,本作にはキャラメイクがなく,プレイアブルキャラクターから選択する形式となる。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/004.jpg) |
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/006.jpg) |
行動範囲が広いこともあり,装備品関連の仕様や,操作システムも大きく変化している。ゲームプレイの手触りを明確に変えているのが機動力で,本編におけるトレント並の高速移動が生身で行えるアクション「疾走」が追加されたほか,ジャンプで壁を蹴って高所に登ることも可能になった。
さらに,落下ダメージは存在しないため,着地さえすれば落下しても死ぬことはない(奈落に落ちれば死ぬ)。本編の「褪せ人」と比較すると超ハイスペック。あまりに身体能力が高いので,本作に慣れたあとで本編をやると,うっかり落下死してしまうかもしれない。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/007.jpg) |
より細かな仕様については,前回のプレイレポートでまとめている。操作方法に加え,死亡時の処理,インベントリ関連の仕様についても紹介しているので,そちらも参考にしてほしい。
「ELDEN RING NIGHTREIGN」を4時間遊んで,分かったこと。約40分にRPGの“成長と達成”を詰め込んだ新世界をチェック

2025年2月5日,フロム・ソフトウェアは「ELDEN RING」のスピンオフタイトル「ELDEN RING NIGHTREIGN」のメディア向け先行プレイを実施した。本稿では,本作のシステムとプレイフィールをまとめてお届けしよう。2月14日から17日にかけて実施されるネットワークテストの参加者は,参考にしてほしい。
とにかく情報量が多くて忙しい
その先にある異常な中毒性
基本情報を押さえたところで,さっそくゲームを始めよう。今回は時間制限もなく,好きなだけ遊べるということで,とりあえず何も考えずにやれるところまでやってみた。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/008.jpg) |
1プレイの流れをざっくりまとめると,こうなる。
- レベル1でスタート
- 1日目のフィールド探索(バトロワ系のように,動ける範囲が狭まる中で敵を倒して,自身を強化していく)
- 1日目の夜に出現する中ボスを倒す
- 2日目のフィールド探索(ルールは1日目と同じ)
- 2日目の夜に出現する中ボスを倒す
- 夜の王(ボス)との戦いに挑む
つまりは,2日間でできるだけ強くなって,準備を整えてから夜の王に挑まなければならない。1プレイの長さは,夜の王にたどり着いた場合で40分程度だ。
ゲームを始めた直後は,面白さどうこう以前に「とにかく忙しい」という感覚で頭がいっぱいだった。把握すべき情報が多いゲーム性なのだが,ボスが出現するまでの時間は限られているため,立ち止まって考えている余裕がないのだ。
それに加え,始めたての頃は操作に慣れず,かつ「どこに行くと何が起こるのか」といった基礎的な知識が不足しているため,まごついているあいだに活動範囲の収縮が始まってしまう。戦闘の操作はほぼ本編と同じなので,プレイヤーに経験があれば中ボス戦くらいなら乗り越えられても,大ボスである夜の王を初見で撃退するのは容易ではない。
したがって,ファーストランで受け取った印象はやや漠然としたものだった。本編との違いについても,それが単に摩擦を生んでいるだけなのか,意味をなしているものなのか判別するのは難しかったように思う。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/009.jpg) |
しかし,ゲームへの理解がある程度進むと,少しずつ印象が変わっていく。マップに示されるアイコンの意味を覚え,それぞれから得られる報酬を把握すると,視界が開けたかのように試行錯誤が楽しくなってくるのだ。
たとえば,マップの各所には野営地や遺跡といった敵の拠点にあたる場所がある。各拠点には強敵が待ち構えており,倒せば大量のルーンと強力な報酬を得られる。となれば,野を走って適当に戦うよりも,拠点をめぐって戦ったほうが効率がいい。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/011.jpg) |
それ以外にも,マップにはたくさんの要素がある。聖杯瓶の数を増やせる「教会」,装備強化アイテムを確定で入手できる「坑道」,石剣の鍵があれば強敵と戦える「封牢」,聖印が収められている「小屋」など,それぞれ役割が明確に異なっている。
出現する敵の種類を見極め,仲間と意思疎通をして優先する場所を探し,アイテムを拾って次の計画を考えて――という流れを素早く展開していくのは,忙しいながらも楽しい体験だった。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/012.jpg) |
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/013.jpg) |
全体的にテンポよく物事が進行し,試行錯誤自体が苦になりにくいのもありがたいところ。選択するキャラクターによって手触りがまったく異なり,挑戦するボス(夜の王)との相性もあるので,遊べば遊ぶほどいろいろな要素を試したくなってしまう。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/014.jpg) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/017.jpg) |
何度も挑戦を重ねていると,本作独自の仕様とゲーム体験が少しずつ噛み合ってくる。NIGHTREIGNで変更された仕様の多くは,マップ探索と戦闘を素早くこなすためのものであり,使いこなすほど試行錯誤が楽になるのだ。
疾走やジャンプ関連の仕様はマップ探索に役立ち,ステータスや装備制限の簡略化は情報量を減らすのに一役買っている。そのほか,祝福に触れてからレベルアップに至るまでを一瞬で済ませられるなど,ほとんどの仕様が「ストレスのない探索と戦闘」を実現するために作られていることが分かる。
特に驚いたのは,ダウンと「致命の一撃」関連の仕様変更だ。本編ではダウン中の敵は無敵だったが,本作ではダウン中や致命モーション中にもダメージを与えられる。おかげで攻撃を集中させやすく,多人数で戦っていてもヒマな時間がない。このルールはプレイヤーには適用されず,ダウンしても安全に立ち上がれる。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/018.jpg) |
「DARK SOULS」シリーズからELDEN RINGまでの作品では,プレイヤーとエネミーに対し,可能な限り同じルールが適用されていた。そうした公平なデザインは,プレイヤーキャラクターが世界の一員であることを示し,プレイヤーの判断を尊重する世界観を表現していたように思う。
一方,NIGHTREIGNのプレイヤーとエネミーの関係は,ある意味で不公平である。こうした,ルールと世界の噛み合いをシリーズの美点として捉えていたなら,NIGHTREIGNの挙動に強い違和感を覚えるかもしれないが,本作においては間違いなくこの仕様がゲームを面白いものにしている。
「遺物」でより自由なカスタムが可能に
攻略中のコミュニケーションも楽しく
戦い続けていると,各種カスタマイズ要素が少しずつ充実してくる。その中でも攻略に直接の影響を与えるのが,討伐の成否にかかわらず獲得できる装備品「遺物」だ。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/019.jpg) |
今回のプレイでは,遺物にかなりのバリエーションがあることが分かった。単純にステータスを強化するものだけでなく,特定の属性を強化したり,初期武器を強化したりするものなど,さまざまだ。そのなかでも,初期武器に能力を付与するタイプの遺物は効果が分かりやすく,初期戦技を固定する効果や,状態異常属性を与える効果などは,あるとないとで序盤の安定性が大きく変わるように感じた。
ただ,特定の装備の能力を増強する効果や,状態異常になった敵へのダメージ増幅効果など,ある程度ビルドが固まってから効果を発揮する遺物は効果幅が大きい。走り出しと,最終的なビルドの完成度のどちらを優先するべきか,組み合わせに頭をひねっている時間は,カードゲームのデッキを組み上げているような楽しさがあった。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/020.jpg) |
また,遺物はシンプルにプレイヤーを強化するシステムであると同時に,取捨選択の方針を分かりやすくしてくれる要素でもある。最初は夜渡りの特性以外にはビルドを構築する指針がないが,遺物で「致命の一撃強化」を付与しているなら,致命補正のついた武器が魅力的に見えてくるだろう。
チームを組む仲間と情報をやり取りすれば,アイテムの受け渡しを早い段階から行えるようになる。ボイスチャットで通話をしながら遊ぶ場合,自分の遺物構成を相手に伝えておけば,より楽しくコミュニケーションを取りながら遊べるはずだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/021.jpg) |
ちなみに,拠点となる円卓には,攻略とは直接関係のない要素も用意されている。夜の王を撃破するとスキン切り替えシステムが解禁されるなど,意外といろいろな機能があるようだ。自身が選択していない夜渡りは円卓に配置されて会話できるので,ヒマな時間があったら歩き回ってみよう。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/022.jpg) |
本作が発表されてから今まで,筆者はこのゲームを「ELDEN RINGを長く新鮮に遊び続けたい人のためのゲーム」だと思っていたが,実際に遊んでみると「ELDEN RINGの基礎構造を使ったまったく別のゲーム」だった。
想像していたものと違う内容だったこともあり,やや面食らった部分はあるが,じっくりと遊んでみると実に味わい深い。正式リリースされた際には,ぜひ遊び尽くしたいと思うぐらいには,この味の変わったELDEN RINGは楽しい。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/023.jpg) |
現時点では,気になった部分もいくつかある。発生タイミングが悪いと理不尽にリソースをもぎ取られてしまうランダムイベント(襲撃)や,多数の敵と同時に戦うシーンでのロックオン関連の仕様など,調整してほしい部分もチラホラと見られた。
それに加え,事前知識が極めて重要なシステムであるため,いわゆる“野良”(ランダムマッチング)で快適に遊ぶのは,かなり難しそうだ。プレイ自体はできると思うが,夜の王の撃破となると,難度が跳ね上がる。よく分からないまま野良で遊び続けると,序盤で躓いてしまうかもしれない。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / [プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/024.jpg) |
そういった懸念点を踏まえても,本作の独自性と中毒性には目を見張るものがある。いわゆるバトロワ的なシステムを取り入れつつ,システムを協力の楽しさに全振りした本作の体験は,間違いなくNIGHTREIGNでしか味わえないものだった。
ELDEN RINGとは明確に異なる別のゲームながら,ELDEN RINGを下地にしていなければ生まれなかったであろう体験もあり,なかなか絶妙な立ち位置になっている。シリーズを愛するファンであればこそ気になる部分があるかもしれないが,それを感じ取るためにも,触れてみて損のない1本だと思う。
「ELDEN RING NIGHTREIGN」公式サイト
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- この記事のURL:
キーワード
- PC:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PC
- RPG
- MO
- バンダイナムコエンターテインメント
- ファンタジー
- フロム・ソフトウェア
- プレイ人数:1〜3人
- プレイ人数:1人
- 協力プレイ
- PS5:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS5
- Xbox Series X|S:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox Series X|S
- PS4:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS4
- Xbox One:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox One
- プレイレポート
- ライター:蒼之スギウラ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.



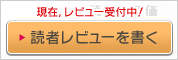




![[プレイレポ]「ELDEN RING NIGHTREIGN」は忙しくて,難しくて,そして楽しすぎた。全要素を“協力の楽しさ”に振り切った異色のスピンオフ](/games/866/G086614/20250527055/TN/025.jpg)










