イベント
「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/002.jpg) |
2024年にPS5で発売されたアクションゲーム「アストロボット」は,ゲーム初心者の子供からゲームに慣れ親しんだベテランプレイヤーまで,誰もが満足できる「分かりやすくて楽しくて驚きがあるゲーム」を目指して制作されたフラッグシップタイトルだ。
同作におけるレベルデザインの考え方やノウハウを,ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation Studios Team ASOBI のリードゲームデザイナー,矢徳浩章氏が紹介した。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/001.jpg) |
「アストロボット」公式サイト
準備&ジオメトリ編
本題に入る前に,矢徳氏はこのセッションにおけるレベルデザインを,「ステージを作る計画を立て,実際に地形を作り,いろいろなものを配置し,それらを体験としてユーザーに届けること」と定義してから話をスタートした。またステージ内のさまざまな体験を,流れるように新鮮な気持ちでプレイできることを「テンポがいいレベルデザイン」と表現すると前置きする。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/004.jpg) |
何事も準備が大切ということで,まず「1.調理の前にいい素材を見つける」というポイントが語られた。
曰く,「レベルデザイナーは調理人のようなもので,料理(ステージ)に使えるいい材料を見極めることも大切」とのことで,例えば[R2]ボタンでスポンジの水を絞る仕組みに面白みを感じたなら,それを素材にどんな料理を作るか発想を広げることが大切だという。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/005.jpg) |
スポンジを活用するなら,当然ながら水を吸い込むことになるので,ステージのアートテーマは水が関係したものになるだろうし,また絞った水をかける対象も必要なことに思い至るだろう。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/006.jpg) |
次のポイントは「2.アイデアを集めて試す」だ。アイデアをそのまま使うだけでなく,ほかのものと組み合わせてみるのも手だという。とはいえ,個人では限界があるので,チームの力を借りてブレストを行うのがベストである。Team ASOBIでは付箋にアイデア一つひとつを書いておき,それを集めてアーカイブしているとか。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/007.jpg) |
それらを実際にプレイして試す試作(ユーズケース)を作ることで,レベルデザイナーはそれが「いい体験」「楽しい遊び」であることをあらかじめ知ったうえで,実際のステージのデザインに取り掛かれる。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/009.jpg) |
次のステップは「3.目的を明確にする」ことだ。ユニークなゲームプレイが生まれたら,それを生かしたアートテーマの組み合わせを作って,「こんな体験を作る」という目的を明確化する。ここで初めてステージの計画にとりかかれるようになる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/010.jpg) |
そして「4.スタートからゴールまでを計画する」。ここではランドマークや登場する敵,スタートとゴール,どんな遊びを配置するかなどを1枚の絵にして,あらかじめ決めておく。また望ましい感情曲線もここで設計するという。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/011.jpg) |
Team ASOBIでは,レベルデザイナー自身がステージを作っていくので,細かい設計図は不要だ。まずは組みあげてみて,その後に実際にプレイしながら手直しを行っていくとのこと。
矢徳氏の話は,ここからより具体的なジオメトリ(ステージ全体の物理的な形や構造)の話題へと移っていく。これらはプレイヤーを迷わせず,しかし自分で行先を決めている感覚を持ってもらうための手法だそうだ。
これにはまず,「5.メインパスをわかりやすくする」ことが重要だという。メインパスとはスタートからゴールまでの主な経路のことで,これが明確であればこそ,プレイヤーは安心して寄り道できるようになる。また鎖やパイプをたどると行くべき場所が分かる,というやり方もあるそうだ。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/012.jpg) |
また「6.曖昧さをなくす」のも大切だ。目の前の段差はスロープなのか,それともジャンプする必要があるのかなど,プレイヤーが行うべき操作は明快にしておくべきだ。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/013.jpg) |
そしてプレイヤーが「7.進行方向を見失わないようにする」のも配慮すべきポイントだ。ゴールはランドマークの位置に置くのが基本で,地形が変化する場合は取り合えずまっすぐ上に進んだり,登ったりすれば間違いではないようにしておくのがコツだという。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/014.jpg) |
意外とストレスになりやすいのが,プレイヤーがステージの奥行きを勘違いしてミスしたときだ。「8.奥行きをわかりやすくする」コツとしては,同じ大きさ,同じ形の足場をいくつも並べることだという。これによりプレイヤーが奥行きを自然に捉えやすくなり,また入口と出口の幅をそろえることで,進んでほしいルートが伝えられるとしている。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/016.jpg) |
これらを合わせて,先に「9.移動パスを想定して地形を作る」方法もある。例えば想定したルートに合わせて,正対するように段差の形を作ることで,プレイヤーがスムーズに動けるようになる。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/017.jpg) |
また上のスライドの地形では,コンクリート上を歩き,金属の上でのジャンプ,金属上を歩いて,再びコンクリート……といった具合に,足音やコントローラのハプティック(振動)が変化する面白さも狙っているとのことである。
レイアウト&調整編
続いては,ステージに敵やさまざまなオブジェクト,装飾などを配置するレイアウトの考え方が説明された。
「10.移動パスを想定して配置する」場合の例として挙げられたのは,移動経路の途中に存在するブロックだ。これにはブロックをパンチし,素早く逆方向に切り返しす動きをプレイヤーに行ってもらい,気持ちよさを感じさせることを狙っている。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/018.jpg) |
「11.コントローラー操作を想定して配置する」は,リズミカルな操作で気持ちよさを生むための配置である。
これは「パラッパラッパー」の有名なフレーズ「Kick! Punch! It's all in the mind!」が登場するシーンのように,リズムゲームのノーツに合わせて攻撃やジャンプを行わせることで,気持ちよさを生み出そうとする手法とのこと。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/019.jpg) |
次の「12.アクションをつなげる」は,一つアクション操作を覚えたあとに,それを連続して行う場所を用意する工夫だ。また何かから逃げつつ移動したり,時間制限がある中でアクションしたりなど,少し難しい遊びを体験してもらうときも,その前にシンプルなパターンを試してもらうのが有効だという。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/020.jpg) |
プレイヤーに絶対に見落としてほしくないものがあるなら,「13.大事なものは中央に置く」べきだ。これはちょっとやり過ぎなくらいが効果的で,さらに重要なものの周りの地面はテクスチャを変えて強調するとのこと。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/021.jpg) |
円形のアリーナの中央にボスを置くのが定番だが,ボスにダメージを与えたときに中央から外れた動きをさせることで,スリルや緊迫感を与えることも可能だとか。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/022.jpg) |
配置のテクニックは強調ばかりでなく,さり気ないものもある。「14.装飾で空きスペースを埋める」という手法は,広々と動けるステージを単調に感じさせないようにするテクニックだ。例えば,移動を遮らない草むらを置くことで,移動を制限することなく,何となくエリアを区分けできる。また草に触った音やハプティックで,手触りを楽しませることも可能とのこと。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/023.jpg) |
人間は散らかった場所に行くと不快を感じやすいが,自分で散らかすのは大好きだ。この習性を利用し,「15.物理オブジェクトはまとめて置く」のがとくに有効とのこと。またステージの重力方向の変化を知らせる場合も,まとまった数の物理オブジェクトを用意しておくと分かりやすくなる。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/024.jpg) |
「16.説明なしで教える」は,ゲーム中になるべくテキストを表示させずに,遊び方を伝える工夫である。これにはテキストを読むためにゲームが中断するのを防ぎ,テンポを良くする効果がある。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/025.jpg) |
また新しいアクションやギミックを伝えるには,それを実際に試せる試遊場を用意するのが手っ取り早い。プレイヤーが操作を理解すると,そこから出る方法も分かるのが理想的だ。またボスバトルの直前などは,「12.アクションをつなげる」を応用して,バトル中に使ってほしいアクションを先に伝える手もある。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/026.jpg) |
ゲーム中に操作ができない時間が続くと,プレイヤーは不満を感じやすい。例えばステージの形状変化を見せているときも,できれば「17.操作できない時間を減らす」べきだ。先に進めないとしても,ただ見るだけの時間が生まれるよりはマシであり,これによりプレイヤーは「ストーリーを見た」ではなく,「体験した」と感じやすくなる。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/027.jpg) |
人間は見た瞬間に行動を変更するのは難しく,情報を処理して計画するのにある程度の時間を要する。そこで,敵などを登場させるタイミングには猶予を設け,「18.1秒先を計画できるようにする」とよい。これにより,テンポよくゲームを進めるようになる。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/028.jpg) |
ちなみに画面の上方向に上っていくステージは,先まで見通せないため対処が難しくなりがちだ。進む先に何かギミックがあるなら,プレイヤーがそれを認識し,利用するための時間が十分に確保できているかをしっかり考える必要がある。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/029.jpg) |
終わりよければすべてよし。ステージ終盤の内容は,プレイの印象を大きく左右する。「19.ゴールに向けて盛り上げる」は,ゴール直前に山あり谷ありの体験を用意しておき,気持ちを盛り上げてゴールインしてもらう「おもてなし」の手法といえる。ボスバトルを乗り越えてもらうのも,シンプルながら有効な一手である。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/030.jpg) |
ひみつ編・カメラ編
次のひみつ編は,サブパス(寄り道)要素や収集アイテムなどをステージに隠すときのコツを説いたものだ。「20.隠すときはヒントをつける」は,明確な発見の瞬間の前に,何かきっかけを用意することで喜びを盛り上げる工夫である。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/031.jpg) |
例えば1か所だけほかとパターンが違ったり,落ちていくはずのものが落ちなかったりといった,「おや?」と思わせる要素を先に用意しておく。それを辿ると発見に至る,気持ちの流れを作ることが大事なのだとか。現代のリッチなゲームであれば,音の聞こえてくる方向なども,ヒントとして活用できるそうだ。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/032.jpg) |
また「21.発見の難しさにメリハリをつける」ことも大切だ。「アストロボット」では,寄り道しつつもテンポよく遊べるバランスを目指し,寄り道の7割は「簡単に発見できるが,アクション的なチャレンジが必要」なもの,3割は「ほどほどに難しく,探すのを楽しめる」ものになっているという。ただ,シークレットゴールだけは発見や謎解きを楽しみたいプレイヤーの期待に応えられるように,あえて難しくしているとのことだった。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/033.jpg) |
そして寄り道は,ちゃんと寄り道だと認識できるようにしたほうがいい。「22.サブパスは少し目立たなくすること」では,寄り道をあえてメインパスと異なる方向に進ませること,あるいはメインパスより細い道にすることで,これを視覚的に伝えようとするものとなっている。
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/034.jpg) |
さらに寄り道の体験を強化するために,「23.サブパスからの帰りは楽しくする」ことを心掛けるといい。ただ同じ道を戻るだけでは退屈なので,一気に飛び降りて帰るなど,見た目にも楽しい近道が開放されるといった,「おもてなし」を用意しておくべきだ。さらにメインパスに戻ったときは,カメラがメインパスの進行方向やゴール方向を向いているのが理想である。
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/035.jpg) |
ステージ制作後のフィードバックでは,「24.行けそうな場所にもご褒美を置く」が徹底されているかを確認するといい。いかにも寄り道できそうな場所や,例えハズれであっても寄り道を探した形跡があるなら,そこにちょっとしたご褒美を置いておくのである。ほか難しいアクションをこなした先にも,些細でいいので「遊べる要素」が用意しておくと,プレイヤーは喜んでくれる。
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/036.jpg) |
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/037.jpg) |
ここからはカメラ制御のコツになる。「25.カメラ操作なしでもプレイしやすくする」は,プレイヤーが進む方向が自動的に正面になるよう,カメラをゆっくりと動かす手法を指している。いっそテストプレイ中は,右スティックによるカメラ操作を封印してしまうのもオススメとのこと。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/038.jpg) |
また「26.場所ごとに遊びやすいカメラを設定する」のも有効なテクニックだ。アナログスティックでカメラを操作しているあいだは,どうしてもボタンが押しにくくなるので,慎重なジャンプが求められる地形では見下ろし気味に,周囲の状況を把握させたいなら引き気味にと,シーンに合わせてカメラを調整するのである。ほかにも,掴んだものを振り回して投げてもらうときは,回しているあいだに「投げてほしい対象」に自動でカメラを合わせてしまうテクニックも紹介された。
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/039.jpg) |
そしてプレイヤーに没入感を感じてもらうなら,「27.カメラとプレイヤーの距離を近くする」のがポイントとなる。カメラを近づけると,どうしても得られる情報量が減ってしまうので痛し痒しだが,意図せずカメラを離しすぎないのが重要である。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/040.jpg) |
このセッションが伝えたい本質「考え方編」
セッションの最後には,これまで紹介してきたレベルデザインの根底にある,少し抽象的な「考え方」の紹介が行われた。
「28.量より質」は,面白さに自信が持てないときに物量でカバーしようとするのはやめようという教訓である。例えばステージを3層構造に拡張するよりも,2階層でも楽しめる状態を目指すほうが,結果的にいい体験につながりやすい。アートチームやサウンドチームの負担を減らすこともできる。
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/041.jpg) |
「29.ロジックだけで考えない」は,レベルデザインは単に「必要要件を満たすことではない」というメッセージだ。ここまでに紹介されたポイントを守っていたとしても,そこにプレイヤーを楽しませる「魂」が入ってなければ,面白いステージは生まれない。
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/042.jpg) |
そして,いよいよラスト30個目のポイントは「30.何度も作り直す」ことである。Team ASOBIでは,2週間ごとにタスクの計画とレビューを行い,試作したステージを多くのスタッフでプレイして,いい点悪い点を書き出してブラッシュアップしていく作業を行っているという。
![画像ギャラリー No.043のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/043.jpg) |
矢徳氏は「プレイヤーが楽しめる状態に向かって,何度も作り直すことが大事」といい,さらにそれはレベルデザインだけでなく,「アストロボット」の制作全体に通底した考え方だと強調して,セッションを締めくくった。
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / 「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/044.jpg) |
「アストロボット」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 アストロボット
アストロボット
- この記事のURL:
キーワード
- PS5:アストロボット
- PS5
- アクション
- CERO A:全年齢対象
- ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- プレイ人数:1人
- イベント
- ライター:高橋祐介
- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー
- CEDEC 2025
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
- 【PS5】アストロボット(ASTRO BOT)【早期購入特典】・封入ポスター ・アストロのパラッパ 少年ラッパーコスチューム(ゲーム内アイテム)* ・デュアルスピーダー - 栄光のグラフィティ(ゲーム内アイテム)* ・アストロのPSNアバター2種 *アンロックするにはゲームの進行が必要です。

- ビデオゲーム
- 発売日:2024/09/06
- 価格:¥6,045円(Amazon) / 5382円(Yahoo)



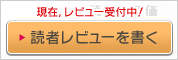






![「アストロボット」のレベルデザインを支えた30則。Team ASOBIのリードデザイナーが語る体験の作り方とは[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250728050/TN/045.jpg)










