イベント
「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/001.jpg) |
※CEDEC運営事務局からの要請により,このレポートは講演の一部内容を省略したダイジェスト版となっている
「アストロボット」公式サイト
2024年に発売されたPS5用ソフト「アストロボット」は,ゲーム初心者のお子さんから長年ゲームを遊んでいるベテランプレイヤーまで,誰もが満足できる「わかりやすくて楽しくて驚きがあるゲーム」を目指して制作されたアクションゲームだ。セッションでは,レベルデザインの考え方やノウハウが伝えられた。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/002.jpg) |
本題に入る前に矢徳氏は,“レベルデザイン”を「ステージを作る計画を立て,実際に地形を作り,いろいろなもの配置し,それらを体験としてユーザーに届けること」と定義する。また,ステージ内にあるいろいろな体験を流れるように,新鮮な気持ちでプレイできることを「テンポがいいレベルデザイン」と表現すると伝えた。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/004.jpg) |
準備&ジオメトリ編
何事も準備は大切ということで,まずは「1.調理の前にいい素材を見つける」。矢徳氏は「レベルデザイナーは調理人のようなもので,料理(ステージ)に使えるいい材料を見極めることも大切」と語る。例えば,[R2]ボタンでスポンジの水を絞る仕組みが面白いと感じたら,それを素材にどんな料理を作るかと発想を広げていく。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/005.jpg) |
水を吸い込む必要があるのでステージのアートテーマには水が関係するだろうし,また絞った水をかけるものも必要だと気が付くはずだ。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/006.jpg) |
次に「2.アイデアを集めて試す」。アイデアをそのまま使うだけでなく,ほかのものと組み合わせてみるのも手だ。とはいえ,個人の力は限られているので,チームの力を借りてブレストを行う。Team ASOBIでは付箋ひとつひとつにワンアイデアを描いて集め,それをアーカイブしている。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/007.jpg) |
それを実際にプレイできる試作(ユーズケース)を作ることで,レベルデザイナーは「いい体験」「楽しい遊び」を知った状態でステージデザインにとりかかれる。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/009.jpg) |
そして「3.目的を明確にする」。ユニークなゲームプレイが生まれたら,それを活かすアートテーマの組み合わせを作り,「こんな体験を作る」という目的を明確にする。ここで初めてステージの計画にとりかかる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/010.jpg) |
続いて,1枚の絵として「4.スタートからゴールまでを計画する」。ランドマークや登場する敵,スタートとゴール,どんな遊びを配置するかなどをここで決めておく。また望ましい感情曲線も決めておく。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/011.jpg) |
Team ASOBIのレベルデザイナーは,ステージを自分自身で作っていくので,細かい設計図などは不要だ。その後は組みあがったものをプレイしつつ,手直ししていくことになる。
次に,矢徳氏の話はジオメトリ(ステージ全体の物理的な形や構造)へと移る。これらはプレイヤーを迷わせず,しかし自分で行先を決めている感覚を持ってもらうための考え方だ。
それにはまず「5.メインパスをわかりやすくする」。メインパスとはスタートからゴールまでの主な経路のこと。ここが明確であればこそ,プレイヤーは安心して寄り道することもできる。鎖やパイプをたどると,行くべき場所が分かる,というやり方もある。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/012.jpg) |
また「6.曖昧さをなくす」のも重要。目の前の段差はスロープなのか,それともジャンプする必要があるのかなど,プレイヤーが行うべき操作は明快にしておきたい。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/013.jpg) |
プレイヤーが「7.進行方向を見失わないようにする」ことも配慮すべきポイント。ゴールはランドマークの位置に置くのが基本だ。また地形が変化する場合は,とりあえず真っすぐ上に進んだり,登ったりすれば間違いではないようにしておく。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/014.jpg) |
意外とプレイヤーのストレスになりやすいのが,ステージの奥行きが分からずにミスをしたとき。「8.奥行きをわかりやすくする」コツとしては,同じ大きさ,同じ形の足場をいくつも並べることで,プレイヤーが自然に理解しやすい状態になる。また,入口と出口の幅を揃えると,進んでほしいルートを伝えられる。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/015.jpg) |
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/016.jpg) |
これらを合わせて,先に「9.移動パスを想定して地形を作る」ことも考えられるという。たとえば,想定したルートに合わせて正対するように段差の形を作るとプレイヤーがスムーズに動ける。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/017.jpg) |
また,上のスライドの地形ではコンクリートの上を歩き,金属の上でジャンプ,金属の上を歩いて,再びコンクリート……という具合に,足音やコントローラのハプティック(振動)が変わる面白さも狙っている。
レイアウト&調整編
続いて,ステージに敵やモノ(オブジェクト),装飾などを置くレイアウト編だ。「10.移動パスを想定して配置する」例としては,移動経路の途中のブロックが挙げられた。ここではブロックをパンチ,素早く逆方向に切り返しす動きをしてもらい,プレイヤーに気持ちよさを感じてもらうことが狙いだ。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/018.jpg) |
「11.コントローラー操作を想定して配置する」は,操作をリズミカルにしてもらうことで気持ちよさを感じてもらうため。「パラッパラッパー」のKick! Punch! It's all in the mind! ……ではないが,リズムゲームのノーツに合わせて攻撃やジャンプをしてもらい,気持ちよくなってもらうという考え方である。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/019.jpg) |
次の「12.アクションをつなげる」は,1つのアクション操作を覚えてもらったあと,それを連続して行う場所を用意する工夫だ。また,何かから逃げつつ移動したり,時間制限がある中でアクションをしたりと,少し難しい遊びを体験してもらいたいときにも,先に簡単な例を試してもらうことが有効になる。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/020.jpg) |
プレイヤーに絶対に見落としてほしくないものがあれば,「13.大事なものは中央に置く」といい。これはちょっとやり過ぎなくらいが効果的で,さらに重要なものの周囲の地面はテクスチャを変えて強調する。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/021.jpg) |
円形のアリーナの中央にボスがいるという配置も定番だが,ボスにダメージを与えると中央からずれて動くようにすることで,スリルや緊迫感を与えたりもできる。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/022.jpg) |
配置のテクニックは強調するばかりでなく,さり気ないものもある。「14.装飾で空きスペースを埋める」は,広々として自由に動けるステージを,単調に感じさせない方法だ。例えば,移動を遮らない草むらを置くことで,移動を邪魔せずエリアを何となく分けられる。また,草に触った音やハプティックなど,手触りで楽しませることもできる。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/023.jpg) |
「15.物理オブジェクトはまとめて置く」。これは最初から散らかった場所に行くと不快感を感じやすいが,逆に自分で散らかすのは大好きという習性を利用したテクニックだ。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/024.jpg) |
また,ステージの重力の方向が変わったことを見せるために,まとまった数の物理オブジェクトを使うという手もある。
「16.説明なしで教える」はゲーム中になるべくテキストを出さず,遊び方を伝えるということ。テキストを読ませると,ゲームが中断してテンポが悪くなるためだ。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/025.jpg) |
新しいアクションやギミックについて伝えるには,実際に試してもらえる試遊の場を用意するのがいい。プレイヤーが理解すると,そこから出る方法も分かるという具合だ。
また,ボスバトルの直前などは「12.アクションをつなげる」を応用して,バトル中に使ってほしいアクションを先に伝えておく手もある。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/026.jpg) |
ゲーム中,操作ができない時間が続くとプレイヤーは不満を感じやすい。「17.操作できない時間を減らす」は,ステージの形状変化を見せる時間でも,操作は可能にしておく考え方だ。
先に進めなくとも,ただ見ているだけよりはいい。そうすることで,「ストーリーを見た」のではなく「自分が体験した」と感じやすくなる。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/027.jpg) |
次は「18.1秒先を計画できるようにする」。人間は思った瞬間に行動できるわけではなく,1秒程度の計画変更の時間を必要とする。そこで,適切なタイミングで敵を登場させると,プレイヤーはそれに対処でき,テンポよく楽しむことができる。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/028.jpg) |
画面の上方向に上っていくステージは先を見通せないため,対処が難しい傾向がある。プレイヤーが仕掛けを認識し,利用する時間を確保できているのかをよく考えたいところだ。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/029.jpg) |
終わりよければ,すべてよし。ステージのラストの印象は大事である。「19. ゴールに向けて盛り上げる」は,ゴール直前に山あり谷ありの体験で気持ちを盛り上げつつ,ゴールインしてもらう「おもてなし」の手法だ。シンプルにボスバトルを乗り越えてもらうのもいい。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/030.jpg) |
……その後もポイントは30まで続くのだが,それらは後日掲載予定の詳報をお待ちいただくとして,本稿は矢徳が最後に語っていた言葉で締めくくりたい。それは「プレイヤーが楽しめる状態に向かって,何度も作り直すことが大事」ということ。作ったステージをスタッフが集まってプレイし,いい点や悪い点をまとめ,ブラッシュアップしていく。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/031.jpg) |
それはレベルデザインだけに限らず,「アストロボット」全体がそうだったと述べ,矢徳氏は本セッションを終えている。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / 「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/032.jpg) |
CEDEC 公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 アストロボット
アストロボット
- この記事のURL:
キーワード
- PS5:アストロボット
- PS5
- アクション
- CERO A:全年齢対象
- ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- プレイ人数:1人
- イベント
- ライター:高橋祐介
- CEDEC 2025
- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
- 【PS5】アストロボット(ASTRO BOT)【早期購入特典】・封入ポスター ・アストロのパラッパ 少年ラッパーコスチューム(ゲーム内アイテム)* ・デュアルスピーダー - 栄光のグラフィティ(ゲーム内アイテム)* ・アストロのPSNアバター2種 *アンロックするにはゲームの進行が必要です。

- ビデオゲーム
- 発売日:2024/09/06
- 価格:¥6,045円(Amazon) / 5382円(Yahoo)



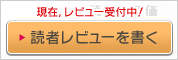






![「アストロボット」のテンポよく遊べる3Dレベルデザインの秘訣。Team ASOBIはどのようにユーザー体験をデザインしたのか[CEDEC 2025]](/games/803/G080391/20250724058/TN/033.jpg)










