イベント
インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/001.jpg) |
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/002.jpg) |
このセッションは2本立てで,前半の「理想に挑み,現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル」では,モノリリスのモーノ氏とリリス氏が,「ヘルヘル」の開発における試行錯誤を,理想と現実の違いを交えて紹介した。
また後半の「Berserk or Dieの絵作りとヴァンサバのponcleとの出会い」では,Nao Gamesの柴田 直氏が個人で開発した「Berserk or Die」のグラフィックスについて,意識したポイントを解説すると共に,インディーゲームパブリッシャであるponcleとの出会いを語った。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/003.jpg) モノリリス |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/004.jpg) 柴田 直氏 |
理想に挑み,現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル
モノリリスが現在開発中の「ヘルヘル」は,最大4人のプレイヤーによる協力型アクションゲームで,ローカルとオンラインプレイの双方に対応している。プラットフォームはPC(Steam)および各種コンシューマ機,そしてiOSで,リリースは2026年第2四半期を予定している。開発は2022年に始まっており,完成すればモノリリス初のタイトルとなる。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/005.jpg) |
ゲームの舞台は,地獄の遊園地「ヘルヘルランド」だ。プレイヤーは地獄に落ちた魂となって,指定された「お供えもの」と呼ばれるアイテムを制限時間以内に集めて脱出を目指す。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/006.jpg) |
コンセプトは,「友人同士や家族が集まったとき,みんなでワイワイ話しながら遊べるゲーム」で,そのため,難しい操作を必要とせずに協力プレイを楽しめるデザインになっており,アクションがあまり得意でなくとも遊べる作品を目指しているという。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/007.jpg) |
特徴となるのは,プレイヤー同士がおんぶするような形でプレイする「重なりアクション」だ。上に乗ったプレイヤーが下のプレイヤーをサポートするシステムで,例えば上のプレイヤーしか取れないアイテムがあったり,上のプレイヤーがジェットパックで進む方向を操作したり,ライトの方向を変えながら道を照らして隠された道を見つけたりする。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/008.jpg) |
モーノ氏もリリス氏も本業がクライアントワーク中心であるため,いつか自分達の「好き」を詰め込んだオリジナル作品を自由に作りたいと考えていたそうだ。
やがて,アート担当のリリス氏がフリーランスになり,ある程度,時間の自由が利くようになったタイミングで,小さい頃から2人が好きだったゲームを作ろうとモノリリスを結成。友達と一緒にワイワイとプレイするタイプのゲームがとくに気に入っていたので,マルチプレイタイトルを作ることに決めた。さらに,「ゲームは好きだけど下手だから一緒にプレイするのをためらう」という意見が意外に多いことに気づき,アクションが苦手でもみんなで楽しめるカジュアルなゲームを作ろうとした。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/009.jpg) |
セッションの最初のテーマは,「ゲーム開発の理想と現実」だ。当初は比較的小規模なゲームを1〜2年で作り,サクッとリリースすることを目標に掲げていた。しかし現実は,開発開始から3年経った今でも開発中となっている。
というのも,最初は60人規模のバトルロワイヤルを作ろうとしていたからだ。たくさんで楽しめるゲームを作ろうとしてスタートしたので,「バトロワ形式がいいんじゃないか」となり,「100人は大変そうだが,60人ぐらいなら行けるんじゃないか」と考えたという。モーノ氏は「今思うと,素人の思いつきほど怖いものはない」と当時を振り返った。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/011.jpg) |
加えて,ゲームの開発経験がないため,どういった仕様でどのように作れば,どのくらい期間がかかるのか,まったく分かっていなかったとのこと。そんな調子で,夢を詰め込みまくった結果,改修や軌道修正に時間を費やし,本来の目標より大幅にリリースが遅れている。
また,インディーゲームでは,1vs.1の対戦ゲームですらなかなかマッチングしないことをあとから知ったそうで,「60人規模のバトロワは無謀な目標だった」とコメントした。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/012.jpg) |
一方,得られた学びもあった。とにかく最初は詰め込みすぎず,やりたいことだけを最小限に絞り,たとえ不出来でも不格好でもいいので,一度は作り切るという経験を踏めばよかったと実感しているそうだ。
1週間でゲームを作るUnity 1weekやゲームジャムなどが頻繁に開催されているので,それらに参加して1本のゲームを作り終える経験をしておけば良かったと話す。また,風呂敷は広げすぎるよりも畳む方がはるかに難しいと日々痛感していることや,こだわり過ぎず,できないものはできないと諦めることも大切だったとも述べた。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/013.jpg) |
得られた教訓としては,以下の3つが挙げられた。
- 小さなゲームのリリース経験を踏み,筋力をつける
- 自分のスキルセットの強みを理解し,生かす方法を考える
- 何を加えるかではなく,何を削るかに注力する
そうやって,まずは作りたいものを小さく作り,そのゲームが面白くなりそうだと思ったら,どんどんボリュームを増やし,仕様を足していく形を取れればベストだったとした。
また,開発の始めには「頭の中にある理想のゲームを作りたい!」と考えていたが,現実はなかなかそういかず,難しかった。その理由は,「理想をどうやってゲームとして実装すればいいか分からない」からだ。初心者であるがゆえに,どのゲームエンジンを選択し,作りたいものをどうやって作ればいいのか? という超初歩的な部分で悩んでいたという。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/014.jpg) |
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/015.jpg) |
結局,ゲームエンジンとして「Unity」を選択したのだが,それは作りたい作品と届けたい形式を中心に検討した結果だった。ゲーム開発の知識がなかった2人にとって,チュートリアルやフォーラムが充実し,かつ日本語で読める点が大きかった。また,ゲームエンジンとしての歴史が比較的長く,ユーザー数も多いため,欲しい機能や実装したいもののほとんどが先人達によってすでに用意されていたこともポイントだった。
加えて,PCだけでなくコンシューマ機やスマートフォン向けにもリリースしようと考えていたため,マルチプラットフォーム展開がやりやすいUnityは魅力的だったとのこと。モーノ氏は,Unityを自分達の「理想と現実のギャップを埋めてくれるツール」と表現した。
開発にあたっては2人でひたすら話し合い,お互いが納得する仕様を作り込んでから一気に実装する方法がベストだろうと考えていた。しかし,実際に作ったものを遊んでみると,まったく面白くないという現実が待っていたという。そこには「予測と現実のギャップ」,そして「環境のギャップ」があったとモーノ氏は指摘した。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/017.jpg) |
予測と現実のギャップは,実際のプレイを確認するまでの時間が長いほど大きくなっていく可能性が高い。つまり,詳細な仕様やゲームデザインを1〜2週間かけて話し合い,そこから数か月かけて作ったプロトタイプが意図したプレイフィールにならなかった場合,その期間が無駄になるうえ,チームの士気も下がってしまうからだ。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/018.jpg) |
そこから得られた教訓として,机上の議論で進めすぎず,とにかく作っては試すサイクルをできるかぎり速く回し,予測と現実とのギャップを早期に認識することが挙げられた。そうすれば軌道修正がしやすくなり,開発効率も向上するという。
モーノ氏は,小規模開発ならではのフットワークの軽さを活かすことが大切だと語った。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/019.jpg) |
環境のギャップについては,開発当初,手元にあるノートPCでテストプレイをしてしまいがちだったことが紹介された。その結果,いざ大画面のテレビやディスプレイでプレイしたときに,UIの文字が小さかったり,キャラクターが視認しづらかったり,エフェクトが派手すぎたりといったことが発生した。サウンドに関しても,ノートPCとテレビなどとでは聞こえ方がまったく異なるといった問題が生じた。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/020.jpg) |
得られた教訓としては,可能なら,ゲームが実際にプレイされるときにもっとも多いであろう環境を再現してプレイすることが挙げられた。「ヘルヘル」なら,マルチプレイの協力型アクションゲームということで,家族全員がテレビの前でソファーに座りプレイするといった環境になるだろう。
これを再現してテストプレイすれば良いというわけだ。
モーノ氏は当初,ゲーム開発に集中すればいいと考えていたが,現実には,ほかにもやることが意外にたくさんあることに気付いた。体感として,ゲーム開発とそれ以外の作業量の比率は,6:4くらいであるという。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/021.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/022.jpg) |
ゲームを開発し,完成してリリースにたどり着けたとしても,プレイヤーに認知されなければ遊んでもらえない。1人でも多くの人に興味を持ってもらうためにも,開発に次いで広報活動に積極的に取り組む必要がある。
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/023.jpg) |
ゲーム開発の時間を少しでも確保することも重要なので,具体的には,SNSの投稿が活発なハッシュタグを活用して効果的なインプレッション数を得,欲している人に情報を届けることを意識しているそうだ。
また,SNSに投稿する時間を1日のタイムスケジュールに組み込み,必要以上に時間を割かないことも大切になる。これには,何かができたら投稿するのではなく,この日のこの時間に必ず投稿するという癖を付ける意味合いもある。イベント出展に関しては,自分達のゲームのターゲットとなりそうな人達が比較的多く来場しそうなところに絞っているという。
続いてのテーマは,「イベントでの理想と現実」だ。
イベントに初出展したときには,試遊した人から「狙ったとおりの反応が返ってくる」と思っていたが,現実は,意図していない部分で盛り上がったり,楽しんでほしい部分がスルーされたり,まったく楽しんでもらえなかったりしたとのこと。さらには自分達自身が見たこともないバグが頻発するなど,散々な結果になった。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/024.jpg) |
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/025.jpg) |
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/026.jpg) |
原因は,開発者自身が自分達の作ったゲームに慣れすぎてしまったことにある。プレイしすぎているため,難度が高めに設定されていたり,必要な説明が省略されたしており,初めてプレイする人が何をすればいいか分からなかったりする事態が多く発生した。
また,イベントに間に合わせるために無理やりまとめた結果,デバッグが足りず,進行不能バグも発生した。
そこから得た学びは,イベントに出展するゲームの難度は,少し下げるくらいがちょうどいいということだ。ゲームジャンルにもよるだろうが,やはりクリアできたほうが達成感を得られるので,良い印象を持たれやすく,覚えてもらいやすいとのこと。
またバグが発生してもあわてず,「おめでとうございます! あなたはこのバグの第1発見者です!」など,ポジティブな言葉に変換して伝えるといい。これは,平謝りしてゲームを再起動する時間が,すごく気まずいからだそうだ。
モーノ氏は,開発者が想定していない部分で楽しんでもらえることも,ゲームデザインを見直すうえで大きなヒントになり,また何より遊んでもらえること自体が開発のモチベーションにつながるため,無理のない範囲でイベントには出展したほうがいいと語っていた。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/027.jpg) |
イベント参加のメリットを実感した2人は,「たくさん出展して,たくさん試遊してもらおう!」と考えた。しかし現実は,出展料や宿泊費,交通費,機材の送料,現地での飲食費など,想定以上の出費に直面した。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/028.jpg) |
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/029.jpg) |
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/030.jpg) |
また,時間もかなりかかる。遠方のイベントでは,移動や準備期間も含め,イベント期間に加えて1週間ほど見込まなければならない。当然,その間の開発は止まり,さらには別途試遊版も作らなければならず,無理なスケジュールを組むこともあったそうだ。
そうした無理がたたり,イベント終了後しばらくは,疲労で開発できなくなったという。
加えて宿泊が必要な場合,シーズンによってホテルの代金が高額になったり,出展に必要な機材が意外に多いことも指摘された。梱包を怠ったことにより,届いたディスプレイの画面が割れていたこともあったという。
モーノ氏は,イベントは会期の前後1週間ほどスケジュールを空け,大まかなコストを計算して,それでもなお参加した方がいいかどうかを検討することなどを挙げた。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/031.jpg) |
3つめのテーマは,「PR・マーケティングでの理想と現実」だ。
当初2人は,ゲームをきちんと作り続けていれば,自然に認知されていくのだろうと考えていた。しかし,Steamでは2024年に約1万8000本のゲームがリリースされており,ただ作っているだけでは,それらの中に埋もれてしまうという現実が待っていた。さらに海外での認知度を上げようとすると,もうどうしていいか分からなかったという。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/032.jpg) |
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/033.jpg) |
そこで2人は,マーベラスが手がけるインキュベーションプログラム「iGi」の第2期生募集に応募することにした。見事採用され,ゲームエンジンやツールの使い方に始まり,パブリッシャとの交渉術,プレゼン資料の作成など,幅広いサポートを受けられたとのこと。
また2024年は,経済産業省が主催するアクセラレーションプログラム「創風」に参加し,より具体的なPR手法やパブリッシャとの交渉などについての支援を受けた。
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/034.jpg) |
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/035.jpg) |
4つめのテーマは,「生活の理想と現実」だった。2人はフリーランスなので,最初はあくまで本業の合間に趣味としてゲーム開発を楽しみつつ,続けていこうと考えていた。しかし現実は,気付けば寝食以外のすべての時間をゲーム開発に注ぐことになっていった。
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/036.jpg) |
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/037.jpg) |
そこから得た教訓は,好きなことを続けるには,生活の確保が大前提だということだ。
リリス氏は,この3年で安定した収入と健康があったからこそ,ゲーム開発ができると実感するようになったと語る。仮に専業でゲーム開発をするつもりなら,外注費や自分自身の人件費を含めて,しっかりとした見積もりを立て,多めの預金を用意しておく必要があるとも話していた。
しかし,そうしたネガティブな側面を含めても,ゲーム開発は楽しいそうだ。
最後のテーマは,「リリースの理想と現実」である。リリース後の理想は,作ったゲームがたくさんの人に遊んでもらえるということだったが,これはおそらくどの開発者も同じだろうとリリス氏は述べる。一方現実は,「ヘルヘル」はまだ開発中であるため,当然ながら不明。リリス氏は,リリースに向けて日々開発を続けていくので,応援してもらえると嬉しいと話した。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/038.jpg) |
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/039.jpg) |
Berserk or Dieの絵作りと
ヴァンサバのponcleとの出会い
「Berserk or Die」は,手のひら全体でキーボードをバンバン叩き,左右から来る敵を倒していくという,体感ゲーム的なアクションが楽しめるタイトルだ。体感ゲームには専用コントローラが必要なものが多く,なかなかインディーゲームでは実現しづらい。そこで柴田氏は,誰もが持っているキーボードで遊べる体感ゲームとして本作を企画したという。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/040.jpg) |
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/041.jpg) |
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/042.jpg) |
セッションの内容は,グラフィックスのクオリティを上げるためのノウハウを紹介するものだ。
しかし冒頭,柴田氏はグラフィックスに関して,必ずしもハイクオリティだから良いわけではなく,個性的であることや,思うままに作ることが良い結果につながることもあると示唆した。
また,作った画像や素材は,必ずゲーム画面でチェックすることが重要だとも述べる。
![画像ギャラリー No.043のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/043.jpg) |
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/044.jpg) |
![画像ギャラリー No.045のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/045.jpg) |
![画像ギャラリー No.046のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/046.jpg) |
柴田氏が手がける作品は,よく「個性的な絵」だと言われるという。理由は,画像の中央部分をほとんど真っ黒に塗っているからだ。以下のスライドのゲーム画面では,地中や背景の丘が黒いし,キャラクターセレクト画面も黒が主体だ。理由は2つあり,その1つは,黒い部分は描く必要がないため,時間を節約できるからだ。
![画像ギャラリー No.047のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/047.jpg) |
![画像ギャラリー No.048のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/048.jpg) |
もう1つの理由がこのセッションの本題で,「画面密度の差を画面内でつける」ことができると柴田氏は語った。以下のスライドに示された星空の画像やキャラクターの髪型のように,密度の差があったほうが自然に見えるのだ。
![画像ギャラリー No.049のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/049.jpg) |
![画像ギャラリー No.050のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/050.jpg) |
「Berserk or Die」のキャラクターは,基本的に1ピクセルの境界線+αしか描いていないとのこと。上記のように黒い部分は描かず,周囲部分だけを描くことにより画面の密度差を出している。大きなキャラクターは少し内側まで描くこともあるが,基本的には1ピクセルの境界線と,光が当たっている部分を少し広めに描くくらいだ。また背景オブジェクトは,1ピクセルの境界線に加え,コントラストを落としてもう少し描き込んでいる。
![画像ギャラリー No.051のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/051.jpg) |
![画像ギャラリー No.052のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/052.jpg) |
![画像ギャラリー No.053のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/053.jpg) |
こうした作られた素材や画像は,最初に柴田氏が述べたとおり,必ずゲーム画面でチェックする。以下のスライドの画像では,大きな面積を占める地面と空は密度を低くし,プレイヤーが注目するところの密度が高くなるようにバランスを取っている。このように,各要素内での密度の差も重要だが,ゲーム画面に配置したときの画面密度の差がより重要になると柴田氏は語る。
![画像ギャラリー No.054のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/054.jpg) |
3Dモデルも,密度の差を付けることでクオリティを高められる。例えば,縁の部分を直線でなく少しデコボコを付けて描くだけでも一気に雰囲気が出る。直線が続くと密度が低くなるため,デコボコを付けることで密度の高い部分を作り出したわけだ。
柴田氏は,直線部分が続くとポリゴンらしさが際立つため,リアルタッチの画像では,こうした工夫がより重要になると述べる。もしポリゴンを増やしたくないなら,テクスチャで傷などを表現してもいいそうだ。
![画像ギャラリー No.055のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/055.jpg) |
![画像ギャラリー No.056のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/056.jpg) |
![画像ギャラリー No.057のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/057.jpg) |
UIは文字やアイコンなどによって密度が高くなる傾向にあるので,やはりゲーム画面で全体のバランスをチェックする必要があるとのこと。
例えば「Berserk or Die」のキャラクターセレクト画面は密度の高い部分があちこちに見られるので,密度の高いところと低いところを意識して作ればクオリティを高められる。
![画像ギャラリー No.058のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/058.jpg) |
![画像ギャラリー No.059のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/059.jpg) |
![画像ギャラリー No.060のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/060.jpg) |
Unityのポストエフェクトである「Vignette」と「Bloom」を使って,緩やかで大きな差を付け,画像のクオリティを高める手法も紹介された。Vignetteを使うと,画面の四隅が暗くなり,雰囲気が出る。またBloomは,明るいものの周囲に光彩を付けるような効果がある。
![画像ギャラリー No.062のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/062.jpg) |
![画像ギャラリー No.063のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/063.jpg) |
両者を併用することで,画面全体に範囲の大きい変化が緩くつき,深みが出る。柴田氏は,画像の密度差と画面全体にうっすらと付ける密度差の両方を合わせることで,より大きな効果が期待できると話していた。
![画像ギャラリー No.064のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/064.jpg) |
話はエフェクトにも及んだ。柴田氏の手がけるゲームのエフェクトは,ほとんど白で,サイズは画面に対して邪魔にならない前提で可能な限り大きくしているという。
![画像ギャラリー No.065のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/065.jpg) |
![画像ギャラリー No.066のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/066.jpg) |
また,エフェクトの表示時間はできるだけ短くしている。せっかく作ったエフェクトだから長く見せたいという気持ちもあるが,柴田氏によれば,思い切って短くすることで,多くの場合,クオリティが上がるとのこと。エフェクトが発生してから最大になるまでの具体的な時間は,柴田氏のゲームだと0.1秒,60fpsのゲームであれば6フレームだ。柴田氏は,エフェクトサイズを大きく,時間を短くすることによって静と動の密度差を出すとした。
![画像ギャラリー No.067のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/067.jpg) |
![画像ギャラリー No.068のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/068.jpg) |
セッション終盤では,「Vampire Survivors」で知られるパブリッシャ,poncleと柴田氏が出会った経緯が紹介された。
そもそも「Berserk or Die」は,「Last Standing」という名称で2024年1月に開発を始め,3〜4か月でパッと作ってセルフパブリッシングするつもりでいた。しかしSteamのストアページを作り,それを自身のXに投稿したところゲームメディアに取り上げられ,多くの人から期待するという反応が得られたという。そこで柴田氏は,もっとしっかり作り込まなければならないと感じた。
![画像ギャラリー No.069のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/069.jpg) |
2024年のゲームイベント「BitSummit Drift」に柴田氏が「Last Standing」を出展したところ,poncleのルカ・ガランテ氏がブースに訪れ,何回かプレイしたあと,翌日また会う約束を交わした。そのときは画像制作のオファーだと考えていたが,ガランテ氏と再会するとパブリッシングの話で,柴田氏は非常に驚いたと話す。
![画像ギャラリー No.070のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/070.jpg) |
具体的な条件も,その場で提示された。柴田氏によれば,どちらかと言えばデベロッパ支援という意味合いが強く,一般的なパブリッシャとは比べものにならないくらいの好条件だったそうだ。
「Berserk or Die」は,柴田氏の書いたプログラムをガランテ氏が編集する形でゲームバランスを調整したという。Steamでリリースされたのは2025年6月で,2週間で1万ドルのセールスを達成するという成功を収めている。
![画像ギャラリー No.071のサムネイル画像 / インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/071.jpg) |
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 Berserk or Die
Berserk or Die - この記事のURL:



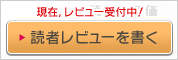






![インディーゲーム開発者の理想と現実が語られたセッションと,絵作りのクオリティアップが紹介されたセッションをレポート[CEDEC 2025]](/games/784/G078414/20250727001/TN/072.jpg)










