イベント
モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]
シリーズの歴史はどのようにして始まったのか? モンハンファンは必見だ。なお,本稿はCEDEC運営事務局からの要請により,講演の一部内容を省略したダイジェスト版となる。諜報は後日掲載予定だ。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/001.jpg) |
個性的な「モンスターハンター」はどのようにして始まったのか,企画書や資料とともに振り返る
●基調講演「モンスターハンターシリーズ」21年の継続と仕掛け 登壇者
・辻本良三氏(カプコン 取締役 専務執行役員 CS第二開発統括「モンスターハンター」シリーズ プロデューサー)
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/002.jpg) |
最初に,本講演は辻本氏が携わったコンシューマ版シリーズを中心にしたものであり,氏はスタッフたちの代表として登壇したと語った。
今やモンハンシリーズのプロデューサーとして知られる辻本氏だが,当初はカプコンのアーケードゲーム部門にプランナーとして配属された。そこで,個性的なキャラクターたちが買い物してパワーアップしつつ戦う「バトルサーキット」や,名作ロボットアニメを彷彿とさせる機体が入り乱れる「超鋼戦紀キカイオー」といった作品に参加し,のちに初代「モンスターハンター」にネットワークプランナーとして携わった。
そんな辻本氏が今でもゲーム開発の際に基礎としているのは,「アーケードゲームは人の目を引きつけてコインを入れてもらい,プレイ後も“もっと遊びたい”という気持ちになってもらわなければならない」という,過去の経験からくる考え方だそうだ。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/004.jpg) |
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/005.jpg) |
「モンスターハンター」
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/006.jpg) |
カプコンがアーケードでヒットを飛ばしてきたメーカーなのはご存じだろうが,「モンスターハンター」はそうしたアーケードゲームを得意とするチームが,自分たちの土俵のマルチプレイとアクションを生かし,コンシューマでオンラインプレイに挑戦しようという企画から始まった。
当時の同社では,コンシューマ×オンラインのかけあわせに挑戦し続けており,スポーツジャンルの「アウトモデリスタ」,既存IPを活かした「バイオハザード アウトブレイク」,そして新規オリジナルアクションとして「モンスターハンター」などを展開してきた。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/007.jpg) |
当の初代「モンスターハンター」については,モンスターの生態をゲーム内で表現し,モンスターから得られた素材で自身を強化していくというコンセプトが,企画当初から固まっていた。
企画書にスケッチされたハンターが身につけている武具のデザインが,製品版でいう「ハンターシリーズ」とほぼ同じであることは有名だが,以下のスライド画像を見ても分かるとおり,企画内容とビジュアルイメージも早い段階から明確になっていたことが分かる。
「モンスターハンター」という,シンプルな字面かつ作品内容を一言で伝えるタイトルも発起時点から一貫していた。企画立案において明確なコンセプトがいかに大事であるかが伝わってくるエピソードだ。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/009.jpg) |
オンラインゲームに挑戦する,といっても2004年時点の通信環境は未発達で,現在の1G回線の1万分の1しか速度が出ない,32kbpsモデムが使われていた。そのため「モンスターハンター」では,アクションに大きな影響を及ぼす,プレイヤーと大型モンスターの動きだけを同期し,小型モンスターはあえて同期しないという取捨選択が行われた。
当時のオンラインプレイの経験者で「仲間がなにもいない空間に,突然武器を振り出す光景」を目撃した人も多いかと思うが,これは当時の通信環境を鑑みての措置だったわけだ。
同作はグローバルで45万本を売り上げ,プレイヤーが仲間を誘って人口が増えるという,モンハンらしい構図が見られたという。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/011.jpg) |
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/012.jpg) |
「モンスターハンターG」
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/013.jpg) |
ガッツやグレートといった勢いのある単語がGで始まることから,続編のタイトル名は「モンスターハンターG」に決定した。
同作は,日本のプレイヤーが「双剣」に初めて触れたタイトルだが,双剣自体は先に発売された海外版「モンスターハンター」から逆輸入されたものである。海外では手数の多い武器が好まれるということから制作されたのが双剣という武器種であり,これだけ取っても,モンハンシリーズが早期から海外展開を意識していたことが分かる。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/014.jpg) |
「モンスターハンターポータブル」
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/015.jpg) |
携帯ゲーム機のPSP(PlayStation Portable)で登場した,初の携帯型モンハンが「モンスターハンターポータブル」である。
従来のタイトルでは,ハンターの攻撃時にゲームパッドの右スティックが用いられていた。だが,PSPでは再現できない操作とあり,攻撃はボタン操作に変更された。以降のモンハンでも(一部をのぞき)ボタン攻撃が標準になったことから,さまざまな意味で重要な1作だ。
この点,個人的にはかなり思いきった変更であると感じられた。右スティックで攻撃させるのも,おそらくは身体性のようなものを表現する意図で,明確なコンセプトがあったかと思われるが,ここで柔軟にボタン操作を選んだために現在の発展がある,といっても過言ではないだろう。
当時はゲームセンターの数も減り,多人数でゲームを楽しむ機会も減少していたことから,若年層がターゲットとなっていた。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/016.jpg) |
「モンスターハンター2」
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/017.jpg) |
再び据え置き機に戻った「モンスターハンター2」の制作コンセプトは,「初代作でやれなかったことを,すべてやろう」だ。
シリーズとしては新たな武器種として「狩猟笛」「弓」「太刀」「ガンランス」が初登場した。なかでも狩猟笛の製作には難航し,開発終盤まで仕様が確定しなかったというのは有名なエピソードだ。
同作はオンライン要素も強化され,“時間経過で昼夜や季節が変わり,プレイに影響を及ぼす”システムが採用された。
個人的には,こうした環境が移ろうシステムは「モンスターハンターワイルズ」にも受け継がれていると感じる。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/018.jpg) |
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/019.jpg) |
「モンスターハンターポータブル 2nd」
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/020.jpg) |
PSPでの2作目「モンスターハンターポータブル 2nd」は,若い世代を取り込むため,週刊少年誌を意識したロゴ作りなどに取り組み,国内出荷本数が初の100万本を突破した。同時期,オフラインイベント「モンスターハンターフェスタ」がスタートするなど,印象深い出来事も多い。
ちなみにモンスターハンターフェスタは,ハンター同士が出会える機会を作りたい,モンハンのテーマパークを作りたいという思いから,造形物やフォトスポットが用意された。名物となったタイムアタック大会も,すごいプレイを見せてくれるヒーローショー的な意図だったという。
同作は携帯機で遊べたため,会場に行くまでの電車や待ち時間の行列といった場所でもプレイされ,ブーム感の醸成に寄与した。
なお,シリーズに激震を走らせた次回作「モンスターハンターポータブル 2nd G」で,強敵「ラージャン」が2頭出現する配信クエストは,開発者がプレイヤーの声を聞いたのをきっかけに制作したそうだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/021.jpg) |
ここまでで,セッション前半のレポートは終える。
あらためて注記するが,本稿はCEDEC運営事務局からの要請により,講演の一部内容を省略したダイジェスト版となる。
以降,モンハンブームを生み出した「モンスターハンターポータブル 2nd G」とキャッチコピー「一狩り行こうぜ」の秘密。初の水中戦が導入された「モンスターハンター3」。こちらも社会現象となった「モンスターハンターポータブル 3rd」。当初は違うタイトルだった「モンスターハンター3G」。立体的なフィールドを実現した「モンスターハンター4」に,AAAを志向した「モンスターハンター:ワールド」,和の世界観を押し出した「モンスターハンターライズ」。
そして近作「モンスターハンターワイルズ」など,そうそうたるタイトルの開発秘話については,続く詳報を楽しみにしてほしい。
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ
- 関連タイトル:
 モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ
- 関連タイトル:
 モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ
- この記事のURL:
キーワード
- PC:モンスターハンターワイルズ
- PC
- アクション
- CERO C:15歳以上対象
- カプコン
- ファンタジー
- プレイ人数:1〜4人
- PS5:モンスターハンターワイルズ
- PS5
- Xbox Series X|S:モンスターハンターワイルズ
- Xbox Series X|S
- イベント
- ライター:箭本進一
- CEDEC 2025
(C)CAPCOM
(C)CAPCOM
(C)CAPCOM



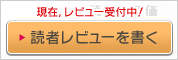




![モンハンはどのようにして始まったのか,企画書や資料と共に振り返る。「モンスターハンター」シリーズ21年の継続と仕掛け[CEDEC 2025]](/games/759/G075952/20250724064/TN/022.jpg)










