イベント
ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/001.jpg) |
「Cluster」公式サイト
本講演は,ゲームにおける従来のチュートリアルとは異なる「好奇心主導型チュートリアル」を紹介するものだ。従来のチュートリアルとは,限られた箱庭の中で特定の機能を制限し,順番に解除していくことで,プレイヤーにゲーム機能を学ばせる,「ゲーム都合」のチュートリアルだ。
これに対し,柳川氏らが提案する好奇心主導型チュートリアルとは,最初から自由に移動できる状況下で,プレイヤーが未知の要素にぶつかるたびにAIエージェントがその状況に応じた説明をしてくれるという,「プレイヤー主導」のチュートリアルだ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/002.jpg) |
柳川氏によれば,プレイヤーとAIエージェントで実験してみたところ,クラスターのワールド探索時間が最大約500%,滞在時間が最大約170%増加し,AIエージェントの効果で,プレイヤーがゲーム空間によりのめり込むようになったという。
実験に使われたAIエージェントには,LLM(大規模言語モデル)が使用されており,選択肢に縛られない自由な会話や,自由度の高い行動が可能になっている。また,そもそも会話をしてもらう必要があるため,つい話しかけたくなるように,キャラクターデザインも考慮されている。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/004.jpg) |
続いて,そんなAIエージェントが具体的にどのような設計で動いているのかが解説された。
AIエージェントは,プレイヤーがワールドに入場したり,エージェントに質問したりといったイベントの発生を受けたLLMが,現在の状態を解釈し,行動内容の決定,合成音声による応答を行う。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/005.jpg) |
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/006.jpg) |
LLMには,「Chat GPT 4o Realtime」が使われている。採用の理由としては,音声をテキストを介さずそのまま受け取れるため,声に込められた感情や息遣いなども処理できること。また,リアルタイムの会話に特化しており,レスポンスが高速であることや,音声合成機能の質が高いことが挙げられた。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/007.jpg) |
さらに,LLMに会話以外の機能を持たせる「Function Calling」を合わせることで,プレイヤーに挨拶を行ったり,決められた座標のリストへ移動したり,プレイヤーの要望に応えてポーズを決めたりなど,さまざまな行動を可能としている。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/008.jpg) |
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/009.jpg) |
なお,LLMの行動を設定する際,誤解の余地がない関数定義をしておかないと,AIエージェントがプレイヤーに移動先のIDを尋ねるなど,世界観を壊す行動をとってしまう可能性がある。そのため,AIの特性に配慮した「LLMファーストな関数定義」が必要になる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/010.jpg) |
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/011.jpg) |
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/012.jpg) |
AIエージェントを利用するうえで避けられない問題が,意図的に生成AIに誤作動を起こさせるような指示を出す「プロンプトインジェクション」攻撃だ。現時点で,完全に食い止めることはほぼ不可能なので,早期検出,被害軽減にリソースを集中したほうが良いという。
具体的な例として,会話の履歴を別のLLMに監視させることで,プロンプトインジェクションの形跡がないか,AIエージェントがおかしな行動をとっていないかを検出していることが挙げられた。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/013.jpg) |
続いて,プレイヤーが実際に目にすることになる,AIエージェントのキャラクターデザインの解説が行われた。なお,説明を行う予定だった小倉氏が体調不良で欠席したため,引き続き柳川氏が解説を務めた。
メタバース空間には人間のプレイヤーが多数存在するため,まず第一に,プレイヤーと明確に区別できる要素が必要だ。そこで,プレイヤーより少し小さい妖精風の見た目にし,そのうえで,話しかけやすく,かつ話しかけた時に知性のある応答が期待できそうなビジュアルを求めたという。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/014.jpg) |
ただし,AIエージェントはどうしてもおかしな発言をしてしまうことがあるため,あまり知的すぎるデザインは適していない。多少変な発言をしても,笑って許してもらえるようなビジュアルにすることで,プレイヤーの期待値を調整しているとのこと。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/015.jpg) |
また,ナビキャラには対話性だけでなく,愛着の湧く「パーソナリティ」が必要だと,柳川氏は語る。というのも,ゲームには,中にスタッフが入ってメタバース空間を案内する「ロビースタッフ」というキャラクターも存在し,その対話性だけでなく,スタッフ個々のパーソナリティが愛されていたからだ。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/016.jpg) |
そこで今回のAIエージェントには「確実に案内をしてくれそう」「親切そう」ということを重視しつつ,好奇心旺盛でプレイヤーのことを何でも知りたがる人格を設定。「そのキャラクター」らしい一面を与えることなどで,親しみやすい存在を作り上げたそうだ。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/017.jpg) |
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/018.jpg) |
最後に廣井氏から,用意したAIエージェントで実際に実験を行った結果と,どういった効果が得られたのか,そして今後の展望が紹介された。
今回の実験は,デスクトップでキャラクターを操作するPCクライアント環境のプレイヤー99人,VRHMD環境のプレイヤー94人の計193人を対象に,カフェと博物館という2つの場所を舞台に,A群(AIエージェントとの自由対話によるガイド),B群(AIエージェントによる固定ルートでのガイド),C群(ガイドなし)の3つの方式にランダムで割り当てて行われた。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/019.jpg) |
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/020.jpg) |
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/021.jpg) |
実験の結果,A群がB・C群に比べて1.5〜1.7倍の滞在時間になったほか,探索時間にいたっては3〜5倍にも向上した。さらに探索のヒートマップでは,A群が複数経路による空間探索と,主要スポットでの長時間滞在を行っているという結果が得られた。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/022.jpg) |
![画像ギャラリー No.023のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/023.jpg) |
また,GQSを用いたAIエージェントの印象評価としては,PCクライアント環境では「有生性(生きてる感)」「好感度」においてA群がB群よりも高く評価していたが,「擬人感」「知性」「安心感」においてはそれほど差がなかったという。これは,回答の遅延が擬人性を,虚偽または誤解を招くような情報を提供するハルシネーションが知性,安心感を損なわせたと推察されている。
![画像ギャラリー No.024のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/024.jpg) |
一方,VRHMD環境のプレイヤーでは,カフェにおける「疑似性」「知性」に有意差が出た。これについては,社交環境では対話が意識されるため,共存感が強化されたためだとしている。
なお,「好感度」において有意差が出なかったことについては,等身大で接するVRHMDでは,人間同士が行う「非言語コミュニケーション」について,まだ改良の余地があるのではないかと廣井氏は語った。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/025.jpg) |
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/026.jpg) |
講演後の質疑応答では,より人間らしさを出すために,応答までの空白時間に「えーっと」のような“考える様子”を混ぜるといった案や,今回のような妖精以外に,さまざまなアバターで研究を進めていくといった今後の展望が紹介された。
また,いわゆるゲームのチュートリアルで求められるシステム指導などは,まだ未実装のため今後の課題としつつ,現時点でもAIエージェントにプレイヤーが操作法を質問し,そのレスポンスを受けることで自ら模索するといった場面が見られ,操作方法を直接教える以外に何か手段があるのではないかという,新しいアイデアの種も飛び出していた。
![画像ギャラリー No.027のサムネイル画像 / ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/027.jpg) |
AIを活用したさまざまなサービスは発展途上だが,それゆえに,今後どのような進化を遂げるのか,大きな期待を感じさせるセッションだった。
ゲーム内でキャラクターがチュートリアルを行う場面は多くのタイトルですでに見られるので,AIを活用した手法が実用レベルに達したら,キャラクターが確立しているゲームキャラクターとの相性は良さそうだ。AI自体も今後大きく進歩するはずなので,これからの展開に期待したい。
「CEDEC 2025」公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」関連記事一覧
- 関連タイトル:
 Cluster
Cluster
- この記事のURL:
(C) 2017 Cluster, Inc.



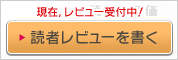






![ゲーム主導ではなく,プレイヤーの好奇心が導くチュートリアル。「メタバースが描き出すAIエージェントによる新しいゲームの姿」聴講レポート[CEDEC 2025]](/games/658/G065855/20250726003/TN/028.jpg)










