イベント
「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/001.jpg) |
インディーゲームとしては異例のヒットとなった「都市伝説解体センター」(PC / PS5 / Nintendo Switch)を手がけた墓場文庫と集英社ゲームズが語った,小規模開発における「制限」と「割り切り」の活かし方をレポートする。
※CEDEC運営事務局からの要請により,このレポートは講演の一部内容を省略したダイジェスト版となっている
「都市伝説解体センター」公式サイト
エターナルな開発にならないための「3つの掟」
セッションの冒頭,「都市伝説解体センター」のセールス本数などが説明された。リリースから3か月で30万本を突破し,主題歌「奇々解体」のYouTube動画は200万PVを記録。さらに少女漫画誌「りぼん」の連載が決まるなど,多方面で注目を集めている。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/002.jpg) |
セッションは,墓場文庫からプログラマーのモチキン氏,シナリオ/キャラデザインのきっきゃわー氏,グラフィック/デザインのハフハフ・おでーん氏,BGM/SEのあだP氏,そしてパブリッシャである集英社ゲームズのプロデューサー林 真理氏が加わり,5名によって行われた。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/003.jpg) |
墓場文庫のプログラマーであるモチキン氏は,今回の講演で主に3点について話すと説明した。
1. “エターならぬ開発”という合言葉
2. 3つのシンプルな開発ルール
3. 集英社ゲームズとの二人三脚
墓場文庫の誕生は,モチキン氏とハフハフ・おでーん氏の共同制作したゲームが「エターナル化」(完成しない状態)した経験にさかのぼる。しかし,その後「和階堂真の事件簿」がGoogle Indie Game Festivalで集英社GCC賞を受賞したことをきっかけに,集英社ゲームズとの出会いが生まれた。
そして2022年,「都市伝説解体センター」の開発がスタートした。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/004.jpg) |
開発が迷宮入りすることなく作品を完成させるため,墓場文庫は「ユルい3つの掟」を決めたという。
まずは「『制限』した中で遊ぶ」。Unityのような開発環境は基本的に「何でもできる」が,モチキン氏いわく,それこそがゲームをエターナル化させる「罠」だという。あらかじめ「枠」を明確に定め,その範囲の中で遊びを考えていくことで,開発コストを削減しつつ,むしろアイデアを増やすことにつながったと語る。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/006.jpg) |
次に「『期限』順守か捨てるか」。スケジュールは「飾り」ではなく,“刃”のように容赦のないものととらえるという。「面白さ」よりも「日付(コスト)」を優先し,期限に間に合わなそうならその要素は捨てるという割り切りを重要視した。なぜなら,「完成しなかったゲームは誰も遊ぶことができない」からだ。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/007.jpg) |
そして「とりあえず一旦まぁええんちゃう」進行だ。迷って手が止まってしまうくらいなら,「とりあえず」実装して,プレイ感から判断していくということである。組みあがったものを見れば,自然と改善案が湧いてくることも多い。「まぁええんちゃう」という姿勢で,何はともあれ前に進むことが大切であり,意外にも,このことで各自の責任感が失われることもなかったという。
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/008.jpg) |
掟は各自にどう適用されたか
これらの掟は,どのように適用されていったのだろうか。まずはグラフィック部門を担当するハフハフ・おでーん氏の場合から見ていこう。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/009.jpg) |
1つ目の掟「1.『制限』した中で遊ぶ」は,まさにドット絵そのものが体現している。色数や解像度を制限することが作品そのものの特徴となり,開発期間の圧縮にもつながった。その分,場面数やアニメーション演出,キャラクターの表情差分の物量を増やすことができたという。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/010.jpg) |
本作のグラフィックス解像度は横240×縦135ピクセル,色数も概ね9色しか使っていない(※場面によってほかの色やグラデーション,ぼかしも使用)。おでーん氏は,解像度が低いことで表現力は制限されるものの,ビジュアルとしての「強さ」は増すという持論を語った。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/011.jpg) |
2つ目の掟「2.『期限』順守か捨てるか」は,主にシナリオ担当のきっきゃわー氏との分業によって実現した。ハフハフ・おでーん氏がシナリオの構成部分を進めている間に,きっきゃわー氏がキャラクターデザインを進めるなど,得意分野に応じて作業を切り替え,並行して進めることで効率化を図った。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/012.jpg) |
また,できないことは外部に依頼する割り切りも重要だ。できないことに時間を浪費しては期限を守れなくなってしまう。さらに,質か量かの選択を迫られた際は「量を取るべきだ」と語る。こだわり100%の絵1枚よりも,50%の2枚,なんなら33%の3枚の方が喜ばれることは往々にしてあるという。
3つ目の掟「3.『まぁええんちゃう』進行」については,クオリティが重要ではないということではなく,「こだわりすぎてしまう」ことへの戒めだと説明する。自分の感性よりも周囲の反応を信用するほうが最適解と無理にでも思い(本当は少し傷つくこともあるそうだ),「あとで描き直せばいい」と思えばこそ,どんどん次に進むことができる。実際,シナリオ変更によって場面全体の絵を描き直すことも珍しいことではない。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/013.jpg) |
実は「都市伝説解体センター」のロゴとキービジュアルも,「まぁええんちゃう」進行で生まれたものである。仮に作ったつもりのものが,結局そのまま作品の顔になったそうだ。このように,とりあえずで作ったものが悪くなければ「作品がそちらにフィットしていく」ということも起こる。
続いて,キャラクター設定・デザイン,シナリオ・演出を担当したきっきゃわー氏のケースが語られた。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/014.jpg) |
「1.『制限』した中で遊ぶ」は,本作のシナリオ制作の根幹にも関わっている。本作は制作の初期から「文章を読むのが苦手な人にもクリアしてほしい」という目標を設定している。描写というものはこだわり出せばキリがないが,ストーリーライン以外はノイズともなり,プレイヤーが物語を読みきるハードルを上げてしまう。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/015.jpg) |
また,メインの3人以外のキャラクターは,意外にも背景設定が決まっていない部分が多いという。それ以外は特徴的なクセやワードを配置して背景を「匂わせる」程度に留めることで,設定にかける時間を大幅に短縮した。そして,できあがった1話から6話の流れを見たあと,6話の物足りなかった部分を埋めるように,5話までの隙間に伏線を足したり,6話の納得感を高める要素を加えていった。
「2.『期限』順守か捨てるか」は,ハフハフ・おでーん氏の話とも重なるが,得意なことを分業することでクオリティとスピードを上げていく考え方である。そして,孤軍奮闘していると感じるときほど,実は危険な状態に陥っているため,周囲とフィードバックし合える環境を作ることが大切だと語られた。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/016.jpg) |
具体的には,集英社ゲームズやroom6からシナリオ執筆経験のある方を紹介してもらい,ひたすら「壁打ち」の相手になってもらいながら,修正・加筆の同時作業を進めたという。
「3.『まぁええんちゃう』進行」については,シナリオ執筆は最初から最後まで「まぁええんちゃう」の繰り返しだという。まずは一旦ストーリーを埋めていき,肉付けはそのあとに行う。完璧に出力することよりも,とにかく前に進んでいくことが重要だ。細かいところは読み返すときに調整していく。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/017.jpg) |
また,きっきゃわー氏は大切なこととして「諦めを余白になれと願う」ことを挙げた。氏は細かく書けないと不安になるそうだが,物語の骨組みをハフハフ・おでーん氏に託したように,細い部分の肉付けはプレイヤーに委ねてしまってもいいと考えるようにしたという。
プログラムを担当したモチキン氏や,BGM・サウンド周りを担当したあだP氏の話も続いたが,それらは後日掲載の詳報に譲ることにして,最後に集英社ゲームズのプロデューサー林 真理氏の話で本稿を締めくくろう。
チームの「解体」を防ぐにはコンセプトの決め方が鍵
インディーゲームのデベロッパとパブリッシャの間には,対立構造が生まれがちだが,これを防ぐ方法として林氏は「一緒にコンセプトを決めて,それを守り抜くこと」を挙げた。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/018.jpg) |
ゲームコンセプトであれば「どのようにお客さんに楽しんでもらうのか」,商品コンセプトであれば「どのようなお客さんに手に取ってもらいたいか」が重要となる。「都市伝説解体センター」の場合,墓場文庫側から「このゲームはミステリ作品なので,結末まで読んでほしい」「普段ゲームをしない人にも最後までクリアしてほしい」という言葉が出たため,そこを本作のゲームコンセプトとして定めたという。
このゲームコンセプトがあればこそ,どんな形のゲームを作るべきか,その枠組みを判断できるようになり,これが今回のセッションで語られた「制限」の大元の部分になっていると説明した。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/019.jpg) |
商品コンセプトに関してもプロセスは同じだ。まず墓場文庫側の声をしっかりリサーチし,「都市伝説,ミステリーに興味を持ってもらうこと」を柱にした。
また,「ピクセルアートをカッコいい,かわいいと思ってもらうこと」を次点の基準にすると同時に,「都市伝説」という言葉からホラーゲームと勘違いされてほしくないという意向を受けて,この点はかなり力を入れて,さまざまな場所で伝えるようにしたという。そこからタイトルが導かれたり,ピクセルアートをとにかく数多く露出したり,「ミステリーではあるが,怖い作品ではない」といったメッセージをSNS等を通して伝え続けていった。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/020.jpg) |
デベロッパと協業するコツとして,林氏は「お互いによく考えてコンセプトを決めれば,目標やゴールがずれにくくなる。お客さんを喜ばせるための制限はチームを1つにする」と語った。こうしてゲーム会社の所属経験がないメンバーで構成された墓場文庫による,異例のスマッシュヒットが誕生したのである。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / 「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/021.jpg) |
CEDEC 公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- 関連タイトル:
 都市伝説解体センター
都市伝説解体センター
- この記事のURL:
キーワード
- PC:都市伝説解体センター
- PC
- アドベンチャー
- CERO B:12歳以上対象
- プレイ人数:1人
- ホラー/オカルト
- 集英社ゲームズ
- 墓場文庫
- PS5:都市伝説解体センター
- PS5
- Nintendo Switch:都市伝説解体センター
- Nintendo Switch
- イベント
- ライター:高橋祐介
- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー
- CEDEC 2025
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES



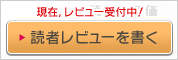





![「制限こそが武器になる『都市伝説解体センター』の創り方」聴講レポート。開発・パブリッシャが目標をひとつにする方法とは[CEDEC 2025]](/games/649/G064901/20250723051/TN/022.jpg)









