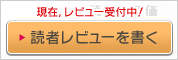イベント
「Dead Space」などを手がけたGlen Schofield氏が語る,アイデア創出の手法と業界再生への提言――gamescom asia基調講演レポート
「アイデアこそがゲーム業界の燃料である」と語る氏は,自身が長年のキャリアで培ってきたアイデア創出の手法を惜しみなく公開するとともに,困難な時期を迎えているゲーム業界の再生に向けた具体的な提言を行った。
 |
講演は当初「10の手法」として告知されていたが,氏は冒頭で「告知では10個となっていたが実際は9個だ。これはイベント主催者のせいではなく,AIのせいにしておこう」とユーモアを交えて切り出す。そして約1時間にわたり,「コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア」での高度なジャンプメカニクスの誕生秘話から,「Dead Space」における宗教要素の着想に至るまで,実際のゲーム開発で使われた具体的なエピソードを交えながら,クリエイティブなアイデアがどのように生まれ,形になっていくのかを語った。
ゲーム業界を支える「アイデア」の力
Schofield氏はまず,会場に集まった開発者,学生,ファンに向けて,ゲーム業界が困難な時期にあることを率直に認めた。しかし同時に,「それでもあなたたちがここに来たということは,ゲーム業界を,ゲームを,そして自分自身への投資を大切に思っているからだ」と呼びかける。
 |
「アイデアこそがゲーム業界の燃料である」――氏が強調するのは,アイデアの持つ圧倒的な力だ。ゲーム業界は今や,映画産業と音楽産業を合わせたものをも凌駕する規模にまで成長した。かつては映画のライセンスを買ってゲーム化していた業界が,今では映画業界がゲームのライセンスを購入して映画を作る時代になった。この逆転劇を可能にしたのは,ほかならぬ「アイデア」だと氏は語る。
ゲームディレクターとして,Schofield氏は常にアイデアを必要としてきた。ゲーム開発においては,大きなものから小さなものまで,無数のアイデアが求められる。そしてそれらを締め切りとともにチームで実現していくために,氏は独自のリストを作り上げ,長年にわたって使ってきた。今回の講演では,そのリストを初めて公開するという。
ただし,氏は2つの重要なルールを示した。1つ目は「アイデアはどこからでも生まれる」ということ。そして2つ目は「ゲームには最高のアイデアのみを採用すべきである」ということだ。
これは,もし自分以外の誰かがより良いアイデアを持っていた場合,エゴを捨ててそのアイデアを使うことがファンとチームにとって最善であることを意味する。
9つのアイデア創出法
1. 個人的な発想時間(Private Ideation Time)
 |
Schofield氏にとって,絵画やドローイングといったアート活動を通じて,頭を「思考モード」に切り替える時間は極めて重要だ。誰もが自分なりの思考方法を持っているはずだが,氏の場合はアートを通じて脳をアイデア創出のモードに入れるという。
「コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア」の開発時,氏は自分自身に問いかけた。「次の『コール オブ デューティ』で何をしたいか?」
その答えは即座に「高くジャンプしたい」と浮かんだ。アイデア自体はシンプルだったが,それをチーム全体に理解してもらい,実装に至るまでには困難が伴った。しかし最終的に,このハイジャンプのメカニクスは「アドバンスド・ウォーフェア」を特徴づける重要な要素となり,その後の作品でも使われることになった。
2. 個人的な経験(Personal Experience)
 |
聞いた話,旅行の経験,人生で出会ったもの――こうした豊かな個人的経験は,アイデアの宝庫だと氏は語る。
「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3」では,Schofield氏は自身の人生を変えた映画監督,ジョージ・ルーカス氏へのオマージュを捧げることにした。
ゲームの冒頭,潜水艦が海中から浮上するシーンがある。一見すると何でもないシーンだが,氏にとってはスター・ウォーズへの敬意を表す重要な演出だったという。こうした小さなアイデアが,シーン全体をより意味深いものにしていく。
3. リサーチ(Research)
 |
「これは非常に重要だ」――氏が力を込めて語るのがリサーチだ。「コール オブ デューティ ワールドウォーII」のために,氏は3年間にわたってリサーチを行った。今はインターネットがあり,あらゆる情報にアクセスできる。ゲームに登場させる戦車やトラック,ジープなどを徹底的に調査し,その弱点や長所,ゲームプレイに使える要素を探す。
もっとも印象的な例は「Dead Space」における宗教要素の追加だ。開発が8〜10か月進んだ頃,氏は何かが足りないと感じた。考えた末,「宗教が必要だ」という結論に至る。しかし信仰に基づく宗教をどうやって作るのか? この問いに答えるまでに,6〜8週間を要した。
ある日,氏は恐竜を絶滅させた小惑星に関する記事を読んでいた。その小惑星が恐竜の時代を終わらせ,氷河期をもたらし,人類の誕生につながったという内容だ。そこで氏は自問した。「もし,それがただの岩ではなく,マーカーだったら? オベリスクだったら?」
この発想から,科学者たちがマーカーを地中から掘り出し,それが人類を創造したものだと信じる者と,疑う者に分かれるという設定が生まれた。ここに信仰が生まれる。このアイデアは「Dead Space」のゲーム性を大きく変える要素となった。氏はこれを「アート・マス(芸術的な数学)」と呼び,複雑な思考プロセスを経て到達したアイデアだと説明した。
4. ブレインストーミング(Brainstorming)
 |
チームワークの基本であるブレインストーミングについて,氏は重要な指摘をした。会議のファシリテーターは事前にリサーチを行い,参加者に準備期間を与えるべきだということだ。全員が何の準備もなく集まり,「今日は何をするんだっけ?」という状態では,最初の15分が無駄になってしまう。
Striking Distance Studiosで「The Callisto Protocol」を開発していた初期の写真を見せながら,氏は通常自分が前に立って議論をリードするが,ときにはチームメンバーに主導権を譲ることもあると語った。ブレインストーミングこそが,異なるアイデアを集めるチームワークの要であるからだ。
5. 場所への訪問(Visiting Locations)
 |
リサーチだけでは得られない「フィーリング」を得るために,現実のロケーションを訪れることの重要性を氏は強調する。もちろん,月を舞台にしたゲームを作る場合は無理だが,それに似た場所を見つけることはできる。
「コール オブ デューティ ワールドウォーII」の開発時,Schofield氏はすべての設計を終えていたが,実際にその場所に行く必要性を感じた。そこで米国立第二次世界大戦博物館の学芸員を雇い,8〜9日間かけてフランス,ベルギー,ドイツを巡ったという。
戦争後に残された物資や遺物を実際に見て,テクスチャの写真を撮影した。「森を舞台にするなら実際に森に行き,これらのものを研究すれば,ゲームに追加できる要素が見えてくる」と氏は語る。
6. 専門家との協働(Working with Experts)
 |
専門家に電話をかけてアイデアや修正,検証を求めることを,氏は躊躇なく行う。そして彼らは喜んで協力してくれるという。
「コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア」でゴールデンゲートブリッジを爆破するシーンを作る際,氏はどうやって破壊すべきか分からなかった。プロデューサーが退職した橋梁検査官を見つけてくれ,氏は彼に電話をかけた。
専門家の助言は明確だった。「橋脚ではなく,ケーブルを破壊すべきだ」。この助言により,Schofield氏が最も好きなシーンの1つが誕生した。実際のゲームプレイ映像では,ケーブルが切断され,巨大な橋が崩落していく様子が劇的に描かれている。
7. ヘッドラインからの着想(Ripped from the Headlines)
 |
ニュース,政治,国際情勢,ビジネスに常に目を光らせておくことの重要性を氏は説く。氏自身,BBCをよく見るという。アメリカでは報道されない情報が得られるからだ。
「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3」のシエラレオネのレベルを開発中,氏は砂嵐が同盟軍の戦闘を2日間も遅らせたという記事を目にした。「砂嵐が軍隊を2日間も止めた? これはゲームに入れなければ」と考えた氏は,砂嵐の要素をレベルに組み込んだ。
プレイヤーは最初,通常の状態でレベルをプレイする。そしてのちに同じ場所に砂嵐の中で戻ることになるのだ。同じマップでありながら,ゲームプレイは完全に変わる。開発者の視点から見れば,作ったものを再利用できるという利点もあった。
8. 音楽と音響(Music and Sound)
 |
Schofield氏は,20年前にサウンドの重要性を認識したという。会話,音楽,エンジン音,風など,常に耳を開いておく必要があると説く。
「Dead Space」の新しいトレイラー用の曲を2週間ほど探していたある日,氏が帰宅すると3歳の娘が「Twinkle, Twinkle, Little Star(きらきら星)」を歌っていた。「これだ」と直感した氏は,この童謡を不気味なトーンでアレンジし,ホラートレイラーに使用した。
もう1つの例は,音がメカニクスそのものになったケースだ。氏とオーディオディレクターのDon Becka氏は,「Dead Space」全体を通じて緊密に協力していた。
ある日,Becka氏が「電車で窓を開けて通過したら,ひどい音がした」と報告してきた。Schofield氏はすぐに「録音しろ」と指示し,翌日Becka氏は窓から手を出して録音してきた。
この音は,ゲーム内で真空状態から脱出する際の音として使用された。テスターたちはこの音に非常に怖がり,効果的なメカニクスとなった。氏はその後もほかのゲームで,小さなエリアで同様の手法を数回使用しているそうだ。
9. AIの活用(Using AI)
 |
Schofield氏が「新しい手法」として挙げたのがAIだ。氏はChatGPTを2年以上,Midjourneyなども含めてAIツールを使い続けている。
重要なのは,「AIは我々の代わりではなく,我々をより速く,より良く,より効率的にするためのツールである」という認識だ。氏はChatGPTをブレインストーミングの相手として使用し,通常の質問ではなく,ストーリーの半分を与えて「どこに欠陥があるか」を尋ねたり,クレイジーな質問を投げかけたりしている。そうした会話それぞれに名前を付け,あとで参照できるようにしているという。
Midjourneyについては,シーンのアイデアを迅速に視覚化するために使用している。例えば,翌日アートディレクターに提示するシーンがあるとして,それを雪のなかにするのか,夜にするのか決めかねている場合,複数のバリエーションを作成して比較する。完成したコンセプトアートではないが,これによりアートディレクターは,チームを動かし始められる。
「Glen,あなたはコンセプトアーティストの仕事を奪っているのでは?」という批判に対し,氏は明確に答える。「ゲームを作りながらコンセプトアートまで自分でやると思うのか? そんな時間はない」。AIを使ってボタンを押せば良いゲームができるという考えは間違いだと氏は強調する。
AIはディレクターだけでなく,アーティスト,ライター,エンジニア,マーケティング,経営陣,すべての人のためにある。「使ってみてほしい,実験してほしい,成長してほしい」と氏は呼びかける。この2年間でAIがどれほど進歩したかを見てきた氏は,常に最新情報を追い続けているという。
AIに質問を投げかけ,新しい方向に押し進めることで,ときには予想外のアイデアが生まれる。シーンのアイデアがあるとき,「全体を炎に包んだらどうなるか?」といったクレイジーなことを試してみる。そして時折,「この炎のアイデアは良い」という発見があるそうだ。
しかし,氏は最後に重要な点を付け加えた。「最終的に,創造性の火花はまだ我々から生まれる」。AIはツールであり,より速く,より大きな夢を実現するための手段なのだ。
 |
ゲーム業界再生への3つの提言
アイデア創出の手法を紹介したあと,Schofield氏はトーンを変えて,ゲーム業界の現状について語り始めた。「これは私の個人的な意見である」と前置きしつつ,氏は率直に述べた。
「ゲーム業界は今,壊れている。打ちのめされ,傷ついている。開発者たちは過去2年間,厳しい状況に耐え続けてきた。我々は業界を元に戻す必要がある。ネガティブな状況から抜け出さなければならない」
そして氏は,業界を再生させるための3つの具体的な提言を行った。
1. AIトレーニングの即座の開始
経営陣,オーナー,すべての責任者に対し,氏は「すぐにでも従業員へのAIトレーニングを開始すべきだ」と訴える。そして重要なのは,競争相手を気にせず,業界全体で協力すべきだということだ。
「EAだろうと,Activisionだろうと関係ない。少なくともトレーニングにおいては協力し,人材を育成すべきだ」――氏はそう力説する。AIは次の大きな技術的飛躍であり,PC,インターネット,携帯電話と同様に新たな波を創出する。いまAIを学び,実験する者が,業界にとって不可欠な存在になるのだ。
2. 投資の再開と適切な人材配置
「さあ,投資家の皆さん,経営陣の皆さん,この狂気を止めましょう」――氏の呼びかけは明快だ。200万ドルや800万ドルでAAAゲームを作ろうとする試みは,現実的ではない。
業界に資金を戻す必要があるが,同時に重要なのは,適切な人材にプロジェクトを任せることだ。氏が見てきたなかには,非常に優秀な人材でありながら,ゲームディレクターを務めるにはまだ準備ができていない人にプロジェクトが任された例もあった。
「クリエイティブな人物をトップに置き,その周りにサポート体制を築く」――これが氏の考える理想的な体制である。自身も現在,スタジオ運営において98%をクリエイティブに集中できるよう,周囲のサポート体制を整えている。
品質の高いゲームを作るためには,適切な人材に適切な投資が必要だ。そうすれば業界は確実に収益を上げられると氏は確信している。
3. E3の復活
「E3を復活させてほしい」――氏の3つ目の提言は,多くの業界関係者の心に響くものだろう。
「E3は最も偉大なものだった。私が参加したすべてのE3は,私のゲームをより良くした」――氏はそう振り返る。ROI(投資対効果)を数式で示すことはできないが,E3に参加するたびにゲームは確実に良くなった。
同僚や友人との会話を通じて,新しい技術やメカニズムが共有された。企業がE3の外で独自のイベントを開催し始めたとき,氏は業界の断片化を予感する。そして実際にE3は終焉を迎えた。「私はそれらの独自イベントをボイコットした。業界が協力して働くのではなく,バラバラになっていくのが見えたからだ」
もしこれら3つの提言,とくに最初の2つが実行されれば,現在失業している優秀な開発者たちが復帰できる。「頭脳流出(Brain Drain)」を防ぎ,業界は健康を取り戻せる。そして大きなクリスマスシーズンが再びやってくるだろう――氏はそんな展望を描いてみせた。
講演の締めくくりとして,Schofield氏は歴史的な視点を提示する。歴史が示すように,すべての大きな技術的飛躍は,まったく新しい産業,機会,専門分野を創出してきた。
「(AIにより)一部の仕事は変化し,消えていくかもしれない。しかし新しい仕事が,何百万もの新しい仕事が,今後の数年間で創出される」――氏はそう語りかける。いまAIに取り組む人々が,その波に乗ることができる。
アニメーターはアニメーターとして,アーティストはアーティストとして――自分の専門分野は変わらない。しかしAIツールを学ぶことで,より良く,より速く,より効率的に仕事ができるようになる。それが自分自身を不可欠な存在にする方法だ。
「いまがその時だ。いまAIを学び始めれば,1年か2年後には専門家になれる。ほかの人たちがまだそこに到達していないうちに」――だからこそ,氏は業界全体でのトレーニングを提案するのだ。
最後に氏は,アイデアこそが業界の生命線であることを改めて強調した。そしてそのアイデアは,AI時代においても人間から生まれ続ける。「次の数年,そしてこれからの時代は信じられないほど素晴らしいものになる。次世代,あなたたちの世代には,本当に強力なツールが手に入る」
講演後のQ&Aセッションでは,会場から多くの質問が寄せられた。
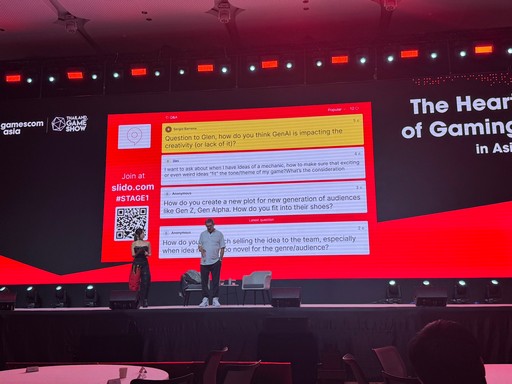 |
AIと創造性の関係について尋ねられた氏は,「AIだけに頼れば問題が起こる」と明言する。すべてのアイデアがAIから来るようになってはいけない。AIは松葉杖ではなく,ツールとして使うべきだと強調した。
アイデアがゲームのトーンに合うか確認する方法については,「周りの人に聞くことだ」とシンプルな答えを返す。氏自身,常にテキストやメールで相談を受けており,チームがない場合でも,適切なフィードバックをくれる人を見つけることが重要だという。
アイデアの規模を管理する方法について,氏は「メンタルヘルスのような広すぎるテーマの場合,本当にそれを作りたいのか,ファンが求めているのか,初期段階で徹底的に検証する必要がある」との見解を示した。
リスクの高いアイデアを実行に移す前には,必ず「ホワイトボックス」(未完成の要素で遊ぶテスト)やプロトタイピングを行うという。「The Callisto Protocol」では,500以上のプロトタイプを作成した。VFX,炎,アニメーション,戦闘――すべてがプロトタイプ段階でテストされていく。
リメイクと新作のどちらを好むかという質問には,「私はリメイクをやったことがない。アイデアがすでに出ているものより,完全に新しいゲームを作りたい」と明快に答える。もちろんリメイクが業界にとって重要でないわけではないが,氏自身はリスクがあっても新しいものを作ることを選ぶ。
最も好きなゲームについて尋ねられると,氏は即座に「Dead Space」と答える。EAと特別な交渉を行い,良質なデモ版の許可を得るまでに1年半かかった。自分が大好きなハードSFを作れた時期が,最も楽しい開発期間だったという。
奇抜なアイデアをどう提示するかという質問には,興味深い答えが返ってくる。「コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア」を最初にActivisionの経営陣20人に提示したとき,「100年先の未来だって? 歩行戦車? 30フィート飛ぶジャンプ? そんなのダメだ」と言われたという。
氏は反省を込めて語る。「やりすぎたと気づいた。最初は控えめに提示して,あとから要素を追加していくべきだった」。そして実際のゲームでは,誰もがカットしたがっていた歩行戦車を,ゲームの最初に登場させた。
アイデアの合意形成について尋ねられると,氏は笑いながら「殴り合いとかはしないよ」と応じる。長年一緒に働いてきたチームメンバーとは,お互いの言語を理解している。誰かが「それは良くない」と言っても,氏は受け入れる。「何百万ものアイデアを却下されてきたし,承認されたものははるかに少ない。拒絶は気にならない。良くないアイデアなら,捨てればいい」
業界の未来へ――クリエイティビティとテクノロジーの融合
 |
Glen Schofield氏の講演は,単なるテクニック論にとどまらず,ゲーム業界全体の未来に対する深い洞察と,具体的な行動提言を含むものとなった。
「Dead Space」や「Call of Duty」シリーズといった名作を生み出してきた氏の言葉には,長年の経験に裏打ちされた重みがある。アイデアの創出から実装まで,具体的なエピソードを交えて語られた9つの手法は,すぐにでも実践できる実用的なものばかりだ。
そして何より印象的だったのは,AIに対する氏の姿勢だ。多くの開発者が不安を感じるAI時代において,氏は「恐れるのではなく,学び,活用すべきだ」という明確なメッセージを発する。2年以上にわたってAIツールを使い続けてきた経験から,AIが人間の創造性を奪うのではなく,それを加速させるツールであることを実感しているという。
同時に,業界が直面する困難な状況についても率直に語り,具体的な解決策を提示した。AIトレーニングの開始,適切な投資と人材配置,そしてE3の復活――これらの提言は,真剣に検討すべき内容かもしれない。
「アイデアは業界の生命線であり,そのアイデアは人間から生まれ続ける」――Schofield氏のこの言葉は,テクノロジーが急速に進化する時代においても,ゲーム開発の中心には人間のクリエイティビティがあることを改めて確認させてくれる。
講演を締めくくる氏の言葉は,会場に集まったすべての人々への力強いメッセージだ。「ショーを楽しんで,新しい人々と出会い,お互いから学んでください。そして何より,楽しんでください」
ゲーム業界が困難な時期を乗り越え,再び健全な成長軌道に戻ることができるのか。その鍵は,Schofield氏が語ったような,創造性とテクノロジーの適切な融合,そして業界全体での協力にこそあるのかもしれない。
gamescom asia x Thailand Game Show 2025公式サイト
4Gamerのgamescom asia x Thailand Game Show 2025記事一覧ページ
- 関連タイトル:
 Dead Space
Dead Space
- 関連タイトル:
 Dead Space
Dead Space
- 関連タイトル:
 Dead Space
Dead Space
- この記事のURL: