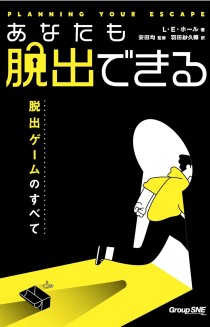連載
没入型ゲームの歴史を辿り,その構造に迫る「あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて」(ゲーマーのためのブックガイド:第42回)
 |
「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。
駅や地下鉄の構内に貼られたポスターで,「脱出」や「謎解き」という文言を目にするのは,今や珍しくなくなった。テーマパークや美術館,専門店などで,実際にプレイしたことのある人も多いだろう。あらかじめ用意された手がかりをヒントに,暗号を解読したりパズルを解いたりしながら,施錠された部屋から脱出する。あるいは別のエリアへと移動しながらストーリーを進めていく遊び。それが脱出ゲーム(あるいは謎解きゲーム)として人気を博している。
見慣れた日常の風景が非日常の空間に変貌することによる「没入(イマージョン)」感覚,複数の参加者が相談を重ねてベストな解法を見つける「双方向的(インタラクティブ)」な体験が,人気の秘訣だろう。
本書「あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて」は,そんな脱出ゲームの歴史と構造を解説した,ありそうでなかった一冊だ。著者のローラ・E・ホール氏は,何百という脱出ゲームに参加し,自身でもデザインを行い,関連するテレビ番組のコーディネーターも務めた人物である。
そんな彼女によれば,狭義の脱出ゲームが誕生したのは2000年代後半のこと。「リアル脱出ゲーム」を商標登録した日本のSCRAPが,初めての“正式な”脱出ゲーム運営会社だという。
「あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて」
著者:L・E・ホール
訳者:羽田 紗久椰
監修:安田 均
版元:新紀元社
発行:2022年6月3日
価格:3000円(税別)
ISBN:978-4-7753-2031-0
Honya Club.com
e-hon
Amazon.co.jp
※Amazonアソシエイト
新紀元社「あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて」販売ページ
面白いのは,本書が脱出ゲームを,先の「没入」や「体験」を基軸としたエンターテイメントとして定位し直している点だ。
だからSCRAPのリアル脱出ゲームだけではなく,アメリカの「5 Wits」のようなテーマパーク形式のガイド付きアドベンチャーや,ヨーロッパ初の“正式な”脱出ゲームとして知られるハンガリーの「Parapark」といったものも,現代型の脱出ゲームの出発点として捉えている。そして歴史を遡りながら,その原点と発展を紐解いていく。
その定義から言えば,「Pokémon GO」(iOS / Android)のような位置情報ゲームや,テーブルトークRPGをはじめとしたアナログゲームも,もちろん射程に入る。なにせ今から5000年近く前に存在したインダス文明の都市モヘンジョ=ダロで,子供たちが遊んでいた迷路ゲームを,脱出ゲームの一つの原点として位置づけているくらいだ。
それだけでなく,古代オリンピックのような競技会や中世の祝祭(カーニバル),ひいてはテーマパークや19世紀の万国博覧会なども,本書の文脈では脱出ゲームの原型の一つである。
中でも著者が重要視しているのは,1955年にアメリカ・カリフォルニアで開園したディズニーランドだ。来園者たちをファンタジックな劇の一員に迎える舞台のような設計思想,地下にゴミ輸送管を巡らせることで,ゴミが通路に溢れて雰囲気がぶち壊しなることを回避した点,お化け屋敷などのアトラクションを普及させたことなど。つまりは双方向的な没入感覚を育むための工夫が,さまざまな観点から凝らされているのが画期的だったというのである。
1970年代になるとテーブルトークRPGが誕生し,普及し始める。1980年代にはテーブルを離れ,プレイヤーが現実世界でキャラクターを演じるLARP(Live Action Role Playing)が世界各地に広がった。1970年代はカウンター・カルチャーの時代で,イギリスのグラストンベリー・フェスティバルなど,参加型のアート・イベントが多数開かれるようにもなる。
アメリカでは街頭での演劇や,廃工場の探索や宝探しといったゲームを企画するコミュニティのSF自殺クラブ――R・L・スティーブンスンの小説から採られた名前で,実際に自殺するわけではない――が活動を始めるなど,現実空間そのものをアートや遊びとして再解釈する試みも盛んになった。現実世界でミッションをこなして隠された宝を探すパズルハントというタイプのゲームが改めて注目されたのもこの時期だ。
ラジオやテレビでの動きにも,少なからず紙幅が割かれている。本書が注目するのは,1990年代に登場したイギリスのテレビ番組「Crystal Maze」だ。この番組では,「アステカ」「未来」などのテーマに合わせたセット内に用意された部屋のなかで,参加者が謎解きや課題に挑戦し,目標アイテムであるクリスタルの獲得数を競うというショーであった。
日本にも似たような番組は少なからずあったが,こうしたショーは脱出ゲームそのものであり,その中には今日の脱出ゲームに引き継がれている出題も少なくない。
脱出ゲームはデジタルゲームの世界にも広がった。
1980年代には,「ゾーク」に代表されるテキストアドベンチャーゲームが評判になり,のちに多くのフォロワーを生み出した。中でも有名なのが,1993年に出て世界的ヒットした「Myst」だろう。無人の島を訪れたプレイヤーが,建物や周辺を調べながら,謎めいた書物にまつわる秘密を少しずつ解き明かしていく同作は,今日の脱出ゲームを先取りしたかのような内容だった。
 |
1990年代後半になると,擬似ドキュメンタリー映画のパイオニア的作品「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」が評判を呼んだ。映画に込められた謎をより深く探るため,インターネットが活用されたのが画期的だった。
2001年には,最初のARG(代替現実ゲーム)「The Beast」も登場する。もともとは,スピルバーグ監督の映画「A.I.」のプロモーション施策だったが,単なるプロモーションの域を超える盛り上がりとなった。熱心なプレイヤーたちがコミュニティを形成すると,彼らの行動に合わせて,作り手側もストーリーを書き換えるようになり,双方向性がいっそう大胆なものとなったのである。
2004年には,高木敏光氏が開発したFlashゲームの「CRIMSON ROOM」が登場。シンプルで直感的な操作方法と,絶妙な難度設定で人気となり,これまた多数のフォロワーを生み出した。「Myst」のように大掛かりでなくても,気軽にゲームが作れるのだと,多くのクリエイターがが気づいたのである。
2010年代に入るとボードゲームでも,「脱出」や「謎解き」をテーマにしたタイトルが評判になり,一つのジャンルを形成するようになる。LINEと連動した卓上謎解きゲーム「ESCALOGUE」など,アナログなコンポーネントとスマホアプリを組み合わせることで,手軽なプレイ感覚とストーリーの奥行きを両立させているのは,現代ならではの工夫と言える。
 |
このように本書を通読すると,近年ブームとなっている脱出ゲームや謎解きが,一過性の流行ではなく,しっかり歴史に根ざしたものだとよく分かる。
なお本書の後半部は,実際にプレイするときの心構えやプレイヤーのタイプ分析,どうやって謎をデザインするのか,適切なヒントの出し方といった,脱出ゲーム初級者向けの実践マニュアルになっている。加えてよくある暗号のタイプや,謎のパターンのカタログもあって,制作者にとってもアンチョコとして貴重なものといえる。事前に目を通しておけば,ゲームに参加したときに慌てることもなくなるはずだ。
本書は読み込むほどに「あなたも脱出できる」という自信が持てるようになり,プレイヤーとしても制作者としても,スキルが向上する一冊となっている。なるほど,「脱出ゲームのすべて」というサブタイトルは伊達ではない。没入型ゲームにわずかでも関心がある人は,ともあれ手にとって損はないはずだ。
■■岡和田 晃(翻訳家,文芸評論家)■■
SF・幻想文学やクラシックなスタイルのゲームにちなんだ翻訳紹介を得意とするライター・翻訳家。2025年8月には,世界で2番目に古いRPGのデザイナーによる新作「ケン・セント・アンドレによるズィムララのモンスターラリー【ワールド編】」(翻訳書,FT書房)や,クトゥルフ神話料理本「料理の魔書ネクロノミコン ラヴクラフトの物語から生まれたレシピと儀式」(共訳書,グラフィック社)が出版予定となっている。
新紀元社「あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて」販売ページ
- 関連タイトル:
 リアル脱出ゲーム
リアル脱出ゲーム
- この記事のURL:
(C)SCRAP All rights reserved.