1����⤮���ޤǤΥץ쥤������
����������ϼºݤ�ɮ�Ԥ�1����⤮���ޤǤˤ��ɤä������ץ쥤�����ɤȤ��Ƥ��Ϥ����褦���Ϥ���������Ƥ��������Τ�����Dota Auto Chess�פϡ��鿴�Ԥ���������ͷ�٤�褦�ˤʤ�ޤǤΥϡ��ɥ뤬���������⤤�Ȥ������ȡ��Ф���٤������̤�����ǡ����������𤷾��Ƥ�ޤǤˤϡ�¿�������ϤȻ��֤�ɬ�פȤʤ롣����Ǥ�³���ơ����������μ����ߤ����龡����Ĥ�����Ȥ��δ�Ӥϳ��̤Ǥ��롣¿���ν鿴�ԤˤȤäƤ��Υ����ɤ�ƻ����٤ˤʤ�й�������
��
STEP1���������˴����
����Dota Auto Chess�פȡ��뤷���ޤ����ꥢ����������ܤ��ɤϡ�CPU������˴���뤳�Ȥ����������˴��졤1�������ή���Ф����Ȥ������������ȥ饤�����
���ֶ���������ע��ֶ�����̤����֤���ע�����Ʈ���ע���CPU���ݤ����饢���ƥ���פȤ��ä���Ϣ��ή���Ф����顤������̤����Ҹˤˤ�ɤ����ꡤ�����Ѥ����ꡤ�����ƥ����������������ȡ��������ijΤ��ᡤ�Ǥ��뤳�Ȥ��Ƥߤ褦��
����������ӡ����������1���Ѥ��������褦����PLAY DOTA AUTO CHESS�פΥܥ�������п��郎�ϤޤäƤ��ޤ��Τǡ����Фʤ��褦�����դ��Ƥۤ���
 |
���������֤ˤ϶����ǽ��å����Ƴ�ǧ���Ƥ���������̩�ˤ��٤Ƥ�Ф���ɬ�פϤʤ������ʤ�Ȥʤ�����ǽ���İ����Ƥ�������
 |
STEP2�����ʥ�������Ω�����Ƥߤ�
��1���Ѥ������������Ƥ����ʬ���뤬���ܺ��CPU��Ǥ�դĤ�����������ͤ���Ŭ���˶������������̤����֤��Ƥ�������Ǥϡ�����Ū�ˤ����Ÿ����³���Ƥ��ޤ���������
�������Ǽ��˳Ф���٤����ܤϡ��ּ�²���ʥ����פȡ֥��饹���ʥ����פ���Ω������ˤ�äơ���²�ȥ��饹�Ϸ�ޤäƤ���Τǡ������ͤ����ˡ��ޤ�Ʊ����²�����饹�ζ������֤��Ƥߤ褦��
�ǽ�Ū�˶����ǽ�ȼ�²�����饹�ϳФ���٤������������ǤϳФ��ʤ�������פ�������碌�Τ褦�˼�²�����饹�����פ�����·���뤳�Ȥ���Ϥ�Ƥߤ褦
 |
��²�Ρ֥��֥��פ䥯�饹�Ρ֥ᥫ�ס֥����ꥢ���פ�����Ͻ��פ˽���䤹���������˥��ʥ�����ȯ�����Ƥ����
 |
STEP3�����åץ��졼�ɤ����äƤߤ�
�����פϽи������μ��ब�������ٸ��ꤵ��Ƥ��뤿�ᡤ���ʥ�������Ω����ñ���Ķ��Ϥ��������פ˸����ơ�Ʊ��ζ��3�ν���뤳�Ȥ�ȯ�����륢�åץ��졼�ɤ��������������åץ��졼�ɤ������ǽ�������˸��夹��Τǡ����ߤ��˥��ʥ�����ȯ�����Ƥ�������Ǥϡ��֡����פζ��̵ͭ����Ʈ�ξ�Ψ���礭���ƶ���Ϳ����櫓����̵���˥饤��ʥåפ�����ɬ�פϤʤ�����������Ƥ�����Ʊ��Τ�Τ��������Ѷ�Ū�˹������Ƥ�������
���ˤ�äƤϥ��ʥ�������ͥ�褷���ܻؤ��������åץ��졼�ɡ�������2�Υƥ���С������Τ褦��ñ�ΤǤ�������ʥ�������Ω���䤹����ϤȤ���ͭǽ��
 |
���饹�֥ɥ륤�ɡפΥȥ��Ȥθ���������ɥ륤�ɤϡ�Ʊ���2�Τ��̤Υɥ륤�ɤ�����Х��åץ��졼�ɤǤ��롣��Ʈ�˴�Ϣ���륷�ʥ����Ϥʤ�����ñ����ǽ����Ʈ�˹����Ƥ����
 |
STEP4����PLAY DOTA AUTO CHESS��
�����ڡ����Ǥ�ڤ����줿�����ܺ��1����CPU��ȥ���饤����п���Ϥޤä����㤦���������ȤʤäƤ��롣�����������˴���ơ����ʥ����䥢�åץ��졼�ɤ�������褿�顤�פ��ڤä��п�������ӹ���Ǥߤ褦���и��ԤȤ����ʤ���äƾ�������Τ�����������Ƿи��ͤ��Ѥळ�Ȥ���ã�ؤΰ��֤ζ�ƻ�Ȥʤ�Ϥ�����
��STEP5�ʹߤǤϡ��п���Ǿ�����夲�뤿��ν��פʹ��ܤ��Ϥ����롣�ܹƤ�����ȸ����櫓�ǤϤʤ������������Ĥ���λؿˤˤϤʤ�Ϥ��ʤΤǡ����ͤˤ��Ƥۤ�����
�ܺ��CPU����п���ǤϹ�ά�����������ޤä����ۤʤ롣�и��Ԥ��餱³����Τ϶줷�������餱�ʤ��饲�����Ф�����Ĺ���Ƥ�����
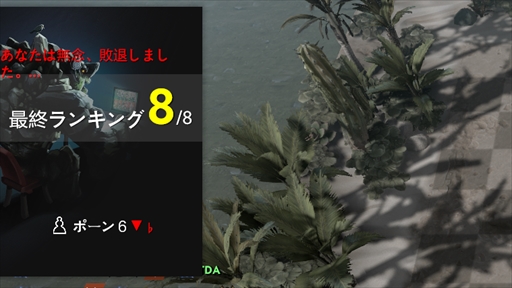 |
�����֤�����˼���Ȥ�ΤⰭ���ʤ������������٥ץ쥤���ʳ��ǥ������ߤ�ơ����������������֤��ꤿ�����Ȥ��˶�Υ����Ȥȼ�²�����饹�ϡ��ǥå������۷Ϥ��ܻؤ�������ɬ���Բķ�ʾ�������������ܻؤ��ΤǤ���С����ä�����İ����Ƥ�������
 |
STEP5�����פϥ饤��ʥåפι�����Ǥ������������
����Ҥ������ʥ����ȥ��åץ��졼�ɤ���������ˡ��ֽ��פ����Υ饤��ʥåפ����褦���פȹͤ���ͤ⤤�������������ϸ��ؤ����Ȥ����Τ��ܺ�Ǥ϶�Υ饤��ʥåפ��ץ쥤�䡼��٥�˰�¸���Ƥ��뤿�ᡤ���פǤϤ����鹹�����Ƥ��㥳���Ȥζ𤷤��и����ʤ��������
�����˽��פ˥饤��ʥåפ��������ޤ�Ϣ���Ǥ����Ȥ��Ƥ⡤�������٥����ब�ʹԤ���ȡ���٥�ι⤤���֤ǥ饤��ʥåפ������ץ쥤�䡼�˥ǥå��μ���Ũ��ʤ��ʤäƤ��롣
���ɤ��ǹ�������Τ��٥��Ȥ��ϡ����äƤ��륷�ʥ���������ˤ�ä��Ѳ����뤿��Ƚ�Ǥ�ɬ�פȤʤ뤬���ҤȤޤ������פ˹�������ɬ�פϤʤ��Ȥ������Ȥ�Ф��Ƥ�������
���ʥ�������Ω���������åץ��졼�ɤ������ʤ��ȶ줷��Ÿ����³���Ƥ��ޤ�������������̤�˾�����ΤǤʤ���С�����˶줷���������ɤ����ޤ�뤿�ᡤ���äȤ��館�ƥ�����ԤȤ�
 |
�������װʹߤǤ��dz����������ʤ���С��פ��ڤä�������ڤ����������Ϥ�����Τ�1�Ĥμ����1�̤������ʤ��ʤ뤫�⤷��ʤ�����1�ĤǤ��̤�夲�뤿��˺���¤����Ϥ���
 |
STEP6����٥륢�åפΥ����ߥ�4���ܿ���1�Υ饦��ɻ�
�����ڡ����Ǥ�줿�����ܺ�����̤��֤����ο����ץ쥤�䡼��٥�˰�¸���Ƥ��롣���̤ζ�����������������Ʈ���줷���ʤ�Τǡ��Ǥ���¤ꡤ�ʲ��Υ����ߥǥ�٥륢�åפ�ԤäƤ�������Ϣ���Ǥۤ��Υץ쥤�䡼��GOLD�ʺ���Ĥ�����С������������ͭ���˱��٤�Ϥ�����
����٥�4����٥�5
5�饦����ܤ˷и��ͤ�1�ٹ�����5GOLD�����
��5�饦����ܤ��ߤ����𤬤������6�饦����ܤ˷и��ͤ�1�ٹ�����5GOLD�����
����٥�5����٥�6
9�饦����ܤ˷и��ͤ�1�ٹ�����5GOLD�����
����٥�6����٥�7
13�饦����ܤ˷и��ͤ�3�ٹ�����15GOLD�����or17�饦����ܤ˷и��ͤ�2�ٹ�����10GOLD�����
����Ƥ���ͤۤɾ嵭�Υ����ߥǥ�٥륢�åפ�ԤäƤ��롣�����ߥϤۤܰ���ʤΤǡ������˳Ф�����Ϥ���
 |
STEP7��GOLD�ξ���Ϻ���¤ˡ�������Ԥ�
����Υ饤��ʥåפ�Ǥ�������������ʤ��ä��ꡤ��Ψ�Τ��������ߥΥ�٥륢�åפ�Ԥä��ꤹ��Τϡ����Ρ������פ���¿�����뤿������ܺ�Ǥϳƥ饦��ɤγ��ϻ��ˡ����饦��ɤǽ�����Ƥ���GOLD��10�������������Ǥ��롣Ϣ��orϢ���Ȱۤʤꡤ������������GOLD�ϰ���Ǥ��뤿�ᡤ�����˺�������ˤ������ɤ����Ǿ���˽Фʤ��Ȥ����ʤ��������ɬ��ˬ��뤬����ʬ�λ����Ϥ����̤��Ĥġ����ߤƤ�������
���Ҥλ��Ȥ�Ū�ˡ�GOLD������10GOLD��ߤ����ܤȤʤ�
 |
�����ξ�¤�50GOLD�ʾ�Ǥ�館��5GOLD�Ȥʤ롣��Ʈ��;͵������С�50GOLD���פ��Ĥġ��ǥå��ζ����˼���Ȥߤ���
 |
10�饦��ɰʹߤ�5�饦��ɤ��Ȥ�ȯ������CPU������Ϥ����äƤ���о������䤹����̵����GOLD��Ȥ鷺��������������褦
 |
STEP8�������ǽ���İ���������Ū�ʥǥå����ۤ�����
�������ޤǤ˾Ҳ𤷤����Ƥǡ���Dota Auto Chess�פι�ά�δ������ˤϤۤȤ�����Ƥ���Ϥ��������褤�辡�����ܻؤ�����κǸ�δ���Ǥ��롤�����ǽ���İ�������Ū�ʥǥå����ۤؤ�����˼���Ȥ⤦��
�����������դ������Τϡ����٤Ƥζ����٤˳Ф���ɬ�פϤʤ��Ȥ������ȡ��ܺ���о줹���ο�������Ǥ����ʤꤹ�٤Ƥ�Ф���Τ������ҤȤޤ��Ϻ��ޤǥץ쥤�����ʤ��dzФ������褫����ǥå������۷Ϥ�Ĵ�١������ɬ�פʥѡ��Ĥ�Ф��Ƥ����Τ�������������
���䤵����Υ饤��ʥåפϥ����फ�ġ��ۤ��Υץ쥤�䡼�ȶ��礹�뤳�Ȥ⤢�뤿�ᡤ�ǥå������Ǥ��ǹ��ۤ���Τ���������������Ū�ʥǥå��������Ĥ��Ф��Ƥ����С��������������Ѥ��б��Ǥ���Ϥ���
 |
ɮ�Ԥ�1����⤮�Ȥ뤿���������ǥå��ϡ���²�Ρ֥��֥��פȥ��饹�Ρ֥ᥫ�פ��濴�ˤ�����������֥��֥�ᥫ�פ���������ͳ�ϡ������ܤ�̾����Ƚ�̤��䤹������
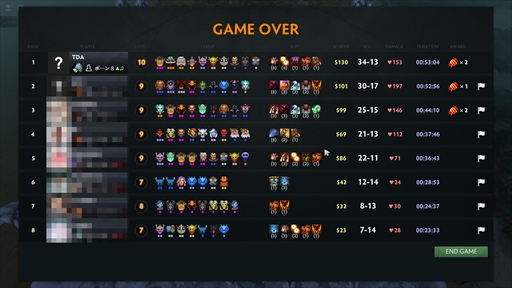 |
���ޤ����鿴�Ԥ˥�������Υǥå����Ĥ��Ҳ𤹤롣�������٤����ȤʤäƤ���Τǡ����һ��ͤˤ��Ƥۤ�����
6�����ꥢ���ʡ�4�ӡ����ȡ�
�������ꥢ���Υ��ʥ����Ǽ��ӡ����ȤΥ��ʥ����ǹ����徺������ǥå������������ꥢ���ζ���ܺ�ǺǤ�¿��11����¸�ߤ������פ˻��Τ����ˤ������Ȥ��礭����ħ�����ӡ����ȤΥ٥Υޥ��������ɥ륤�ɤ�ñ�ΤǤ�Ϥʥ�˥åȤǡ����ʥ�����ȯư���ʤ��Ȥ��礭�ʳ������Ƥ���롣
���ޤ��������ꥢ���Υȥ�����ᆳ�ϥ����ƥ��֥����������ʤ����ᡤ�ּ���줿�۷칶��Υޥ���
���פ�����������Τ˺�Ŭ�ʶ��1�ġ������Ǥ������Ͽ���������������褦��
������줿�۷칶��Υޥ��������������ȵ۷쵴�Υޥ������Ȥ߹�碌�Ǻ�������륢���ƥࡣ��Υ����ƥ��֥����뤬��������뤬������®�٤θ���ȥ饤�ե��ƥ�����10����Ϳ�����
��²���ʥ������������ϡ�
2����Υӡ����Ȥ����֡�̣�������ʾ�����ʪ��ޤ�ˤι����Ϥ�10��徺
4����Υӡ����Ȥ����֡�̣�������ʾ�����ʪ��ޤ�ˤι����Ϥ������20��徺�ʹ��30���
���饹���ʥ�������Τμ���
3����Υ����ꥢ�������֡�̣���Υ����ꥢ���Υ����ޡ���5�徺
6����Υ����ꥢ�������֡�̣���Υ����ꥢ���Υ����ޡ��������7�徺�ʹ�ס�12��
9����Υ����ꥢ�������֡�̣���Υ����ꥢ���Υ����ޡ��������9�徺�ʹ�ס�21��
| ��̾�� |
������ |
��² |
���饹 |
| �������� |
1GOLD |
�ӡ����� |
�����ꥢ�� |
| ���顼���� |
2GOLD |
�ʡ��� |
�����ꥢ�� |
| ��ϵ�饤���� |
3GOLD |
�ӡ�����/�ҥ塼�ޥ� |
�����ꥢ�� |
| ��±������ |
4GOLD |
�ҥ塼�ޥ� |
�����ꥢ�� |
| �ȥ�����ᆳ |
4GOLD |
�ȥ��� |
�����ꥢ�� |
| �ɥ�����ǡ���� |
4GOLD |
�ǡ���� |
�����ꥢ�� |
| �٥Υޥ� |
3GOLD |
�ӡ����� |
���������å� |
| ������ɥ륤�� |
4GOLD |
�ӡ����� |
�ɥ륤�� |
4�������ʡ�3�ᥤ����
�����פ��㥳���ȤǶ��Ϥ����ҤȤʤ�֥������פζ�ᡤ���װʹߤ˹⥳���ȡ�����Ϥʡ֥ᥤ���פζ��Ƥ��������Ҥȸ�ҤΥХ���褯���ɤ�ʥ����פΥǥå��Ȥ��廊���������ߤ����ǥå����濴�Ȥʤ�Τϡ����Ϥ��ϰϥ��������ĥ��������ꤤ�դ���Υ����롣�����ζ�ϡ�̣���˥ޥʤ뤹�������饤�Υѥå��֥�����ˤ�ä������������Ƥ�褦�ˤʤ롣�⤷����������������ݤ���Ƥ��ޤäƤ�����ϡ�HP�ι⤤��θ�������֤���ʤɤι��פ�Ȥ�����������
���ޤ���8���ܰʹߤΥץ��ϡֳ�±������ä���3�����ꥢ����ȯư������ס֥ᥤ�����ɲä��Ƥ�����6�ᥤ�����ܻؤ��ס֥����ɥϥ��ȥ�ǥ塼����ä��ơ�2�ʡ�����3�ϥ���ȯư������פʤɤΥѥ������롣¾�ץ쥤�䡼�Υǥå������˱����ơ����ҡ���Ҥɤ��餫�����Ƥ�������
��²���ʥ�����ɴ��ϣ���
2����Υ����������֡�̣���Υ������κ���HP��250�徺
4����Υ����������֡�̣���Υ������κ���HP�������350�徺�ʹ�ס�600��
���饹���ʥ�������ˡ�����������
3����Υᥤ�������֡�Ũ��������ˡ������35���㲼
6����Υᥤ�������֡�Ũ��������ˡ�������45���㲼�ʹ�ס�80���
| ��̾�� |
������ |
��² |
���饹 |
| ����� |
1GOLD |
������ |
�����ꥢ�� |
| �������㥬�� |
2GOLD |
������ |
�����ꥢ�� |
| �ӡ����ȥޥ����� |
2GOLD |
������ |
�ϥ� |
| ���������ꤤ�� |
4GOLD |
������ |
���㡼�ޥ� |
| �����饤 |
2GOLD |
�ҥ塼�ޥ� |
�ᥤ�� |
| ������� |
3GOLD |
������ |
�ᥤ�� |
| ����Ϸ��ƻ�� |
4GOLD |
�ҥ塼�ޥ� |
�ᥤ�� |
6���֥��ʡ�3���������å���
��̣�����Τ˥����ޡ���HP��������Ϳ����֥ʥΥޥ���פΥ��ʥ������ܻؤ��ǥå����������֥��ϣ��ѻդΥ��饹�����������å��Τ��ᡤ�ƤΥǡ������Ի�Υͥ����Ȥ��ä�ͥ���ʥ��������å����Ȥ߹�碌�ơ��������ɲå��ʥ�����ȯ����������Τ����ߤ���
�����������֥ʥΥޥ���פΥ��ʥ����ϡ�6�ΤΥ��֥��·��ʤ������Τ�ȯ�����ʤ���������5�����빩�������������餱�뤳�Ȥ�¿�����ꥹ�����ʥǥå��Ȥ⤤���롣
��²���ʥ����֥ʥΥޥ����
3����Υ��֥������֡�����������Ф줿̣��1�ͤ˥����ޡ���15������10��HP��������Ϳ
6����Υ��֥������֡�̣�������˥����ޡ���15������10��HP��������Ϳ
���饹���ʥ����֥����륹�ƥ������
3����Υ��������å������֡�̣�������˹���ȥ������Ϳ�����������10��ʬ��HP��������륹�������Ϳ
6����Υ��������å������֡��嵭�Υ������Ϳ�����ݤβ����̤������20������
| ��̾�� |
������ |
��² |
���饹 |
| �������� |
1GOLD |
���֥�� |
�ᥫ |
| ���֥���Ԥ� |
1GOLD |
���֥�� |
�������� |
| �ƥ��� |
1GOLD |
���֥�� |
�ᥫ |
| �ƥ���С����� |
2GOLD |
���֥�� |
�ᥫ |
| ���֥��ϣ��ѻ� |
4GOLD |
���֥�� |
���������å� |
| ���빩��� |
5GOLD |
���֥�� |
�ᥫ |
���嵭6���֥��˲ä��ơ��ʲ�����2��
| ��̾�� |
������ |
��² |
���饹 |
| �ƤΥǡ���� |
3GOLD |
�ǡ���� |
���������å� |
| �Ի�Υͥ��� |
4GOLD |
����ǥå� |
���������å� |
| ������� |
5GOLD |
������ |
���������å� |
| �Ի�ΰ���Ȥ� |
5GOLD |
����ǥå� |
���������å� |
�����֤��ץ쥤��³������ã���������ڤ��⤦
���ʾ夬�ץ쥤�����ɤȤʤ롣ɮ�Ԥϥ�����ȡ��뤷�Ƥ��顤�嵭�Τ褦��ƻ�ڤ�é�ꡤ�ݡ�2���֤�����1����⤮��ä����餱³�����줷�����֤�Ĺ���ä������������ľ�ã�����μ��⽼�¤�����������沈����ʤ�ǤϤγڤ��ߤ��ͤޤäƤ����褦�˴�����줿��
���ܵ����ˤϡ�Dota Auto Chess�פ�ץ쥤���뤿���ɬ�פʴ����μ��Ϥ��٤�������ޤ�Ƥ��롣���줫���ܺ������⤦�Ȥ����ͤϵ����ͤˡ��餱��礫��⤤�������ʤ��Ȥ�ؤӤʤ��顤����ͷ��³���Ƥۤ�����







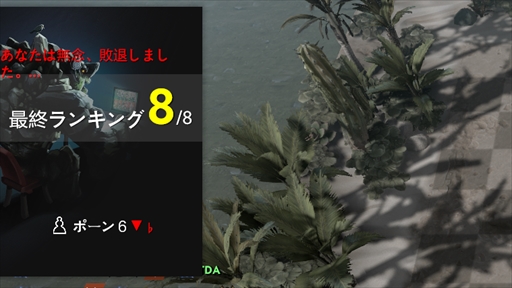








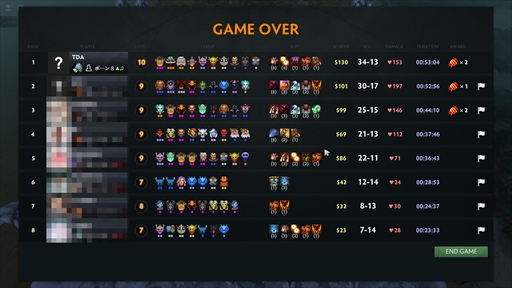









 Dota 2
Dota 2



















