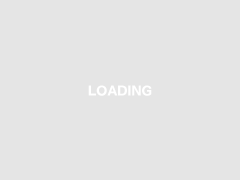連載
蓬萊学園の揺動!
Episode04
この学園を救ったりなんだりするはずだが一体どうやってそれを成し遂げるのか当人はもちろん作者もよく分かってないっぽい主人公は、旧図書館に入館した!
(その7)
――どれだけ走ったことでしょうか。
あたりまえの、本当にどこにでもありそうな、書棚に挟まれた薄暗い通路の中ほどで、わたしたちは立ち止まりました。隅のほうには図書閲覧用の机と椅子もありました。
「……ああ!」
突然、わたしの隣で高い声がしました。
「ああ、ああ、ああああ!」
紫苑さまでした。
わたしの紫苑さまが、崩れるように膝をつき、両手で顔を覆って、嘆きの声を……悲鳴をあげ続けたのです。
「し、紫苑さ……」
悲鳴が止まりました。
いいえ、わき出ようとする悲鳴を必死にこらえたのです。
「ごめんね、子猫ちゃん」
しばらくして、ようやくそんな言葉が聞こえました。
「僕は――ああ、僕は弱い人間なんだ。臆病で、いつも不安で、迷ってばかりいて、何の取り柄もなくて……」
「そんなことないです!」わたしも叫びました。「紫苑さまは、いつも美しくて、カッコよくて、上級学生で!」
「それは――あんなのは、まやかしだよ」
「え?」
美しいお顔を覆っていた両手がゆっくりと膝に降りてゆき、涙でくしゃくしゃになった彼女の瞳が、まっすぐわたしを捉えました。
「上級学生、女生徒たちの憧れ、男装の麗人――まやかしだ、全部まやかしなんだ、本当の僕とはなんの関係もない外見ばかりのデッチアゲだよ。僕はお金持ちに生まれたわけでもないし、家柄が優れているということもない。ただ単に、顔の彫りが深くて、そのおかげで――そのせいで、あの野々宮グループの総裁である女王さまに拾われて……そうさ! 拾われたんだ! ゴミ箱に捨てられていたオモチャが、ちょっとばかりまだ綺麗だっただけでね!
そして僕はちょいとした訓練を受けさせられて、磨かれて、化粧をされて、この島へ連れて来られたんだ。
上級学生……特別奨学制度……学園に寄付をして他の生徒たちの勉学や部活を奨励するから特別の待遇が与えられる――そんなのは建前さ。この僕自身が学園に寄付してるわけじゃない。僕の名義で、野々宮グループが寄付をしてるのさ。それが一般生徒たちの学費に回され、部活の補助金になり、安くて美味しい学食横町の経営を補填し……」
「――――」
「……そしてそこで消費される食べ物や飲み物の材料は……そう! 野々宮グループが一手にまかなっている! 何もかもが、お金の姿をとってグルグルと巡っていて、僕らはその大きな回し車の中で走り回っているハムスターさ! ただのでっち上げ、作り物、仮面劇――! 上級学生? こんな虚飾の制度!」
静寂。
呆然と、わたしは床に座り込んで、閲覧机に座っている彼女を見上げていました。
やっとの思いで、わたしは彼女の名前を口にしようとしました。
「しお――」
「違うよ」というのが返答でした。
「え?」
「それは野々宮の女王さまが僕につけてくれた名前だよ。僕の見栄えにふさわしい、と言ってね。あの日のことは忘れないよ。女にしては、ちょいと背が高くて、日本人にしては鼻筋がとおっているだけの……女に生まれたのに男になりたくて、でも素敵な男の人と一緒になりたがっている、家族からは理解されるどころか煙たがられていた、ただの田舎の女子中学生が、新しい飼い主に、新しい名札をつけてもらったんだ。教えてあげようか、僕の本当の名前はね――」
彼女は、わたしの耳元に、その青ざめた唇を近づけました。
わたしは両目を見開きました。
「それって――」と、つぶやくのが、わたしは精一杯でした。「それって、すごく地味な名前ですね」
「だろ?」青ざめた笑み。青ざめた涙。「もう僕のことなんか嫌いになった?」
「ええ」
わたしは正直に答えました。
とても正直に。
「その名前は好きじゃなくなって……でも、あなたのことはもっと好きになりました」
そのまま、そこで10年が経ちました。
わたしたちは旧図書館からの出口を探しましたが見つからず、そのうちに地下四階で生きるすべを探し求めるようになりました。
幸いなことに、地下四階の片隅が深い密林となっており、そこには私たちに必要な水や、食糧となる果実や小さな獣が豊富にありました。
わたしたちは小さな寝床を作り、それはやがて大きな家にまで成長しました。わたしと彼女(もはや紫苑様ではありません)は、果物を集め、獲物を狩り、時にはきれいな花を集めては首飾りにもしました。彼女は初めこそわたしのことを「子猫ちゃん」と呼んでいましたが、そのうち「そよ子ちゃん」となり、やがては「そよ姫」というあだ名も付けてくれました。
時には喧嘩もしましたが、それはかえって、わたしたちの絆を深めるきっかけとなったのでした。
そうしてわたしたち――わたしの愛する彼女とわたし、そして物言わぬアプちゃんの二人と一頭は、とても幸福に暮らしていました。
けれど、ちょうど十年目の朝、あの正十三面体が戻ってきたのです。
わたしたちは驚き、逃げまどい、そしてとうとう密林と本棚の境目にまで追い詰められました。
わたしは叫び、彼女に手を伸ばし、ああどうかこの方だけでも御無事であられますように、このわたしなんかはどうなっても良いから……と、心の底から願いました。
けれども正十三面体はわたしの視界を覆い尽くし――そして空間が反転し、時間が暗転し、すべての実在が無限と重なり合って――
「あ、起きました? そよ子さんが目覚めましたよ、みなさん!」
京太くんの大アップと、スットンキョウに明るい声が、わたしの視界いっぱいに広がっていた見知らぬ天井の代わりに押し寄せてくると、わたしは自分が学園病院のベッドに寝かされていることに気づいたんです。
「良かったわあ!」アミ先輩の巨大な体が視界の左半分を占拠します。「そよっち、痛いとこあるん?」
「いま何年?」
「へ?」京太くん、眉をひそめて、「まだ今年ですよ。て言うか、あれから五時間くらいしか経ってませんけど」
「地下四階は――失われた教科書は……」
「あ、あれはアミ先輩とボクでちゃんと返却してきました。司書さんからコッテリ絞られましたけどね」
司書? 旧図書館に司書?
「ああ、あの正十三面体のことを、ボクがそう命名したんですけどね。他にもいろんな大発見がありまして――」
混乱したまま、わたしは京太くんとアミ先輩の大冒険と蘊蓄を聴くともなしに聴いていました。
え。
なに。
なにこれ。
これって、もしかして。
夢オチ?
大先生・手塚治虫が「やっちゃダメ」って『漫画のかきかた』で厳命してた、アレ?
ぜんぶわたしの妄想?
衝撃と恐怖のあまり、わたしが手塚大明神の神呪を暗唱しようとした、その瞬間。
「やあ無事でよかった」
紫苑さまの美しい声が、わたしの近くで響きました。
手足がグルグル包帯巻きではありましたが、その麗しいお姿は、まさに返還旅団作戦開始の際と――ほんの数時間前と! ――寸分変わらぬものでした。
「あの……あの……」
よかった無事だったんですね! と言おうとして、わたしは大きくクシャミをしてしまいました。
「もう大丈夫だよ」絹のハンカチで顔を拭きながら、紫苑さまが微笑みます。「僕たちは助かったんだから。無事に任務も達成したし」
「でも、でも、でも……」
そして。――
愛しの北白川紫苑さまは、わたしと十年の愛の年月を共に過ごしたこの方は、わたしが睡眠導入剤によって再び眠りにつく前に、わたしの手を取り、こう囁いたのでした。
「だから安心してお休み、そよ姫」
- この記事のURL: