連載
ゲーミフィケーションの進化系「ゲームフルデザイン」と,その著者・伊藤真人氏:身近なところにゲーミフィケーション 第5回
 |
ゲーミフィケーションとは,ゲームの持つ要素や原則をそれ以外の分野に導入して,人々のやる気を高めたり,問題解決を図ったりすることに活用する仕組みである。
本連載「身近なところにゲーミフィケーション」では,ゲーミフィケーションを活用した製品やサービスなどを,ゲーミフィケーションデザイナーとして活躍している岸本好弘氏とともに紹介していく。
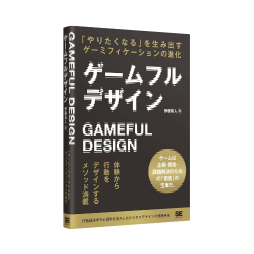 |
ゲームフルデザインは,ゲーム要素を活用した体験設計により,対象とする人たちに「ついやってしまう」「ついやりたくなってしまう」「ついやり続けたくなってしまう」といった行動を促す課題解決を目指したアプローチで,ゲーミフィケーションの中に内包された概念である。
本書では人間が持つ「9つの欲求分類」に紐付く「101の手法を体系化したゲームフルデザインボード」を使って,人を夢中にさせる力を活用する手法を紹介している。
そんなゲームフルデザインについて,本書の著者であるセガ エックスディー 取締役 執行役員COO 伊藤真人氏に話を聞いた。
 |
セガに入社し,モバイルゲームプランナーを経てアドテクの領域へ
1987年生まれの伊藤氏は,相対性理論に興味を持ち,大学では量子化学を専攻していたという。それ以前は人並みにゲーム好きで,小学生のころは「スーパードンキーコング」や「ゴールデンアイ 007」「大乱闘スマッシュブラザーズ」といったタイトルを好んでいたそうだ。
伊藤氏:
大学時代は,麻雀をやって,サークル活動をして,飲みに行くというような,ごく普通の大学生でした。ただ2009年に起きたリーマンショックの影響で,新卒採用が厳しくなったんです。私も100社以上を受けましたし,大学3年生のときは,ほぼ就職活動をしていた記憶があります。
2010年4月に伊藤氏はセガに入社した。ソニー・エリクソン(当時)がXperia X10のOSにAndroidを採用したことをきっかけに,伊藤氏はスマートフォン向けのゲームが流行するのではないかと考え,モバイルゲームの部署を志望したという。
伊藤氏:
コンシューマゲームやアーケードゲームと違って,少人数でこぢんまりとやっていたので,1年目でもいろいろプロジェクトを任せてもらえたんですよね。
モバイルゲームといっても当時はフィーチャーフォン,かつキャリアの月額サービスが主流でしたから,先輩方がそちらをやって,スマホは新人に任せるという空気だったんです。
2012年にはガンホー・オンライン・エンターテイメントの「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット。セガも2011年の「Kingdom Conquest」がヒットしており,2012年にはスマホゲーム専門のセガネットワークス(当時)が設立されている。
伊藤氏:
私の場合は,たまたま時期が良くて結構自由にやらせてもらえたので,本当にラッキーでしたね。プランナーとして,エンジニアとデザイナーがやること以外は全部やっていました。
 |
2012年,伊藤氏は当時セガの新規事業だったスマホアプリ向けマーケティング支援サービス「Noah Pass」(ノアパス)に,ディレクターとして参画したことから,活躍の場をアドテクの領域に移すこととなった。
伊藤氏:
ゲームそのものよりゲーム周辺を扱うほうが面白いと感じるようになっていったんです。そのあともセガの新規事業としてゲーム周辺のサービスを手がけていました。その新規事業チームが,そのまま2016年にセガの子会社として設立したセガ エックスディーの初期メンバーになったんです。
岸本氏:
ゲーム自体の面白さではなく,ゲームの周りのいろいろなことをやって面白いと思った伊藤さんの経験が,今のゲームフルデザインの考え方につながっているんですね。伊藤さんにとって今の状況はゴールではなく,より面白いと思うことがあったら,きっとそちらに飛びつくんでしょうね(笑)。
 |
ゲームフルデザインは,本質的なゲーミフィケーションを踏まえた体験設計
セガ エックスディーではゲーミフィケーションを扱っているが,一番大きな課題はゲーム業界とほかの業界のコミュニケーションの難しさだったという。
つまりゲーム業界では「いかに感情的な価値を高めるか」など「体験の最大化」が価値となるが,ほかの業界では基本的に「ユーザーの不便をどう解消するか」「いかにコストを抑えて生産するか」といったように「体験の効率化・最適化」が価値になるため,話をしていてもギャップが生ずるのである。
伊藤氏:
ゲーム業界の人がゲーミフィケーションに取り組んだとき,どうしてもゲーム業界の感覚で話をしてしまうんですよね。そうなると,ほかの業界の人は「たかがゲーム,遊びでしょ」という認識になってしまう。そこはギャップを感じました。
たとえば鉄道業界だったら「どれだけ効率よく,多くの人間を移動させられるか」といったことが価値になるので,そこに面白さは関係ないですよね。ビジネス上の価値があるということをしっかり伝えないと具体的な話にならないということを学びました。
 |
海外では,認知度が高まっているゲーミフィケーションという概念だが,セガ エックスディーが2024年に実施した「ゲーミフィケーションに関する意識調査」によれば,日本の16%しか知らないという結果が出たという(関連リンク)。
セガ エックスディー設立から9年経った2025年になっても,日本にはまだまだゲーミフィケーションが浸透していないと伊藤氏は語る。
伊藤氏:
ゲーミフィケーションという概念は昔からありますが,認知度はまだまだ低いのが現状です。テレビというマスメディアでは最近になって「新しい概念だ!」と取りあげられるくらいですし,弊社の調査でも浸透度は16%と低いです。
この調査で「ずっと狭い村にいたんだな」と感じたことが,ゲームフルデザインの本を作る衝動の1つになりました。
ゲーミフィケーションというと,よく「バッジ」や「レベル」などの手法が挙げられる。伊藤氏は,これらの手法を「ゲーミフィケーションが持つ価値を扱いやすくフォーマット化したにすぎない」と説明する。
伊藤氏:
ゲーミフィケーションは,ゲームのパーツを持ってくることではなく,「ゲームの面白さ」をプラスしていったり,使ったりしていくものであるべきなんです。
ただ,それはゲームを作った経験のある人にしか作れない。その結果,ゲームを作った経験がない人たちが「ランキングだったら作れる」「リワードだったら作れる」と簡単な部分にフォーカスしたんです。それが流行しましたが,短期間で消費されてしまいました。
岸本氏:
日本にはゲームに慣れ親しんでいる人が多いですよね。それでゲームを作ったことのない人が,「ゲーム好きなんで,ゲーミフィケーションも実装できますよ」みたいなことを言うわけです。それで広告代理店も「どうぞ,作ってください」となって,サービスに安易なゲームの要素を入れるんだけど,ユーザーとしては別に面白くない。ユーザーは目が肥えているから,どうしても本当のゲームと比較してしまうんですね。
伊藤氏は,2011年から2015年まで使われていたゲーミフィケーションを「狭義のゲーミフィケーション」とし,ゲームの面白さの本質を追求したゲーミフィケーションを「本質的なゲーミフィケーション」と定義する。そして本質的なゲーミフィケーションが広く使われるためには,それを言語化・構造化して一般化する必要があると考えたという。
伊藤氏:
言語化・構造化して一般化しないと,狭義のゲーミフィケーションのように使われなくなっていくと考えたんです。そこで,本質的なゲーミフィケーションを踏まえた「ついやりたくなる」という体験設計そのものを,差別化する意味合いも込めてゲームフルデザインと呼んでいます。
最近になって,ようやく本質的なゲーミフィケーションの話ができるようになってきたと伊藤氏は語る。その背景には,デジタルシフトが進み,誰もがアプリやWebサービスを作れるようになったことが挙げられるという。しかし,「とりあえず作りました」というアプリは見向きもされないし,事業としても投資対効果がない。そこで再びゲーミフィケーションが脚光を浴びるようになっているのだという。
伊藤氏:
2019年から2020年にかけてさまざまなところでアプリやサービスが大量にリリースされたんですよね。しかし,アプリとしては使いづらいものも多く,見向きもされなかった。その後「夢中になるものと言ったらゲームやエンターテイメントだ」という流れになり,ゲーミフィケーションが注目されています。
以前の流行と違うのは,僕らや岸本さんのような存在が「ただランキングを入れても意味がないですよ」と言えるようになったことです。「人間が本質的に使いたくなる欲求とは何か」といった建設的な議論ができるようになったんですね。
岸本氏:
昔みたいに「ポイントやバッジを入れればいいんですよね」という段階でなくなっていることもあり,今では「より深いゲーミフィケーションを活用したサービスを自分には作れない」と考えている人が増えているように最近感じます。
そういう人は,経産省の「『令和5年度地域デジタル人材育成・確保推進事業(ゲーミフィケーションを活用した人材育成等に関する調査事業)』に関する報告書」(関連リンク)や,伊藤さんのゲームフルデザインを読んでみてください。とくにゲームフルデザインは,「ゲームにはこんな要素が入っている」ということを網羅した本で,今までにないものになっています。
 |
伊藤氏は,ゲーム開発者が「どうやったら楽しんでもらえるか」という本質を突き詰めてゲームを作るから,ゲーミフィケーションも実装できるとする。
逆を言えば,ゲームを作ったことのない人であっても,ゲームの本質を理解できていれば,本質的なゲーミフィケーションを実装できると話す。本連載でも取り上げたコクヨの「しゅくだいやる気ペン」やエーテンラボの「みんチャレ」といった例はゲームの本質である「人を夢中にさせる要素」を理解していたからこそ実現したのである。
コクヨの「しゅくだいやる気ペン」は勉強を監視するのではなく,親子の幸せな姿を追求した学習ツール:身近なところにゲーミフィケーション 第1回

ゲーミフィケーションデザイナーの岸本好弘氏が,ゲーミフィケーションがうまく取り入れられている身近なアイテムやサービスを紹介していく連載「身近なところにゲーミフィケーション」がスタートします。第1回は子どもの学ぶやる気を引き出すコクヨの「しゅくだいやる気ペン」を紹介します。
習慣化アプリ「みんチャレ」は,ユーザーの積極的な行動を促し,幸せにつなげる:身近なところにゲーミフィケーション 第2回
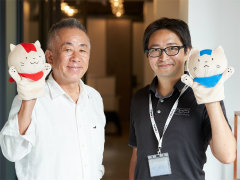
ゲーミフィケーションデザイナーの岸本好弘氏が,ゲーミフィケーションがうまく取り入れられている身近なアイテムやサービスを紹介していく連載「身近なところにゲーミフィケーション」。第2回はユーザーに習慣化を促す三日坊主防止アプリ「みんチャレ」を紹介します。
伊藤氏:
「人はなぜ夢中になるのか」ということをしっかり考えられるなら,別にゲームを作った経験は必要ないんです。たとえばマーケティングをするうえで,「どうやったら人の気持ちが変わるのか」といった行動変容を意識している人は,ゲーミフィケーションを活用できる。しゅくだいやる気ペンもみんチャレも,そういった本質的な人間の欲求を理解したうえで作られているんだと思います。
これからの時代,人間の本質的な部分の理解を促していける人材,「なぜこれをやりたくなるのか」を言語化できる人材が強いと私は考えています。狭義のゲーミフィケーションによく用いられたランキングも,「なぜ夢中になるのか」を抽象化してみると,別の手法に置き換えられる可能性に思い至る。こういった考え方は,これからどんなビジネスにも共通して必要なスキルになっていくと思います。
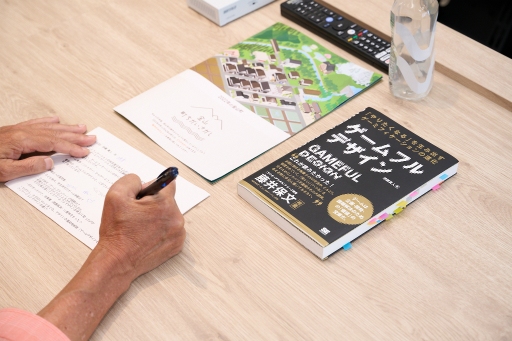 |
ゲーミフィケーション事業は,クリエイターではなくビジネスマンの領域
ゲーミフィケーションは万能ではなく,得意不得意がある。得意な領域は,「その人にとって重要だと頭では理解しているのに,優先度が下がってしまう行動を実行するよう促すこと」だ。たとえば健康診断や防災訓練は重要だと分かっているが,面倒だという理由からなかなか腰が上がらないという人も多いだろう。そうした行動を促すときに,ゲーミフィケーションは極めて有効であると伊藤氏は語る。
伊藤氏:
逆に人間の行動や不合理性が介在しない領域では,まったく使えません。たとえば工場のオートメーションを最適化するのに,ゲーミフィケーションは必要ないです。人間の合理的じゃない部分に対してアプローチをするからこそゲーミフィケーションの効果があるので,人間が介在しない行動に対しては無理です。ロボットなど合理性だけで動いているものには,あまり効果がありません。
教育や健康,環境などに関する社会課題と呼ばれているものの多くが,人間の行動変容で解決できるのではないかと伊藤氏は語る。例として,国政選挙などへの投票を促すゲーミフィケーションを挙げた。
伊藤氏:
誰しも「投票しなきゃ」とは思っているんですよね。そこをゲーミフィケーションで促してあげられないかと考えています。
たとえば,人間は本当に面白そうだと思ったら,たとえ遠方でもライブを観に行ったりしますよね。同じように「選挙は面白い」となれば,政治や候補者のことは分からなくとも,とりあえず白票を投じるくらいにはなるんじゃないかと思っています。
ただ,国政選挙には「投票率を上げたい」というミッションを明示的に持っている人がいないので,ここが大きな課題でもあります。ビジネスに置き換えてみると,破綻していると言えるかもしれません。
 |
また,小学生に向けた投資などの「お金の仕組み」の教育についてのゲーミフィケーションの可能性も伊藤氏は挙げていた。伊藤氏が子どものころは,「お金の流れや投資の仕組みを学ぶのはよくないことである」という風潮があったそう。しかし,社会人になって,急に投資やお金の仕組みについての知識が求められることに違和感があったという。
伊藤氏:
「お金があればあるほど幸せ」とまでは言いませんが,選択肢が増えるのは事実です。だから小学生のうちからしっかり学んでおくべきなんですよね。そういった想いもあり,みずほフィナンシャルグループとタッグを組んで,小学生からお金や投資,経営について学べるお金のおけいこアプリ「PochettePlus」を開発しました。
あとは,高齢社会が加速しているにもかかわらず,介護の現場で人不足が続いているということもよく聞くので,エッセンシャルワーカーの仕事にもっと人気が出たり,実際に現場で働いている皆さんがもっと前向きになれたりするようなことができないだろうかと考えています。
岸本氏:
ゲームフルデザインの考え方を持つと,誰かに言われたからやるのではなく,自分で考えて行動するようになるんですよね。皆がそうなると,日本の生産性も上がると考えています。
苦しくてもがんばることが良い意味でも悪い意味でも好きなので,仕事や勉強に楽しさを入れると皆やる気になるということを否定する人も未だにいます,ただ,セガ エックスディーがやってきたこれまでのゲーミフィケーションでの成功事例があるわけだから,それが広まることによって日本の未来ももっと良いものになるのではないでしょうか。
最後に伊藤氏にゲームクリエイターやデベロッパがノウハウを生かして,ゲーミフィケーション事業に参入するときのポイントも聞いてみた。
伊藤氏:
一番大きなポイントは,クリエイターからビジネスマンになるという意識でしょうか。自分自身もそうだったのですが,ゲーム業界の人は自分がクリエイターだという意識が強い傾向があるように思います。一方で,ゲーミフィケーション業界は,あらゆる課題解決の業界なので,当然非ゲーム/非エンタテインメント領域のビジネスマンばかりです。
ゲーム業界との違いをわかりやすい例で言えば,普段からきっちりとスーツを着て仕事をしている方もたくさんいるということ。その意味では,ゲーム業界とは別の世界とも言えるため,自分たちのいた世界の延長線上と捉えてはだめなんです。
そういったビジネスマナーを大事にしている人がいるのも事実ですから。それを覚悟してゲーム業界からゲーミフィケーション業界に来るべきだと思いますね。
岸本氏:
今回の伊藤真人氏へのインタビューを通じて,「狭義のゲーミフィケーション」から「ゲームフルデザイン」へと移行する新しい時代の始まりを強く感じました。この流れを加速させるには,“本質的な”ゲーミフィケーションデザイナーがたくさん生まれることが鍵になります。
印象的だったのは,「ゲームを作ったことがなくても,その本質を理解していれば,本質的なゲーミフィケーションは実装できる」という言葉です。つまり,誰もがゲーミフィケーションデザイナーになれる可能性があるということ。
書籍『ゲームフルデザイン』は専門的で内容も網羅的なので,初めて触れる方は,その中で「これだ!」と感じた部分だけでも,まずは1つ取り入れて実践してみるとよいでしょう。それが第一歩になります。
また,ゲーム開発者の方がゲーミフィケーションの分野に踏み出す際にも,多くのヒントが詰まっていたと思います。特に「クリエイターからビジネスマンへと意識を切り替える」という考え方は重要です。ゲーム開発のノウハウは,ゲーミフィケーションでも必ず生かせます。
ゲーム開発者であってもそうでなくても,本質を理解したゲーミフィケーションデザイナーがもっと増えれば,「世界は神ゲー」に近づいていく。そんな未来に,私はワクワクしています。
「セガ エックスディー」公式サイト
- 関連タイトル:
 書籍/雑誌
書籍/雑誌 - この記事のURL:






















